モンゴメリ日記
1895年
1895年1月6日(日曜日)
今日は怠け者の気分だったので、他のメンバーが日曜学校に行った後、私は(家にいて)横のソファーに座った。テニスンとドーナツと一緒に暖炉に火を入れ、心地よい静かな時間を過ごす準備をしていた。
その時、ドアをノックする音が聞こえた。私はそれがルー(エラズリーのロッジで会った人)であることを知っていたし、そうであったほうがいいと思った。しかし、私たちは楽しくおしゃべりとドーナツををしましたのよ。
1895年1月17日(木曜日)
ルーは祈祷会の後、ここにやって来た。小説を持って来てくれた。彼は毎回新しいのを持ってきてくれる。もちろん、小説はたくさんあるわけではないので、これは幸せなことだ。メソジストの牧師館にある調度品だ。確かに、この貧弱なタイトルでは面白い話かどうか、この世で判断するのは(本を選ぶのは)彼だ。しかし疲れた時間や暇な時間を埋めるには何でもいいのだ。私は非常に悪質なルーが帰った後、自分の部屋に行き、四六時中本を読む習慣がある。私はとても読書に夢中で、たとえそれがどんなにつまらない本でも、終わりを見るまでは手放せない。
料理のレシピのような退屈なものでもだ。私はいつもこのことについて良い決心をし(つまらない本なら熱中するのは良そうという決心)小説を手にしたとたんに、それを破ってしまう。
1895年1月27日(日曜日)
今日の午後は読書で美味しい時間を過ごした。読書は私にとって贅沢な時間だ。今はあまり時間が取れないので、静かな時間が取れたら、その時間を利用して座っている(読んでいる)。
本を読むのはとても楽しいことだ(本は知識を得る唯一の方法か)。最初の30分はロングフェローの本を読んだ。詩は私にとって決して魔力を失うことはない。間違いなくロングフェローより偉大な詩人はたくさんいる、しかし(彼のは)強く、壮大で、深い。甘さと優しさと気品に満ち溢れている。
そして、ホーソンの素晴らしい「緋文字」を読み返した。これは驚異的な作品だ。スタイルが非常に強力な本だと分析する。なんという人格の力。そしてそのような人物、つまり、深く、荒々しく、情熱的な人物像が描かれている。その主人公は男で、ヒロインは女。人間の偉大な心、その多様な鼓動に強く訴えかける。情熱と苦痛の相。
1895年1月29日(火曜日)
ウィル・モンゴメリーが土曜日の午後に来て、私をマルペケまで連れていってくれた。ジョン・モンゴメリーおじさんはもうじき死ぬ。私たちはその日、夕方湾を渡った。
大きな吹雪の中、たくさんの家があった。それは悲しいほど変わっていた。この家の生命と魂は失われていたのだ。私は哀れなジョン叔父さんに会いに行った。もしかしてあの痩せっぽちのおじさんが、昔家を揺るがすような声と笑い声であった?大きくて元気なおじさんだったのか。
精神的な変化もさることながら、目のかすみ、不明瞭な言語、曇りなど、肉体的な変化と同様に知性も哀れなものであった。
昨日の夜、ポートヒルに戻ってきたんだけど、ウィルが今日の朝、家に連れてきてくれた......。
私たちは、今日は薪がなくなって学校で凍えそうになったので、2時になってから管理委員会に致命的な復讐を誓って下校し、帰宅した。
1895年2月18日(月曜日)
金曜日にエディス・Eが私に来るようにと連絡をくれたので、学校が終わった後、私はその場所に行ってきた。
土手の上を泳ぎました(ぶらついたのであろう)。いつものように楽しい時間を過ごした。土曜日の夕方、ルー(前記のエラズリーのロッジで会った人)が出てきて、私を彼の家に連れて行き、日曜日の夜まで滞在した。その往復のドライブはとても楽しかったのだが、(ルーの家では)あまり楽しめたとは言えない。そこにいる間中、サディ(ルーの姉妹であろうか)はとても無味乾燥で、クラゲのような女の子だ。D(ディスタンス)夫人は、うるさいほどの親切心であなたを死ぬほど心配させる。あるいは親切心のつもりかもしれないが。
日曜日の夕方、車を走らせると、完璧なまでに晴れていて、きらきらと輝いていた。西の方角にはレモンの灯があり、大きな明りの宵の明星が液体のように輝いている。死にゆく日の慌ただしい頬に、宝石をちりばめたようだ。その日車を走らせると、だんだん暗くなってきた。ビロードのような空は星屑で覆われ、トウヒの木はその姿を現した。その神秘的な暗さ!
哀れなジョン・M叔父さんが死んだ。ポートヒルから電話で知らせてくれた。それは予想していたこととはいえ、ショックだった。(モンゴメリは電話の時にはちゃんとteleponedと表記しているので、ただのcollとなっていた場合は人による呼び出しと判断した)
1895年3月10日(日曜日)
金曜日の夜、学校の帰りにイーディスの家に行き、一晩中過ごした。そこではいつも楽しく Edith E.の素敵な家がうらやましいくらいだ。私が得たいと願っているものが、彼女には全て叶っている。
それでも、私は彼女と入れ替わるつもりはない。実際、私の小さな試練や苦難――それは常に私にはあった――
立場を交換したいと思う人に出会ったことは、今まではまだ一度もない。性格も含めてね。
1895年3月14日(木曜日)
昨夜はValley教会を支援するための社交場がMillar氏の家で開かれ、Lou(ルーか)と招待されました。私は本と空想の仕事に別れを告げ少し後悔した。というのも、私たちは昔ながらの乾いた時間(教会での社交)を過ごすことになるだろうと思ったからだ。
その場に到着した私は、すでに無表情で並んでいる部屋を通り抜け、2階の空き部屋に逃げ込むと、そこには6人の少女たちが私のラップを外すのを待たずに、女の子たちがチリンチリンと鳴いていた。
そして座ってルーが持ってきた手紙を持ち出して調べた。ひとつは、編集者からで、とても嬉しい驚きだった。
トロント・レディース・ジャーナル誌は、私が送った詩「湾岸で」を受け入れてくれた。そして、賛辞の言葉も添えてくれた。詩はお金にならないのだ。しかし、その「名誉」がすべての報酬である。
他の手紙を読んだ後、私は帽子を脱いで前髪をふわっとさせながら(前髪が帽子のつばのように見えてひたいを隠し表情が引き締まるの)、次の場所へ向かった。下へ降りた。音楽が呼ばれていたので、私は疲れるまでその隙間を埋め(演奏したのか)、そしてモード・ヘイズとリリー・ダルトンの間に陣取った。みんなが少なくとも、刑務所の犯罪者のように思えた。
話すと死刑、笑うと死刑。私たちは、自分たちで話題を作らない限り、楽しいことはないと思っていた(どんどん話せということか)。モードと私は、お互いに無謀なスピーチをし始めた。
私たちは自分たちの機知に笑い、年配の女性たちが私たちを不審に思うようになった。なぜならこのような教会の社交界は、まさに「ケーキを取る」ような愚かさだからだ。人々はより初々しく、その時は、他の時よりも絶望的に面白くないし部屋は暑い。みんな邪魔なんです。主な用事は
1. プリムに座る。
2. あなたの年齢に応じて控えめなまたは不賛成な顔。
3. 他の人が立ち上がろうとするゲームでは、後ろにぶら下がって不機嫌に振舞う。
4. 4、消化の悪いものをたくさん詰め込んで、その影響を受ける。
一週間、あなたのそばにいてください。
である。
私は少なくともウェイターになることで、このプログラムの最後の番号を免れた。もちろんケーキを運ぶのに疲れましたよ。
でも、その方が、私の抵抗に耐えるよりずっとましだ。甘いものをたくさん食べて、激しい頭痛と不機嫌な顔で家に帰る。悪意に満ちた気性だ。
夕食後、キスゲームが始められ、他のすべてのゲームが盛んに行われた。
私はそのような遊びはしないので、ルーを速やかに担ぎ上げて帰りました。もし、私がそれを守るだけの道徳的な強さがあれば、私はもう二度と教会に行かないことを誓うだろう。
1895年3月28日(木曜日)
プリンスエドワードアイランド、ビデフォード
春の美味しいお天気が続いている。道路はどんどん陥没して、坂の頂上は雪の冠からかろうじて顔を出している。冷たい白い土手の足元には、小さな水たまりが打ち寄せていて、次第に憐れなほど蹂躙された姿になっている。太陽は、その処女の純粋さを冒涜している。(雪が溶けてぐちゃぐちゃになっている)
これはすべて詩だが、ドアの外に足を踏み出すたびに足首の深さまで泥まみれになるというのは、実にくだらない散文だ。(詩では自然の様子に感情がこもっているように表現し、散文では事実をそのまま言う)
この晩はイングランドさんのところで過ごした。私があそこに行くのが好きな理由のひとつは自分の家のようにくつろぐことができるのだ。彼らはあなたに迫害を加えることがない。
楽しませようという気負いがない。自分流に楽しむことができる。
1895年4月6日(土曜日)
今週は泥とぬかるみのせいで大変な一週間だった。木曜日の夜E(エスティ)夫人と私は車でEast BidefordにあるMcKays氏のところへ行き、そこでキャンベル審査官(教師がちゃんと勉強を進めているか検査する人)に会った。彼は翌日、私の学校を訪れるので、私はかなり気分が良かった。
緊張する。昨日の朝は早くから学校に行き、掃除と手入れをした。そして、子供たちを訓練した。やがて彼がやってきたが、事態はそれほど悪くなかった。子供たちはよく働き、秩序は素晴らしいものだった。彼は(学校の様子には)満足していると公言し、半休をもらった。
1895年4月12日(金曜日)
ビッドフォード
今日、エラズリーで大師団が開かれ、私は朗読をする約束をしていた。今夜の市民集会には、ルー(ディスタンス)が私の後に出た(何か講演した)。会場は混雑していた。
私はCaleb's Daughter」とアンコールの「The Schoolmaster's Guests」を朗読した。
エドウィン・シンプソン(Edwin Simpson)が、教師をしているベデック(Bedeque)から来ていて、少し話をした。短いおしゃべり。
1895年4月15日(月曜日)
昨夜は教会でイースター宣教師の礼拝があった。私は詠唱と朗読をした。ルーは私たちと一緒に降りてきて、歩き方が悪かったので、エスティ夫人が注意した。彼は一晩中いた。E牧師(エスティ夫人の夫)が不在でなければ、あえて延長することもなかっただろう。
今朝、エスティ夫人が起きると、どのドアも薪の丸太が高く積まれていた。
フレッド・エリスとジョス・ミラーがやったことがわかったよとクリフ・ウィリアムスが言った。ピクニックに行くようなものだ(ピクニックに行くのを邪魔したと言う事か)。しかし彼は(クリフは)全く行かなかったので、その計画は頓挫してしまった。
今朝起きたとき、ドアを開けなければならなかったエスティ夫人がかわいそうだ。
1895年4月20日(土曜日)
この一週間は何事もなく、まるで別の日のような一日だった。ルーは木曜日に出かけた。今日も夕方から夜にかけて、手紙を持って来てくれた(ルーは郵便局に関係があったのか)。ひとつはRev.,ハリファックス・レディース・カレッジのレーシング牧師からのもので、私がそのことについて書いたものです。彼は、私の勉強があまりに進みすぎているので、このままではいけないと思ったと書いていた。
学部生として入学する気がないのなら、ダルハウジーで選抜コースを受けることを考えなさいと、この世でこれ(ダルハウジーの学部生になること)ほど欲しいものはないのだが、無駄なことだ。というのも、学士課程を修了する余裕がなかったからだ。もし進学することになれば、私はおそらく選抜コースになる。本物の大学で1年過ごしたいと思っている。作家になるという野望に役立つと思うからだ。
私は休暇が必要なので、休暇が来たら心から喜ぶ。私は毎日水に濡れている。風邪をひいてしまった。全く体調が悪い。
1895年5月6日(月曜日)
プリンスエドワード、ビデフォード
地球は愛らしさを、春は愛らしさを忘れてはいない。美味しかった
今日も。お茶を飲んだ後、エスティ夫人と私は駅まで歩いて行き、帰りにP.O.(郵便局)に寄った。私は休暇の後、そこに乗り込むつもりです。Estey夫妻は6月上旬に別の巡回先に行くので(牧師館は牧師の持ち物ではない)、新しい居住地(私が下宿する所)を探す必要がある。私たちが郵便局を出ると、ルーがやってきて、みんなで涼しい中を歩いて帰った。
素敵な夕暮れ。ここに来て、私とルーは中に入らず、迂回してベランダの手すりに腰掛けて、しばらくおしゃべりをした。1時間 とにかくおいしい夜だった。月光が金色の霧のように降り注ぎ、木々や草の上にシャワーのように降り注ぎ、目の前の湾は輝きを放っている。風は6月の風のようにやわらかく、カエルが鳴いている。すべての心配事や悩みは生きていることの幸せと喜びで、溶けていくようだった。私は、まるで心も体も軽くなったような気分で子供のように自由である。
1895年5月23日(木曜日)
キャベンディッシュ
今週はとても静かで楽しい日々を過ごしている(休暇でキャベンディッシュに戻っていたのか)。今日の夕方、ルゥと私は祈祷会の後、時間が早すぎたので、道路沿いを散歩した。それはそれは素敵だった。木々や野原は繊細なフェアリーグリーンで、スミレは紫色。
夕方には、夕陽が、トウヒの下の草むらから顔を出し、漆黒に染まる。池や湾や海が "火と混じったガラスの海"になるまで。
ペンシーは祈祷会に出ていて、明日は私たちを誘ってくれました。
1895年5月28日(火曜日)
キャベンディッシュ、P.E.L.
今、町から帰ってきたところだが、ジャンケンの後でかなり疲れている感じだ。土曜日に郵便屋さんと一緒に駅まで行ったのだがとても大変だった。疲れるドライブだった。6時ごろに町に着いて、すぐにメアリーおばさんのところに行った。その後メアリー・キャンベルが現れ、私は驚きと喜びを感じた。
私たちはノーマンの下宿に行き、街中を案内してもらい、楽しく過ごした。
日曜日の朝、私たちはザイオンに行った。私はあの教会が大好きだ。私たちはサザーランド氏の説教を聞きたかったのだが、急病のため彼の説教は聞けなかった。
ケンジントンホールの堂々とした青年がその場所を提供した(代わりに説教した)。彼はとても背が低く説教壇の上に薄いポンパドール(髪型だが、小さな髷くらいしか髪の毛がないと言う事だろうか)がやっと見えるくらいで、文法は野蛮であった。彼が告げたテキストは、「詩編第11章16節」だった。――エコーが「どこ」と答えるか――この問題のある(難解な)テキストを彼は扱った。(彼の説教は)その題材の発見不可能な性質に見合ったもの(ちんぷんかんぷんな物)であった。
夕食後、ジャック・S(サザーランド)が降りてきて私に会った。夕方、ノーマンと私は一緒に教会に行った後、プリンス・ストリートを散歩した。
メアリーと買い物をし、昼に大学へ行った。すると、そこにはA博士が部屋で学術試験の監督をしていたのだが、彼はとても喜んでいた。
私たちを見て、私たちは1時間近くも座っておしゃべりしていた。私は彼に、自分が来年はダルハウジー大学の選抜コースに進むと言ったが、彼は私には「偉大な文学の才能があるのだから、それを磨くべきである」と言い、さらに良いアドバイスをしてくれた。
そして、私の成功を信じて疑わないと言った。このような言葉はアンダーソン博士のような人からの言葉は、実に心強い。その後私たちはキャベン氏は相変わらず陽気で、ロバートソン氏、ショー氏も同様だと言って(話し合って)帰った。メアリーは午後の列車で帰らなければならなかった。
お茶のあとセレナ・ロビンソンが訪ねて来て、楽しくおしゃべりした。ジャックとウィル S. とジャック・ゴードンが降りてきて(come down
となっているがやってきての間違いであろう)夜を過ごし、とても愉快な時間を過ごした。
今朝は早い列車に乗るために、ヒバリとともに起きなければならなかった。今朝は早起きして列車に乗った。
ハンターリバー(駅)は魅力的だった。この国は今、まさに "エデンの園"だ。花は全部咲いている。今日の夕方、ルゥと私は恋人の小径を散歩してきた。桜の花が咲き乱れる季節になった。
(桜が咲くのも5月の終わりだから日本より2ヵ月も遅いでしょう)(ハンター・リバー駅はブライト・リバーと名を変えて赤毛のアンの中に登場しています)
1895年6月5日(水曜日)
月曜日からまた仕事を始めたが、33人の生徒が集まり、その半分は初級クラスなので、仕事量は相当なものだった。放課後はパーソネージでお茶を飲む。まるで家に戻ったような気分だった。お茶の後、E夫人と私は楽しいドライブをした。火曜日の夜はMillars家で過ごした。
1895年6月6日(木曜日)
エラズリー
私は、自分の人生の中で、記録すべき経験をした。一生分の経験がある。どんな物語にも始まりがあるはずだ。
そして、ここに最初に来たときまでさかのぼらなければならないだろう。ルーツだ。ビデフォードに来て間もなく、私は郵便局からそう遠くない丘の上にいることに気づいた。そこには、大きな古風な家が建っていた。かつては美しかったが、今はひどく放置され、荒れ果てた土地だ。調べてみるとその家はかつて裕福な家庭のものであったが、逆境が訪れた。
そして、何度かの変更を経て、すべて下降線をたどった後、この財産は現在の所有者の手に渡ったのだが、彼らは噂に違わぬ人物だったそうだ。
異様で汚いアモス・マッケイが学校に来たとき、彼がここに住んでいることを知った。マッケイ夫妻は彼を養子にしたのだ。さて先週の火曜日の朝は......。
アモスは私宛の手紙を持って現れた。私は内心、不安な気持ちでそれを受け取った。これに関して、何らかの罪や不作為を犯して、その責任を追及されることを予期していた。しかし、私はこれを読んだ。
"モンゴメリーさん
あなたがここに来てから一度も私たちに会いに来ていないので、私はあなたが来ることを望む。いつ来るか、この手紙の持ち主(生徒、アモス)に知らせてください。本当にありがとうございました。
アーチボルト・マッケイ"
もちろん、私は行かなければならないので、木曜日の夕方に行くという手紙を送りました。そして、モード・ヘイズやその他の人たちは、すぐさま、「これは何だ?」と思うようなものを食べに行こうか、などなど、いろいろと相談にのってくれた。私はほとんど気が狂いそうでした。
今晩は学校から帰ってきてから、服を着て、願わくば私自身は1000マイルも離れている場所にいたかったが。私が玄関のドアをノックすると、大きな音がした。
急いで、急いでという、ヒソヒソ話!? ドアを開けると、そこは薄暗く埃っぽい大きなホールで、家族全員が一斉に私を出迎えた。
アモスは、壁伝いに滑ってきて、まるで小さな妖怪のような姿であった。彼は異常な服を着ている。最初に私を出迎えたのは、この家の女主人であった。髪を耳にかけた枯れ果てた老女である。
50年前のファッション。キスされるんじゃないかとビクビクしていたが、慌てて彼女の手を離し、彼女の主君に私の手を差し出して、これを免れた。
その人は文字通り、ヒゲとボロ布だらけの醜い年寄りだった。続いて、後方には息子と娘がいたのだが、彼らは私にまったく熱烈な挨拶をしてくれない。おそらく、耳が聞こえないという素晴らしい理由からでしょう。
私は押されたり引かれたり追い詰められたりして食堂に入り、そこでマッケイ夫人が私の帽子を取り、お茶を入れる間、アーチー老人と話すようにとのこと。彼はずっと呟くような不明瞭な声で、次々と質問を浴びせられ、私があたふたしている間にも、私はテーブルから目を離さず、モードが言ったことを思い出しながら、自分の答えを考えていた。
そして、「半分は語られなかった」こと(噂よりひどいこと)を目の当たりにして、私は落胆した。
その時の私の気持ちは、言葉では言い表せないほどだった。彼らは本当にこんなものを食べろというのだろうか。床が開いて、私を飲み込んでくれればいいのにと思ったが、そうならない以上、何か食べなければと、不機嫌に戦いに身を投じました。私はむしろ後者になると信じていた。
一度も洗っていないようなカップに、おばあさんがお茶を注いでくれた。買ったときからずっと洗っておらず。内側も外側も古代の茶渋でびっしり汚れていて、私はカップのきれいな場所を見つけて飲もうと思っても、なかなかうまくいかなかった。
目をつぶってグッと飲み干すと、その味は見た目の印象とほぼ同じだった。サワークリームの巨大な塊が浮遊しているような、残虐な醸造物だったからだ。(紅茶にクリームを浮かべたようなものだったのか)
泥海の氷山のようなものである。このとき、私は少し回復するとすぐに私は目を開け、皿の中身を見て何が食べられるか確認した。
あえて食べる。それは巨大な塊でほぼ埋め尽くされていた......まあ、それは意図的なものだったと思う。おずおずと覗き込んでいるのは、パイだが、皮のような縁取りのある厚い茶色の皮。その中には
薄緑色のぬるぬるした塊があり、おそらくルバーブ(食用ダイオウという、一般的にはパイの材料である)の煮込みと思われるが、モードはゴボウだと言い張る!! そして、大きなスプーン一杯の粗めの黒砂糖。
その上に、酸っぱくてこってりしたクリームが混ざっている。この魅力的な混合物はさらに、「クランベリーサーフ」(粉のようなもの)を大量にかける。
いやー、これは絶望的だったね。スプーン一杯は食べたが、もし死んでもいいくらいだ。もう一杯は食べられない。そこで私は、1インチもある大きなパンを手に取り、厚いバターが上に、こんなにバターが!? その中に髪の毛が3本入っていた。
一口ごとに紅茶をゴクゴクと飲み干す。実際に一切れ全部食べてからパティパン(何か載せてあるパン)を喉に詰まらせる。正直、一口ごとに吐くんじゃないかと心配になった。
私はこのときの惨状は忘れられない。食べ物が粗末なのは気にならなかったが、清潔でさえあれば、調理が悪くても大丈夫なのだが。
すべてが終わった後、私たちは応接間に入り、そこで私は残りの時間を過ごすことになった。
その晩は、主人や女主人と話をした。床は醜い赤のマットで覆われていた。椅子には同じくおぞましいかぎ針編みの小物入れ。
紳士は「マギーの作品だ」と誇らしげに教えてくれた。窓には汚れたレースのカーテン、壁には驚くほどたくさんの作品が飾られていた。新聞紙面、カード、年鑑、賞品の豚のカットなど。
私たちの会話を絵に描きたいくらいだ。しかし、一つの例を挙げれば十分であろう。
「単語の翻訳とか、そういうのわかるか」と老紳士が聞いた。
「ああ、はい」と私は軽率にも答えてしまった。
彼は私が持っている新聞に非常に汚い指を動かして、「それは何だ」と尋ねた。
"その言葉をラティング語に直すとそれは何だ!"
"これ?" 私は弱々しく息を呑んだ、彼は私にその新聞を全部訳せというのだろうかと思った
"そうだ、ラティング語で "新聞"って何?
新聞は帝国時代よりも近代的になっている。
私は知らなくても仕方ないのだが、アーチーには無理でした。このことを理解させる(私は知らないと言うと)と私の古典的な学問に対する評価が危うくなる。
しかし私の知っているラテン語の単語はすべて記憶から消えてしまったと厳粛に断言する。
溺れる者は縋るが如く、「パピルス」と口走ったのだ。藁のことわざのように。
しかし、それは目的にかなったもので、哀れな年老いたアーチーは、それを単に不思議だと思ったのです。「デ・アー、デ・アー」(さすが先生だ博学だ)と、私のことを深く驚嘆するような口調で、注視していた。
しかし、何事も生きていればいつかは終わりが来るもので、とうとう私は這ってでも帰りたくなった。本当に私たち学徒兵には悩みがつきものだ。
そして、ポープの言葉、"A little learning is a true" (習うより慣れろ)を痛感した。
1895年6月17日(月曜日)
昨日の朝、説教を聞きにに行ったが、それが私がここで聞く最後の説教だ。Bidefordの教会では、明日からEstey氏が会議に出るからです。私はびっくりした。この発表を聞いて、私はここでの残りの時がいかに短くなったかを実感した。I
忙しさにかまけて、あまり考えていなかったのだが、突然思い知らされた。その時、鋭い衝撃が走った。去るのはとても残念だ。私はとても楽しかった。ここで楽しい時間を過ごし、多くの友人がいる。
今日の夜、ルーと私、ジョージ・ウォルシュとバーティ・ウイリアムズ、チャーリーとモードとヘイズは説教を聞きに11号地まで車で行き、楽しいドライブをした。異様な集団がそこにいる。とんでもない人たちが、とんでもない格好で非日常的な服を非日常的な方法で着ると、その結果は超非凡。
今日の学校には始めは40人の子供がいて、今では60人以上いる重い学校だ。
エスティ夫妻は今日旅立ちました。エスティ夫人を見送るのは、とても残念なことだった。さようなら! 彼女は私にとても親切でした。
トロント・レディース・ジャーナルに記事が受理されたんだ。まだ報酬はないけれど、でもそれは
いつか来るかもしれない。(モンゴメリはこのころまでに詩が1編掲載されていたが、報酬は雑誌の購読料だけだった)
1895年6月24日(月曜日)
Bideford校での最後の月曜日がやってきた。最初の月曜日を忘れることはないだろう。月曜日? 私の人生の一つの章がもうすぐ閉じられる。時の見えない指がすでに(ここでの)最後のページをめくっている。そしてそれは喜びと労苦の様々な章であった。子供たちと別れるのは残念なことだ。ほとんどの子供たちが私の心の中に入り込んでいる。
ジョン・ミラーは私のお気に入りの弟子で、男らしい小さな仲間だ。アーサーミラーもいい子だが、ひどくいたずら好きで、
ゴードンは私の嫌いなアンチェイン(鎖から解くと言う意味で暴れん坊か)でした。私はこの子が好きで、ずいぶん迷惑をかけられた。
アリス・ミラーはまだ "子供"だ。薄くて、日焼けして、徹底したおてんば娘で、いつも男の子と一緒に走っていて、特別に愛すべき存在である。
そばかすだらけの小さなモード・マッケンジーは、妖精のような短い頭をしている。絹のような赤いカールと「かわいい」顔はいいものだ。
フレッド・エリスとロッティ・エリスは、私はこの二人を好きになることはなかったが、問題を起こすことはなかった。一緒にいて落ち着かない。
エマ・エリスは最悪の生徒で、他のどの生徒よりも私に迷惑をかけた。
他の人たちを合わせると クラウドとレビー・ウィリアムズ、レーグ・ゴリル、モード・エスティはみんな大切な弟子だった。
それから、「Yard」(スコットランドの言葉で「地球」を意味するが、駆け回っていると言う意味であろうか)の子供たちもいる。
しかし、中には残念なことに、発展する見込みのない子もいる。
もっといいことがある。マッカーサー家の二人の少年、アーサーとコーネリアスは、二人とも完璧な小悪魔と恥ずかしがり屋を擬人化したものだ。彼らは単に学ぶことができなかった。
ベルとガーフィールド・マッカーサーは、少しばかり明るかった。
ベルとリジーとマクファディンはとてもかわいい女の子でいい生徒だった。
モードとアニー・マクドゥーガルは静かで平凡だった。
その後、エラズリーにやってきたモード、バーティ、クリフォード、アイリーン、エラ・ヘイズは、教師が望んだとおりのいい生徒たちだった。
ウィリー・キャノンとオルドレッド・イングランドはスマートでいい子だったが、フランク・グラントは
賢くて、うぬぼれが強くて、落ち着きがなく、いじめっ子のような......非常に困った生徒だった。
マーフィー、サッズバー、ハウエルは、一括して「まあまあ」と分類されるかもしれない。
また、欠点と美点が混在しているような人も少なくなかった。実際、最後の分析になると、私たちのほとんどがそうなのだ。
1895年6月28日(金曜日)
プリンスエドワード州、ビデフォード
「杖はユダから離れた」――私はもうビデフォードの教師ではありません。(ユダは私のことで、杖はキリスト教の例えで王権のことで、杖が離れたユダとは、教師の資格から離れた私と言う意味で使っている)
しかし、私はとても気分が悪いので、辞めなければよかったと半ば諦めている。今朝、私は早く学校(ビデフォードの学校)に行った。子供たちは皆、花束を飾りつけに持参し、男の子たちは大きなシダを両手いっぱいに取ってきて、飾れるところは全部飾りました。
旧校舎は、いつもと違う華やかさを放った。17人の来客があり、試験(私に教師に務まるかどうかの試験)は見事に終了した。試験終了後、生徒たちから住所録とセルロイドに銀箔を貼ったとても可愛い宝石箱を貰った。女の子たちは皆、そして私も泣き、その場にいたほとんどの女性も泣いた。そして私たちは「ゴッド」(イギリス国家)を歌った。
そして、ウィリアムズさんのところに行き、お茶を飲んだ。帰り道、私はさびれた学校に一人、別れを告げるために寄った。そこに立っていると、初めて敷居をまたいだ日、震える混乱した若者(私のこと)の姿が思い浮かんだ。
私が統治することになる子供たちよりも幼稚に感じられた。これは私にとってはとても幸せな年であり、あの古い学校を無条件に思い出すことはないだろう。とても優しい気持ちになりました。
1895年7月2日(火曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
もうすべてが終わった。この数日。
土曜日は別れの挨拶をし、夜はDystant氏のところへ行った。日曜日の夕食後、ルー(オレンジ会のルー・ディスタントとも長らく付き合っていた)と私はフォーティーンロードにドライブに出かけた。
その後、Millar氏の家でお茶をした。お茶の後、私は彼らに別れを告げ、私たちはクラス・ミーティングに上がった。教室が終わるとわかれを言うのが難しいものもあった。
イングランド氏の家に行って、短い会談をした。ヘイズさんの家に戻ると、みんなベッドに入っていた。
玄関ホールで、私はどうしたらいいのか分からないまま、居心地の悪さを感じていた。私はこの1年間、ルー(ディスタント)と行動を共にしてきたが、私は決してルーに私が彼のことを気にかけているなどという(振りを見せた)ことは全くない。友人として。それどころか私はかなり苦心して、あらゆる方法で間接的な方法で、彼を落胆させる(自由があるんだから)ように勤めてきた。それでも私は、彼がどうしたら(私を気にせず別れてくれるか)と思っている。(アッシー君に使ったのだから)
このところ、彼はひどくブルーになり、落ち込んでいる。
私がラウンジに座っていると、彼がやってきた、その顔をひと目見て、それで十分だ(恐ろしい濡れ場が来る顔だ)
私たちはとても恐ろしい話をしました。詳細は書きませんが。ルーは私を愛していると言ったが、私が決して彼を励ましたことは一度もなく、彼は私に会いに来ずにはいられなかったが、彼のことを気にかけていた。(来たら嫌だなと)私はとても切り刻まれた。ルーがこれほどまでに気にしているとは思わなかったが、彼はただ単に気が散る。私は彼に、あなたはそのうち私のことを忘れてしまい、もっといい人を見つけるだろうと言った。
しかし、恋する求婚者にありがちなことだが、彼はそれを受け入れることができないようだ。彼はとうとう行ってしまったので、私はとても残念に思った。(もう少し醜態を続けましょうよと)彼はもう少し威厳があってもよかったかもしれない。彼の感情の放棄(あきらめの良さ)は、むしろはっきり言って気持ち悪い。
翌朝は5時に起きて荷造りを済ませた。疲れがたまっているようで、頭が痛んだ。Maud HayesはS'Side(サマーサイド)に受験に行くことになり、私たちはS'Sideに出発した。8時15分にエラズリー駅に着いた。ルーも仕事で行くことになり、一緒に来た。
私は旧校舎が見えなくなるまで眺めてから、ため息をついて振り向いた。ルーは私の向かいに座っていて、やつれた顔で恐る恐る見ていた。私はまったく気になんかしない。そのため3人組の中でモードが唯一陽気だった。(モード・ヘヤーズはサマーサイドで降りて、私はその先のケンジントン駅まで行き)ケンジントンは、ドミニオンデー(カナダ連邦が成立した記念日)のため、どこもかしこも閑散としていた(休日だった)。(マクニール)おじいさんはトラックワゴン(農業用の広い荷台がある馬車)で出迎えてくれた。私は暑くて埃っぽい、とても疲れるドライブをした。
ほとんど消耗した状態でここに(我が家)到着した。それ以来、私はとても惨めで寂しい思いをしている。
最初の週にキャベンディッシュにホームシックになったように、ビデフォードにホームシックになった。
1895年7月21日(日曜日)
私は孤独を克服し始めたところだ――私は半分狂って準備していた。
今日の午後、ペンシーとアレックと私はニューグラスゴーの教会に行った。私たちはもちろん出てきてからも(教会に入ってからも)、可哀想なアルバート・レアード夫人に笑いっぱなしだった。通路を歩いてきたその人は、私たちの前にどっかりと腰を下ろした。ボンネットの冠からミシン針と1ヤードの白糸が垂れ下がっている。
背中越しに 彼女が頭をピクピクさせるたびに(彼女はそのことで有名なのです)。針が飛ぶん(跳ねるのだろう)です。その姿は実に滑稽で後ろの席の男の子たちが、「最新式の飾りつけだね」と言うのが耐えられない。
私たちはマミー・モファットの家でお茶を飲み、夕方にはバプテスト派の教会に行った。New Glasgowの教会。ドライブにはもってこいの夜で、私はそれを楽しんだ。
1895年8月16日(金曜日)
キャベンディッシュ
セレーナと私は楽しい時間を過ごしている。水曜日にリアンダーおじさんが新しい花嫁を連れてきた。3人目の花嫁だ。彼女は容姿が悪くない。しかしどちらかというと平凡な顔立ちをしている。一番の魅力は、きめ細かい顔色と明るい金色の髪。彼女は親切で楽しい人だが、全く知的でないようだ。
彼女はまったく無学なようで、ひどい言い訳をする。普通の文法で、賢くて潔癖な叔父さんの花嫁としては、かなり異様だ。
リアンダーは、しかし二重の男やもめで(二回夫人と死に別れている)ので、大家族でもないのに"単純な" (平凡なという事であろうか)男は結婚の相手を選ぶ余裕はない――結婚するとしても!
明日、セレーナが行ってしまうので、とても寂しくなる。
1895年8月17日(土曜日)
キャベンディッシュ
今晩は寂しい家だ。今朝は大移動があったんだ。L(リアンダー)のおじさんは行ってしまったし、ペンと私はセレナをニューグラスゴーに送っていった。彼女がいないと寂しい。私たちの陽気な騒動、内緒の話、小さな企み、計画がすべて終わってしまう。私はベッドでゆっくり泣くことにしよう。
1895年8月25日(日曜日)
今週はとても忙しい一週間だった。先週の月曜日ヴィニー・マクルーアが私の仕事を手伝いに来てくれた。
それ以来、私たちはコツコツと縫い続けています。ヴィニーはとても陽気な女の子で私たちはいくらでも楽しむことができ、夕方には仕事も一段落して少しばかり空を飛んでいます(空想しているということか)。
1895年9月5日(木曜日)
...今週、Ch'TownのPerle Taylor(ペルレ・テーラー)から手紙が届きました。彼女は去年はレディース・カレッジでハリファックスにいた。手紙で来年は彼女とルームメイトになりたいと言っている。私は彼女のことを全く知らないのだがそうする。しかし私はそこにはほかに誰も知らない
見知らぬ者は見知らぬ者と同じである。ペルレはシャーロットタウンのテーラー博士の娘だ。
1895年9月15日(日曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
明日からハリファックスに行くので、今日はもうここしばらくいた家にいる最後の夜だ。 今週はずっと準備で大忙しだった。疲れと不安で、希望や期待など微塵もなく、落胆している。ハリファックスに行くことになったことを誰も本当に共感していないようだ。 祖母は私が行くことを望んでいるので喜んでいる。 しかし私がなぜ行きたいのか、その理由を理解しているわけではない。 経済的にも少し援助してくれるそうだ。
教師をして得た180ドルの給料はH.L.C.(宿舎であろうか)の食事代とダルハウジー大学の授業料に当てる(当時の価値では180万円に当たる)。
祖父は私が行くことに何の関心も示さない。 キャベンディッシュの人々は概して、やや軽蔑的な態度で不承諾の意を示している。しかし、アルバート・マクニール夫人は何を言っても気にしない人だ。
彼らの意見を下品に表現している。
先日彼女は私にこう言った。「いったい、あなたに何が必要なのかわからないわ。 これ以上の教育を得たいと言うことは 伝道師にでもなりたいのか?"
さて、私はアルバート夫人やその仲間の意見など全く気にしない。 私の心、です。しかし私はA(アルバート夫人)さんのことが好きだ、彼女の欠点も含めて。 旧友のこのような態度に私は傷つき、傷つけられたように感じているのだ。 知人です。他の人の言葉は嫉妬したり卑屈になったりする。千本の針で刺されたように苦しみに変える。もし私に一人でも自分の意見を大切にしてくれる友人がいたらこう言ってくれるでしょう。
あなたの言うとおりです。あなたには、適切な訓練を受ければ、何かを成し遂げる力がある。 知的訓練が必要です。どうぞ!」それはどんな慰めになるだろうか?
(モンゴメリはのちに、ダルハウジー大学で受けた教育は、すでに知っていたことばかりで無駄な事であった、こんなことではイングランドとスコットランドにでも旅行して見聞を広めた方がよかったと言っていますが、経験の中から機智に富んだ話を編み出そうという、作家が望むような願望は特殊な事なので、その能力は容易には得られない物でした)(更にモンゴメリは大学の授業でも得られなかった経験を、次には新聞記者になって得ようとします)
ハリファックス 1895年9月17日
この日付はきっと大文字で書く価値があるね。この4年間、私がこの日を迎えたときに、この見出しを日記に書くべきことが、私の目の前で踊っている。(今や私はダルハウジー大学に通うという見出しを日記に書けることになった)
野心と希望に満ちたウィル・オー・ザ・ウィスプ。(成功したいと言う魂の意思)ついにこの日がやってきたが、結局のところ私は本当にどう思っているかわからない。
それは私が今までしてきた労苦と自己犠牲と闘争に本当に値するものなのだ。この古い言葉には、かなりの真実が含まれていると思う。予期と現実ということわざがある。
とにかく、私はここにいる――少なくとも、私があちこちに翻弄されながら生き延びてきた限りにおいて今日もまた、地球のあちこちを旅している(カナダ国内でも地球のあちこちのうちに入れている)。今朝私は早起きして、ルー・ディスタントとルー・マッキンタイアと一緒にボート(連絡船)に乗りに行ったんだ。
私はセントローレンスを渡る(ノーサンバーランド海峡というところ)、ふらふらした古い桶のような船だ。かなり荒れていたが最初は十分に快適だった。ぼろぼろで不機嫌そうな雲から注ぐ太陽は、水面が焼けた銅色に変わり、その間から陸地が顔を出す。
霧のカーテン。その後少し船酔いをしてしまい、船着き場に着くまで横になっていなければならなかった。 ピクトー港、Stellartonで車を乗り換え、Truroで再び車を乗り換えた(乗合馬車か)。
そして ハリファックスでは7時半頃。L.C.(レディースカレッジ、ダルハウジーの学生の宿舎)の家政婦のミス・クラークさんが出迎えてくれた。彼女はとてもいい人そうだ。
アーサー・ウィリアムズと婚約している。大学に着くと、彼女は私をパール・テイラーの部屋へ連れて行った。 パール・テイラーは気さくでいい人そうだが、私はそれほど時間をかけず、10分もすれば彼女の頭脳がゼロであることに気がつくだろう(頭脳のいい人と話し合いたいの)。
夕食をとった後、私は疲れも取れたので、パールと一緒に集会所に上がった。そ の部屋で体操を見た。その後部屋に戻ってきたのは、パールに「エサ」(おやつ)をご馳走になるのだが、これは言うまでもなく今は違法だ。彼らはいなくなり部屋は静かだ。私はあまりに朦朧としていて、疲れきっているのだが、しかし私はここが好きなのだろうと思う。あえて言うなら他のダルハウジー大学の女学生たちがいる家、「サードアンドハーフ」の部屋に泊まる方が楽しい。
この部屋に寄宿している女の子は知っている子だ。 しかし私は推測するのに疲れすぎているのでここにいます。 狭い小さな鉄の簡易ベッドが2つ入っている。
私の古い知人、EdithとMarian MacLeodがここにいて、私はとてもうれしく思っています。 嬉しい。
1895年9月18日(水曜日)
レディースカレッジ、ハリファックス
今朝はパールの目覚まし時計で早く目が覚め、起きて着替えた。 その間にパールからH.L.C.のエチケットについて情報を吸収する。そして私たちは朝食を食べに行った。ダイニングルームは細長い素っ気ない部屋である。
大きな窓が16あり、壁には黄色の羽目板が張られている。実に醜悪な 憂鬱になるようなアパートだ。 夕食後、校長のミス・カー(年配のイギリス人女性)にインタビューした。
荷解きをしてから、速記のレッスンに行った。ミス・コービンが先生だ。 クラスには他に3人いる。私は速記がとても好きになれそうだ。 そろそろ落書きを(日記のこと)をやめて、寝る支度をしなければならない。
10時だ。もし私がサード・アンド・ア・ハーフに住んでいたら、こんなことに巻き込まれる必要はなかったのだが。パールとはそうしなければならない。明日からダルハウジーが始まるので、気を引き締めていかなければならない。
比喩が混じってしまいましたが、お許しください。
1895年9月19日(木曜日)
H.L.カレッジ
先週の木曜日から1年経ったような気がする。今朝はダルハウジーに上がった(登校したということ)。私のベッシー・カミングとエルマ・ベイカーは(先輩)(2年生)、そしてリタ・ペリー(後輩)です。
私は彼らの誰とも激しく惹かれることはなかったし、彼らは確かに門外漢の彼女(私)の新しい出発をあまり助けようとはしなかった。
大学までは半マイルほどで、レンガ造りの大きな醜い建物がむき出しの中にある。(フォレストビル、当時は広い原の中に建っていた)
醜い敷地。中に入るとものすごい歓声で迎えられた(女生徒が来たから)。階段でグリーンを歌う新入生の群れ。さっそくフォレスト博士の部屋に行き、登録を済ませた(聴講生の様なもので試験はなかったのか)。それから家(宿舎)に帰った。このころには私は疲れと戸惑いと寂しさで、涙をこらえるのがやっとだった。でベッドで丸くなり、心地よい遠吠えをしようと思っていた。その時クラークさんが来て、散歩に誘われた。私たちは公園へ出かけた。
とても静かで自然が美しいところだった。ミス・Cはとても親切で陽気な人で、私たちはたくさん話すことができた。6時に帰ってきたとき、私は生まれ変わったような気分だった。私たちは夕食に遅れてしまったので、C子さんに待っててと言われ、一緒に夕食を食べに行った。
応接間でおしゃべりを終えた。だんだん落ち着いてきたので、このままではいけない。来週にはかなり充実した気分になれると思う。
あの永遠のピアノの練習は、いつも通り行われている。昼も夜も耳元で鳴り響く。ここに来てしばらくすると、慣れてしまって気にならなくなるそうだ。そうであるように、神々がお守りくださいますように
この日は家では(キャベンディッシュの家では)祈祷会の夜だ。今頃は教会に集まっていることだろう。
今すぐ帰りたい。まだ1週間しか経っていないのに、1年経ったような気がする。ホームシックになりそうというのは否定できないし、呪文でかなりブルーな気分になっている。
1895年9月24日(火曜日)
今日は楽しい一日だった、いや、悩まされることがなければそうだっただろう。断続的に頭痛がする。朝、元気が出るような手紙を何通かもらった。今日、大学では2時からフランス語の授業が1回だけあった。
市内に住むミス(ロッティ)シャットフォードと知り合いになったが、彼女はとてもいい子だ。彼女は私と同じように特別コースを取っている。今のところ私はダルハウジーの女の子である大嫌いなレタ・ペリーと一緒に帰らねばならなかった。この午前中はキケロについて勉強した。彼らはローマン方式で
私はこの方法が全く好きではない。新しい言語のように思えるし発音を注意深く観察している。実際昔のP.W.C.時代やA先生のことを思い出して、今夜はホームシックになりそうだ。恐ろしい気分だ。
1895年9月25日(水曜日)
H.L.カレッジ
今日のラテン語の授業はすばらしかったし、セカンドイングリッシュもすばらしかった。私たちは後者のテーマは「私の自叙伝」だった。私たちの英語教授のマクメチャン先生はとてもいい人だが、どちらかというと弱い人だと思う。
ダルハウジー大学のエイミー・ヒルさんが今日私を訪ねてきて、私はダルハウジー大学のパーティーに招待された。明日の晩のパーティーでその招待状、私は袖の中で彼女の呼びかけに少し微笑んだ。動機はわかっているつもりだ。マレー・マクニールの機嫌を取ろうという魂胆だろう。彼女はかなりマレーに好意を抱いていると評判だ。(マレーは私の伯父さんの子で私の従兄弟)
彼(マレー)の従姉妹(私のこと)に少し気を遣うことで、これは彼のいとこへの親愛の情だと考えると、面白いことだ。私とマレーはお互いに嫌いなのだ。ちなみに彼はダルハウジー大学の4年生だが、私が来てから一度も声をかけられたことがない。
これはもちろん、私にとっては全く関係ないことだ。しかし彼はほぼ毎夏我が家を訪れている。(リアンダー伯父さんが来るのと一緒に来ている)少なくとも自尊心を保つために外見的な礼儀は示すべきだ(親戚だから通り一遍の礼儀は示す)。しかし、マレーは私が彼にひれ伏し、彼を崇拝していないことが許せないのだ。
彼はすべての女性的な生き物に崇拝することを要求している。これは明白な真実だ。だから私は可哀想に、ミス・ヒルは私に気を使っても、あまり希望が持てないだろう。(マレーに良く言ってもらえない)
イーディス・イングランドから、今朝、長い手紙が届いた。彼女はサックヴィル・カレッジで音楽と絵画が好きで仕事も好きだが、この場所は嫌いだ。しかし、それはおそらく単なるホームシックに過ぎず、すぐに治るだろう。イーディスは一人っ子で可愛がられてきた。ずっと贅沢な暮らしをしてきた彼女には、その対比がむしろ辛いのだろう。
1895年10月3日(木曜日)
大学までの道のりはとてもきれいだ。病院とその周辺は貧しい家も素敵だ。木々は黄金色に輝き、爽やかな朝を迎えている。霜の降りた木の葉の匂いのする空気。私は、だんだんと落ち着いてきた。
大学の大きな部屋や長い廊下でくつろいでいると、あちこちで知った顔を見かけるようになる。グループやクラスタ(集合、寄合)のあちらこちらで見ることができる。英語の授業はとても楽しい。
1895年10月9日(水曜日)
ロッティ・シャットフォードに誘われて、昨夜は一緒に下へ降りた(下校した)。彼女は彼女の結婚している姉は現在留守にしており、ロッティは一人だ。彼らはパークロードのとてもきれいなコテージに住んでいて、ロッティと私は素敵な時間を過ごした。
今日のセカンドイングリッシュでは、マクメチャン教授が私たちの「自伝」を返却してくれた。批評を加えたものだ。彼は私のものが特によくて面白いと言ってくれた。それから、私たちは「私の最も古い記憶」について書かなければならなかった。私の場合は、たまたま棺桶の中の母を見たとき、小さな赤ん坊の手を母の冷たい顔の上に置いたことだ。
.jpg)
ロッティ・シャートフォード
モンゴメリを新聞社の校正係に推薦してくれた人であるが、彼女とはウマが合わなかったのか、のちに疎遠になった
1895年10月12日(土曜日)
落葉の月」は、なんという速さで過ぎ去っていくのだろうか。今朝はミス・チェイスがグリーンマーケットに行った(モンゴメリを連れて行ったのか)。ハリファックスの「名所」であり、水曜日、次の授業でそれについてテーマを書かなければならないからだ。
一見の価値ありだ。午後はチェイスと一緒にダルハウジー対ユナイテッド・サービスの間で行われたフットボールの試合を見にいった。私はフットボールを見たことがなかったのだが、理解することができなかったので、特に面白さは感じなかった。
1895年10月22日(火曜日)
H. L.
私は衝撃的なほど散漫になってきている。もう真夜中だというのにまだベッドに入っていない。しかし、それなら毎晩寝ればいいし、毎晩オペラを観に行くわけにもいかない。と、またまたそんなところだ。(祖母からの援助もありオペラを観にいけたのか)
今日、シニア・イングリッシュの後、ロッティと私はパブリック・ガーデンに散歩に出かけた。明日テーマを書くからだ。それは楽しい夜だった。澄み切った爽やかさ。今は寂しく、さびれた印象の庭園だが、その寂寥感さえも悲しいほどに美しく、灰色の道にはしわくちゃになったものが散らばっている。葉っぱ。栃の木は見事な琥珀色に輝き、湖や池は薄暗い光の中で、静かに銀色に輝いていた。
今夜のオペラは「イオランテ」、とてもきれいだった。帰宅後、私は偶然にも玄関でミス・クラークと鉢合わせして、二人で中に入り、餌を食べた。
キッチンでクラッカーとグーズベリージャムを食べた。これこそ仲が良いということだ。家政婦さんの味方です。
1895年10月27日(日曜日)
何がどうなってしまったのか、本当にわからない。もう2日間も元気でいられない。一日中ひどい頭痛と眼痛に悩まされている。
リードとペリーと私は今日の午後、ダルハウジーで開かれた宣教師の講演会に行った。夜はフォートマッセイ教会へ。後者では懇親会があるそうだ。水曜日の夜は参加するつもりだ。
1895年11月17日(水曜日)
本当に、「カップと唇の間には、多くの滑りがある」。誰が想像しただろう。あの日曜の夜、ペンを置いたとき、いつまたペンを取るのか(いつまた日記に書き込める時が来るだろうか)、あるいは私が訴えた「頭痛と目の痛み」は、何を予兆していたのだろう。
私は麻疹にかかったことがあり、それによって物語が始まるのだ。実際、何度もかかっている。27日の翌月曜と火曜は、すべて「はしか」にかかってしまった。頭の風邪」だと思ったが、いつも通り出かけた。惨めな気分だった。しかし、はしかのことは考えもしなかった。
ダルハウジーで、私は疑われたかもしれない。水曜日、私はこれまで以上に気分が悪くなったが、大学には行った。ペリーも「風邪」をひいてしまい、体調を崩してしまったのでベッドに寝たままだ。
昼食後、あまりに気分が悪いのでベッドに入った。もし眠れたら、フォート・マッシーの社交界に行けるほど元気になれるかもしれない。I
午後はずっとうとうとしていて、夕食の支度をしているときに、クラクストンさんがその細い、好奇心旺盛な小さな顔に、不思議そうな表情を浮かべて入ってきた。彼女はクラクストン、通称クラックは寮母で、イギリス人の女性だ。
うるさいお節介なイギリス人女性。正直なところ、私は彼女が心底嫌いなので、だから彼女の登場を狂喜乱舞することはなかった。私の冷静な対応に臆することなく、クラクストンさんは、こう言った。「ペリーさんは麻疹です"
"あなたもそうではありませんか」彼女の言葉は少なく、短いものだった。しかし、残念なことに、私の希望は見事に打ち砕かれた。
ペリーさんが大学を 爆破しようとしたとしたら、ダイナマイトを使い、私を共犯者として非難したのだから、これ以上のことはないだろう。
雷に打たれたようだ。私が散り散りになった知恵を取り戻したころには、ミス・Cは刮目して見ていた。私の首は、軽率なことを発見し、私の運命を決定づけた。私はすぐにペリーの部屋へ行くよう命じられた。リタ・ペリーという、私の大嫌いな女の子と一緒にいるのはあまり気持ちの良いものではなかった。
クラックがリンゼイ博士を呼んだが、博士は賢明に診察し、こう宣告した。麻疹にかかり、ただでさえ烏のような顔をしている私に、空腹であるはずがないと断言した。
最も不親切なのは、私が夕食前に捕まったことだ。ローストビーフの夜も。あの心ない人は、私に何一つ食べさせてくれず3週間も大学病院に隔離するよう命じた。
次に看護婦のフレイザー夫人が来た。(あの看護婦は)週6ドルを簡単に稼いだと思う。お金といえば、はしかは私の乏しい資金に、悲しいことにかなりの穴を開けてしまったのだ。
私たちは「病院」に連れて行かれた。大学から離れた場所にある。ここで私たちは寝かされた。私はもうかなり具合が悪くなっていてその夜から翌日にかけてはずっと体調が悪く、目もとても悪かった。しかし金曜日にはだいぶ良くなり、それからは急速に良くなった。
しかし、ああ、なんと退屈で疲れることだろう。ダルズの女の子たちは、私たちに楽しいメールを送ってくれた。毎日手紙が届き、フレイザー夫人は「余暇」の中から完璧な物語を読んでくれた。
しかし、それにもかかわらず、(回復までの)時間は恐ろしく長くかかる。私はペリーを嫌っているが、彼女も私を嫌っているに違いない。
私たちは互いに反目し合う性質を持っているのだ。彼女は私の魂が一目で宣戦布告する相手だ。しかし、私たちはいつもお互いに礼儀正しく、表面上不幸な仲間である以上、最善を尽くした。
物事は、宣言されていない斧を埋葬し、非常にうまくいき、自由に話をする。キャベツと王様と男! そして食べるもの。私たちはほとんど飢えていた。弱い(薄いか)紅茶、トースト、様々な「スラッシュ」(薄い切り身か)がすべだった。
最初の2週間は、空腹感を和らげたりして、時間を潰した。私たちの体験談を「ペリーが来たとき」と題して連載している。モン(モンゴメリのことであろう)がはしかを患ってしまったのだ。
翌週の金曜日には起床が許され、ベッドから出るのがこれほど嬉しかったことはない。私の人生において初めてだ。目が覚めるとすぐに本や新聞を手に入れた。それでも時間は長い。もちろん楽しいこともあった。面白いことはたくさんあった。
毎日2つか3つ、新しいジョークが生まれた。すると女の子たちが3番通路のトイレの窓(ちょうど向かい側)に来るんだ。そこからおぼつかないアルファベットで話しかけてくる。
外の世界 1、2日は散歩に出させてもらった。楽しかった。その後私たちは毎日外出したが、誰とも会うことは許されなかった。
フレイザー夫人(看護婦)が去ったのは水曜日で、その後はいつになく冴えない日々だった。私たちは、自由になる日が来るのをどれだけ待ったことだろう。そしてついに月曜日が来た。今朝私たちは頭からかかとまで消毒された。
シナモンの香りを漂わせながら、しかし言葉にできないほど幸せな気分で降りてきた。そして私はあなたに保証する(日記に直ったことを報告する)。
今日は忙しい一日だった。週明けまでサードアンドハーフに宿泊することになった。文明の利器に戻るのは何と楽しいことだろう。しかし私は勉強しなければならないだろう。もちろん私は何もかもが遅れている。
病気をしてからというもの、手紙は山積みになっている。家からの手紙によると、Mr.アーチボルドはサニーブレーに呼ばれることを承諾し、今週中にセコイアを発つそうだ。とても残念だ。大きな変化であり、(そこに)他の人がいることはとても奇妙に思えるだろう。彼は18年間C.M.に在籍していた。
1895年12月1日、日曜日の朝
先週の月曜日、大学に戻ってこれて十分嬉しかった。午前中、ロブ・マクレガーに頼まれて、金曜の夜ソサエティ(大学の集会か)でイアン・マクラレンに関する論文をフィロマティック誌のために書いた。
私はやりたくなかったのだ。しかし彼に強くせがまれ承諾してしまい、すぐに掲示板に張り紙をしてもらった。――少なくとも私の名前は、クロケットとクロケットとの間にあった。「シンプソン・オン・バリー」。(不明)
今は自分のアカウント(権利)で「家事をする」。ミス・カーが月曜に言ったことは、私はこのダルハウジー・フラット(宿舎)に住むのがいいと思うということだ。(管理人にまかせず自分で家事をしているのはマメだから)
良いことだ。私はいつもミス・カーに同意するわけではないが、今回は断固として同意する。
1895年12月12日(木曜日)
H.L.カレッジ
今日は一日中「失楽園における性格」についての論文を書いていた。私はこの論文が大嫌いだ。このテーマは、できる限り邪悪な日を先延ばしにしてきましたが(グズグズして取り掛かるのを遅らせていた)、今日、それに落ち着く必要がありました。(とうとう仕上げねばならなくなった)しかし、私はこのテーマを見事に成功させることができなかった。このテーマは私には大きすぎるのだ。
今夜はガンディエ氏の社交パーティに招待された。(ガンディエ氏は)フォートマッセイ教会の人気牧師である。私はクリーム色のクレポン(シボのある織物)(平らな布地ではなく、デコボコした織り目がある布)のドレスを着て行った。ピンクのシルクのクラッシュカラーに、淡いピンクのシルクリボンのフィレット(縁を滑らかにしたリボンか)を髪に巻いている。女の子たちは、私は「アウト・オブ・サイト」(7人の目に見えない)(場の中で目立たないという意味か)ように見えると断言した。私はかなり楽しい夜だった。満員の社交場は、招待客はアルファベット順で招待され、主としてお互いに知らない者同士はそうもいかない。(その他の者はバラバラに紹介されたか)
1895年12月23日(月曜日)の朝
先週の月曜日から試験が始まった。ラテン語とフランス語があった。ラテン語は簡単だったが、フランス語は非常に難しい。火曜日は試験がなかったので、3つの試験のために一日中一生懸命勉強した。
水曜はローマ史と第二・第三英語だ。私は最初の二つはよくできたと思うが、最後の二つはあまりできなかったのが残念だ。その試験は、はしかの病気で休んでいたときの勉強が中心だったようだ。これは英語で負けるのは初めてだ。
木曜日の午後、レムの家で休暇を過ごしているジョン・ディスタントが訪問してきた。いい奴で嬉しかったが、彼の話を聞くのは嬉しくない。
レム夫人の命令で、午後の間私を外に連れ出すように言われたのだ(モードでも誘ったらどうかといわれたのか)。そこにはまともな逃げ道がないので行くしかなかったのだ。彼らは私にずっといてほしいと言った。
夜も、ダルハウジーで行われる「解散コンサート」に行かなければならなかったのだ。そこには非常に多くの人が集まっていて面白かったのだが、あまり楽しめなかった。疲れていたのかもしれない。しかし松明行列は楽しかった。
金曜の朝には、大移動が行われた。女の子はみんな家に帰った。(クリスマス休暇か)正直言って、みんなが帰ってしまって、自分は取り残されたようなかわいそうな気持ちになった(ああ、私は可哀そう)。しかし、おばあちゃんの手紙には、次のように書かれていた。道路が悪くなるのを恐れて、家に帰らない方がいいと思ったそうだ。
喜び勇んで上京した。私は「瀟洒な氷の上の豚のような」凹み(余計な者か)。私は決してそれらを全く興味がない。
このため、彼女はかなり面倒くさい(性格だ)。彼女の頭の中には(どうやって楽しもうか)、次の3つのアイデアしかない。美味しいもの、素敵な服、そして恋人。私はこれらすべてが適度に好きだ(恋人も適当に遊んでいるだけなら好きだ)。
でも、それが他のものを押しのけてしまうことはないのだ。間違いなく私は、パールは私を退屈させたのと同じくらい(パールにも)退屈させたので、私たちはずっと離れていた方がいいんだ。ここでは、私は女王のように幸せで、邪魔をすることなく、好きなように煮込んだり、遊んだりすることができる。誰にも干渉されず、誰にも干渉されない。
木曜日に論文を書き、先週の金曜日の夜ロッティが私を呼んで、一緒にダルハウジーに行った。学生たちが大勢集まっていて、私は緊張していた。少し緊張したが、うまくいったと思う――少なくとも、みんなはそう思ってくれているようだ。
今夜、私たちは再びYMCAの宣教師の会合に行った。その前に論文を読まなければならなかったのだ...。パールは素敵なコリドー3の小さな部屋を独り占めして、まるで独立したような気分だ。
祖母は、彼女はとても耳が遠く、駅などその意味がよくわからない。祖父は面倒くさがりなので、私に会うことも、連れ戻すこともしたがらない。
クラークさんは今朝まで出かけていなかった。私は他の誰よりもまとめて彼女を恋しく思うだろう。
夕方
今日の午後4時頃、散歩に出ようと思い立った。
公園(時計塔のあるシタデル公園)でグリーンバンク(草の土手)に腰を下ろし港を見渡すと、それはとても愛らしい。私の左手には街があり、その屋根や尖塔は紫煙のシュラウド(夕闇の幕)に包まれて薄暗くなっていた。それは港を漂い空の青さを濃く染めている。
天使が天国の穏やかな美しさの上に、濁ったピニオン(歯車)を広げたのだ。霧の中にジョージ島が浮かび上がり、目の前にはサテンのような滑らかな光沢の水面が広がっていた。花崗岩の岩肌に優しい波が打ち寄せている。右手には港が広がっていて、バラ色と銅色のゴールドの色調を帯びている。
夕日が、鈍い火で縁取られた雲に隠れるまでずっと続いていた。何艘ものプレジャーボートの帆が遠くで白く輝き、その長い反射が美しく灰色の水面に揺らいでいる。小さな暗い岬がクリーム色の広がりを横切っている。霧で和らいだ対岸は、丘と丘のように折り重なっている。
闇と光の谷。熟した空気の中でさまざまな音が交錯する。このあたりはジョージズ島では灯台のビーコンが煙の中ではげしい星のように光っていた。
水平線の彼方で、もう一つの答えが返ってくる。そしてそのはるか上にある凹みの中に、土が届かないステンレスの青に、銀白色の半球が光っている。真珠のような水蒸気の乙女なヴェールを、その清らかな顔に貞淑にかけた月。
(詩的な表現と言うのは自然の光景の中に感情がこもっているように見せる表現であろう)
1895年12月24日(火曜日)
本当に、なんだか単調な毎日だ。一日の流れを説明すると、ここで過ごすすべての休日のパターンと同じになる。休日? バカヤロー!
8時になったら眠いのだが着替える。8時半になると私は朝食のテーブルの前に座っていた。私のやや快活な人相が取り得る限り、ほとんど適切な表情をしていない。笑顔がない。今は(食堂に)暖房が効かないので、食事は書斎でとっている。
ダイニングルーム。テーブルの一番前に厳しい態度でミス・カーが座っている。自然はミス・カーを男のつもりで作ったのに、(女の)ラベルが混ざってしまったのだろう。彼女は、しかし女性としては大失敗の(風采)だと思う。彼女には罪はないが。
コルセットと服装は、衛生と醜さのルールに厳密に準拠している(衛生のためにはコルセットをしていなければならない))。鉄の灰色の髪はいつも髷を結ったままだ。口ひげがある。彼女は「ガートン」出身で、間違いなく非常に賢い。しかし彼女は魅力や磁力(人を引き付ける力)は微塵もない。
ミス・カーの反対側にはミス・クラクストンが座っているが、彼はまさに彼女のアンチタイプである(派手だ)。ミス・Cは鉤鼻で好奇心旺盛な表情をしており、神経質で小さなオールドメイドだ。細いガラガラの小さな笑い声が、私の神経を尖らせる。
ミス・ティルスレーもまた、年齢不詳のイギリス人女性だが、どちらかというと他の人に似ている。彼女は色黒で目が黒く、いかにも「英国人」である。ミス・オイラース(発音はドイツ人教師のアーラー)は最も心優しく、最も人間に近い教師です。
しかし、彼女は非常に滑稽なところがある。ミス・カーは彼女を嫌っていて、いつも不当な扱いを受けている。ミス・カーは彼女の三つ編みを掴み、激しく揺さぶる。(赤毛のアンでギルバートがアンのおさげを引っ張った場面のようだ)
ノッティング嬢は幼稚園の先生で、老女主義の悪化した見本のような人だ。彼女は若い頃も好感が持てなかった。ミス・ホワイティド、発音指導の先生はカナダ人で、しかも若くてとてもきれいだ。私は、他の不気味な猫ほど彼女を恐れていない。私は本当に怖いのだ。
というのも、ミス・カーと "カチャ"の二人は、どんなものにも飛びかかろうと待ち構えているようなのだ。
この2人のどちらかが、無防備な言葉や表現で、鼻で笑うと腹が立つ。彼女らは、そのような冷たい毒を植え付けることができるようだ。もし私が女子大生だったら
しかし、私はそのようなことはしない。私はダルハウジーの学生で、ここ(ハリファクス・レディース・カレッジ)の寮生に過ぎないので、彼らの「ボス的存在」にむしろ憤慨している。確かに先日、クラクストンさんとは見事に打ち解けましたけどね。私は先生の応接間に入ると、ホワイトサイド先生とティルスレイ先生が二人きりでいるのが見えた。
"いい朝だね"と言ったら... するとミスが飛び出してきて(1人だけいないように見えた)Craxtonは人目につかないようにしゃがんでいた低い椅子から降りてきた。「そんな私たちを女の子と呼ぶのは失礼よ」と冷ややかな口調で言った。「ああ、失礼しましたクラクストンさん」私は礼儀正しく言った。「そこにあなたがいたとは知りませんでした。もちろん、"女の子"と言って(バカにした)私をクラクストンさんはあまり好きではないようだ。しかし、彼女はそれを受け入れざるを得なかった。
謝罪は口調も内容も完璧に礼儀正しくやったので、彼女には言い訳ができない。恨みっこなし。
(アンがリンド夫人にしたお詫びの元ネタのようだ)
朝食が終わり、この地の一日の主要なイベントである郵便物を待つ。その後本を読んだり、文章を書いたり、勉強したり、かぎ針編みをしたり、寂しく歩き回ったりして夕方まで過ごす。午後は散歩に出かける。6時からの夕食もまたフォーマルなもので、そのあとは夜は午後の繰り返しになる。
1895年12月25日(水曜日)
H.L.カレッジ
今年のクリスマスは、とても退屈なものになると思っていたが、むしろ楽しいものになった。結局のところ。可愛いプレゼントがいくつも届き、嬉しい手紙も届いた。私たちは夜にはガチョウを食べ、その後パーラーで楽しい夜を過ごした。
1896年
1896年1月7日(火曜日)
昨日から今日にかけては、到着するものばかりで、そのクライマックスは今夜、ダルハウジー家の娘たち(生徒たちのこと)が戻ってくると、聞こえてくるのは、廊下や階段での競争や追いかけっこ、キス、歓迎の雄叫び。
明日から大学が始まるが私は少しも嬉しくない。私は怠惰で満足な日々を過ごしてきたので。また苦労することになるのは嫌だ。きっとそうなのだろう。しかし私は宗教上、目覚まし時計を7時にセットし、"バックル"するつもりだ。(ベルトを留めるように気を引き締めるということか)"気合いで"やる。
この3日間ものすごく寒かった。本当に冬が来たんだなあと思う。
これからの2ヶ月は、肉体に厳しい季節になりそうだ。さて小説も朝寝坊も、すべてあきらめなければならない。休暇の楽しみは、ハードでシステマティックな仕事に戻ることだ。
1896年1月8日(水曜日)
H.L.カレッジ
冷たい風呂は入るのは嫌だが、一回入れば気にならなくなるということです。休み明けの復職もそうだ。目をつぶって、毅然とした態度でヘッダー(定型文のことだが生活上のモットーのようなもの)をつけると、それにすっかり慣れている自分に気づく。
今朝、ラテン語の試験の結果がクラスで発表された。ラテン語はP.W.C.(かつていた師範学校)とは全く異なる方法で行っている。
教授が大量の書類の束(生徒が提出した論文のような物)を小脇に抱えてやって来て、悪意を持って価値に応じて処分する(出来栄えによってその中から合・不合を決める)。しかしそれ以外については、教授はただ読み上げるだけだ(感想は加えない)。クラスごとに、「ファースト」「セカンド」「パス」(パスは最低の合格ライン)のリストがある。名前がない人は呼ばれないと黙って運命を読む(不合格だと知る)。私はローマ史の成績もラテン語でもクラスをリードした。これはかなり良い成績で、私としては、このために一生懸命に働いたので、私はそれを楽しんでいます。(ラテン語は学者になる者の教養として重要な物だったらしい)
1896年1月10日(金曜日)
フランス語は驚いたことに「2」、英語は「1」だった。この日は今夜はパールの部屋で七面鳥の餌を食べた。楽しい時間を過ごせたに違いない。
今日は大雪で、そろそろ覚悟を決めなければならないようだ。本格的な冬の到来だ(日本の冬とは厳しさが違うようだ)。去年のように雪をかき分けなくて済むといいのだが。でもそうなると、そり遊びもできなくなりますね。かわいそうに、ルーは確かに私に素敵なものをくれられなくなる(ルー・ディスタンスはモンゴメリがビデフォードにいたときオレンジ会の会合で会った青年で、一緒にダルハウジー校に上がっていた)。(要するにモードはお人形のように可愛いので誰からも告白を受けた)
1896年1月11日(土曜日)
H.L.カレッジ
今日の午後、マッケンジー夫人とモーディに会いに行った。彼らはMayna'd(アンの愛情にステラ・メイナードさんが出てくる)に住んでいる。
St.(メインストリートのことか)を離れ、シタデルヒル(要塞の岡)の反対側にある。彼女はモーディに音楽を聴かせてやりたいと言っている。レッスンだ。最初はレッスンをするのを躊躇したんだ。しかし結局は承諾した。5ドルで、1セントたりとも無駄にしないためだ。私は水曜日と土曜日に行くことになっている。
ダルハウジー大学の新しい寮生、ニーナ・チャーチがいる。彼女は痩せていて神経質で彼女のことは好きでも嫌いでもなく何も知らない。ペリーとリードは心から彼女を嫌っているが、それは目安にはならない。しかしクラークさんもそうだ。ということは何か理由があるのだろう。
今夜は時間をもてあまし気味で、まずマクロード家の娘たちと、それからそして、私たちDal.女子(ダルハウジーの女生徒)全員がReidの部屋に座り、議論した。ラブレターなど、重厚長大なテーマが多い。私たちはハッピー・ゴー・ラッキー、このアパートには自分たちだけの小さな世界があるのだ。私は女の子たちとはあまり親しくないが、ペリー以外はみんな好きだ。
ミス・チェイスが一番好きで次がリード。ベッシー・カミングとエルマ・ベイカーは......あまり好きじゃない。でも、みんな仲良しで、とても楽しいよ。
1896年1月20日(月曜日)
H.L.カレッジ
「書くことへのかゆみ」――綴りを忘れてしまったのでラテン語で書く――今夜は、この古い日記帳を取り出さなければならない。走り書きをする。
今朝はラテン語の授業が最初にあった。私たちはとてもいいものを手に入れた。マレー教授は魅力的だ。最初は少し堅苦しいと思ったが。私はもう慣れた。
ラテン語の "k" の発音で、たまに舌打ちしてしまう。「キケロ」という言葉だ。今はVirgil(詩人か)の第五巻を読んでいるところだ。
P.W.C.ではVIを勉強したが、アンダーソン先生が私たちをまっすぐに導いてくれた。ラテン語の良さを実感している。ラテン語は今、私の好きな勉強の一つだが。あの古い白い建物(かつてのキャベンディッシュ校)で習い始めたときは、ほとんどこんなことになるとは思ってもみなかった。
ミス・ゴードンが見守る校舎。昔はよく恐ろしくて語尾変化や活用がうまくいかず、私は絶対に習得できないと確信していた。しかし、時間は不思議なもので、ラテン語よりも難しいものがある。結局のところ、征服されたのだ。
ラテン語と英語の間の1時間は、図書館で本を読みあさる。授業で習うより、もっといい本がある。古くていいところだ。図書館には学生が読書するテーブルがいくつかあり、あちこちに居心地の良いコーナーがあり、そしてキケロの胸像が、古典の上の高い位置からその光景を眺めている。本当にキケロに少しも似ていないのだろうか。
ここは噂話に花を咲かせる場所であり、少年少女が唯一おしゃべりをする場所でもある。
もちろん、常に慎重に下ネタで。大声で話すことは禁止されているので、音は聞こえない。囁き、木の葉のそよぎ、つま先立ちの足音、そして外廊下の反響音。
英語の時間は概して興味深いものだ。ロッティ(ロッティ・シャートフォードはフィリパ・ゴードンのモデルのようだ)と私は、一番前の席の隣の席に座った。
壁には、タイターニアとその妖精の宮廷の絵の下に、長い列がある。シェイクスピアのヒロインたちが私たちの顔をじっと見ている。今読んでいるのは『ロミオとジュリエット』感傷的な場面はマクメチャン教授の得意とするところなので見事にマッチしている。
昼食後、ドイツ語のためにDalhousieに戻るのは、いつも迷惑なことだ。その授業からは、何一つ得るものがないような気がしている。しかし私は行った。
教科書を読んで1時間を過ごした。とても恐ろしいと思わないか? しかしそうではない。そうです。これは上級の英語の授業の一部だ。今夜は "パンデモニウム・フラット"でピクニックをしたんだ。新しいルールの1つだ。
今年から、私たちデイジーに課されたのは、明りを消すこと。表向きは健康を守るためだが、実際は "Daddy Laing"の節約のためだ。貴重なガスです。まあこのルールがいつも厳密に守られているわけではないことは言うまでもない。連休明けは、これまで以上に
そのため、5分ほど間違えて11時過ぎに、「鏡の前に立って、古典的な服を脱いで、ブラッシングしている時」。ドアを叩く音がかすかに聞こえた。
私は「氷の上の豚」のように平然と、「おいで」と呼びかけた。女の子たちの一人だ。しかしあなたは伝統的な羽で私を打ち砕くことができただろう(誰かが遊びに来たということか)。すると、厳格な校長先生自ら、ドアから顔を出してくれた。「寝ないんですか」と、いかにもな口調で聞いてきた。
根っからの徹夜好きなんだなあ、と。
「そうなんです」私はかすかに口ごもり、「11時を過ぎていることに気づきませんでした」それは、というのも、私はそのことをまったく気にしていなかったからだ。
"まあ、あなたは気づく必要があります。" 母カーは憤慨して彼女はそそくさと立ち去った。
私はできるだけ早く、他の誰かが(明かりを消し)遅れていないかどうかを確認するために抜け出した。チェイス・ベイカーとカミングは全員捕まっていたが、悪魔は自分の面倒を見るものである。
ペリーとリードは、彼女(校長)が通り過ぎる前に、ちょうど自分たちの分を出したところだった。チェイスと私は、好きなだけ起きていようと決心した。私はガスを止め、チェイスの部屋に入り、二人でおしゃべりをした。12時近くまで笑っていた。
1896年1月26日(日曜日)
今晩は雨で風邪をひいていたので、リードと私は教会から家(ガールズカレッジの寮)に残った。廊下を歩いているときに、偶然チェイスの部屋を見たんだ。その部屋はドアが開いていた。チェイスは片付けないことで有名で、彼女の部屋を出て行ったのです。その部屋は、いつものようにカオスの原型のような状態になっていた。だからリードと私は、事態を悪化させるために、いや、そんなことはありえないのだが、悪戯に乗り込んだ。部屋にピリッとしたアレンジを加える。私たちは見事に成功した。
あの部屋は、私たちが完成させたときのものだ。そして、ほうきに枕を着せチェイスの服を着て、窓際に立てかけた。その時、「命からがら逃げろ」だった。チェイスが帰ってきた。
真夜中
私がこんな時間にベッドを抜け出していると知ったら、ミス・カーは子猫のように怒るだろう。9時頃、メイドの一人が、クラーク夫人が私に会いたいと言っていたなと思いつつ急いで降りてきた。C子さんは、自分の話を打ち明けたことがある。私は以前から彼女とウィリアムズ氏の関係を知っていた。
ほとんど降参しているようなものだ。私が中に入ると、彼女は泣きながら、ただ指輪のない指を私に差し出した。彼女はついに婚約を破棄したのだ。彼女はそうせざるを得なかった。ウィリアムズは彼女に恥ずべき仕打ちをした。
心が折れそうだ。彼女には申し訳ないが、もう彼とは縁を切った方がいいと思う。私は彼の中には一片の理念もなく、彼女を幸せにすることはできないだろう。
1896年2月15日(土曜日)
今日は特別に運が良かったのか、頭がかなりクラクラしている。一月にイブニング・メール(新聞か雑誌)では、以下の質問に対する最も優れた手紙に5ドルの賞金を出していた。
「人生の平凡な心配事や試練に対して、男と女どちらがより忍耐強いか? 手紙は殺到し、その中から最も優れたものがメールに掲載された。
当初私はこのコンテストにほとんど興味を示さなかったのだが、ロッティは、彼女の義理の兄が新聞に載っていて手紙を出すようにと毎晩のようにせがまれとうとう出した。私はいつもの緊張感に飽きたので、もっとオリジナルなものを作ろうと思って書いたのがこの作品だ。短い寓話を......。
ウィアー氏はこの手紙(投稿)をロティに見せたが、もちろん私のものだとは知らなかった。一番きれいだと言っていた。
しかし、これは議論になっていないので、賞を取ることはできないだろう。私はまたしばらく考えて、ある夜、夜中に起きて書いた。次の詩を書き下ろした。
「私の手紙は簡潔でなければならないので
私はすぐに私の信念を述べる。
そしてこれは、世界が始まった時から
アダムが最初に言って以来
イブが私を迷わせた
女は男より忍耐力があると。
もし男が待つことを余儀なくされたら
遅れてきた人のために
どんな人間でも、こんな煮え切らないことはない。
そして、もし何かが見つからなかったら
その辺にあるはずのもの
聞いている空気は、時にかなり青くなる。
ただ、ある男が
赤ん坊の泣き声をなだめるために
寒さの中でストーブを焚いてみたり
彼はどんな状態になるか。
どんなに大騒ぎして、大騒ぎして、大騒ぎして
そして、踏みつけ、威張り散らし、嵐を巻き起こし、叱りつける。
ある者は誇りをもってヨブを指し示し
自分たちの側の主張として!
なぜかというと、忍耐強い人はとても珍しいからだ。
それが本当に発見されたとき
彼の発見者は
彼のために歴史に名を残すために
そして、それは事実であると認めるが
あの人も忍耐力がある。
そして、女性はいつも甘く穏やかとは限らない。
しかし、私はすべての人が同意しなければならないと思います。
この中心的な事実、それは彼女が
「一般的な万能の忍耐は手のひらを返すことだ」
私はこの文章に「ベリンダ・ブルーグラス」(一種のペンネーム)と署名して送った。
7日にコンクールは締め切られ、手紙(投稿)は教授に手渡された。審査員のマクメちゃん。今朝ロッティが突然三々五々、息を切らしながら叫んだ。
"あぁ、モード、あなたが賞を取ったんだわ! マクメシャン先生は、最優秀作品を送ってくれた。と2番目が届いた。どちらも詩で、片方は''Belinda
Bluegrass''の作品だが、どっちが先かわからない"。
というわけで、一日中サスペンス状態だった。今夜、モーディのところから帰るとき、レッスン中に新聞配達員からメール(新聞)を買った。しかし私はその時それを開けなかった。いや、小走りになって家に帰り、2階へ飛んで行き、夕食のために服を着た。そして新聞を開くと、まず「ベリンダ・ブルーグラス(私の2回目の投稿)が入賞」という文字が目に飛び込んできた。もちろん嬉しかったですよ。
しかも、私の最初の手紙(1回目の投稿)は、その文学的価値から、佳作に選ばれた。
1896年2月20日(木曜日)
今朝はもう一つ、とても嬉しいサプライズがあった。しばらく前に私は短編を送った。フィラデルフィアの雑誌「Golden Days」に「Our Charivari」(中世ヨーロッパで性的反秩序を犯した者を村人が罵倒して騒ぐお祭り)という物語を寄稿した。(英語ならセレブレーションということになる)
今日、5ドルの小切手が届いた。これはラッキーだ。そしてとても励みになった。私はとても嬉しいことです。
今日、メールの賞金(新聞の課題に入選した賞金)を投資するためにアップタウンに行った。何かいつも持っていて飽きないように、テニスン、ロングフェロー、ウィッティア、とバイロン(それぞれの作者の詩集)を手に入れた。きれいな装丁で、ずっと自分のものにしたいと思っていた。
やれやれ、冬が過ぎ去るのはなんと早いことだろう。冬とは思えないほどこのところ、とても穏やかで良い天気が続いているからだ。昨年の冬とはBidefordでは、親愛なる古株の私たちが巨大なドリフト(雪が溜った所)に囲まれていたのだ。パーソネージ(牧師館)。この冬、私の古い部屋は誰が使っているのだろう。
ここでふと目をやると、目の前の壁にカード(写真か絵ハガキ)が貼ってある。そのほとんどすべてが私のよく知る場所だ。そのうちのひとつはウィルとローラ、そして私が散歩した「リバーロード」だ。
西部の夕暮れ時、遠くおぼろげな空に薔薇や金や深紅の花が咲いていた。大草原の斜面、川の水はその色を妖精のような陰影で映し出し、土手の太いポプラの下で、深く暗いところ以外は夕日が当たっている。大草原の黄昏にはなんという魔力があるのだろう。私たち3人は薄暗い道をぶらぶらと歩いては漫然と笑い、おしゃべりをする。それから、(また別のカードは)駅の風景だ。列車を待つときによく遊んだ長いホーム。その背後にはポプラの茂る断崖と紫煙を上げる丘があり、その向こうには曲がりくねった小道、大草原のヒマワリやブルーベルの花畑、そしてきらめく宝石のような湖。
あの年の高校生の奨学生は今どこにいるのだろう。私は半分、名前すら忘れてしまった。フランク・ロバートソンは亡くなった。
ジャルダン少年、ニッチーことトム・クラーク、ハリー・オラム、彼の顔は決して忘れられない。(歯がでかいから)
ジョン・マクラウド、マッケイ兄弟、そしてあの特異な若者、ダグラス・マヴィーティ、ウィリー・マクビース。他の人は忘れた。もちろんウィル・P(プリチャード)を除いて。(彼は)なんと初めて学校に来た時、私の後ろに座っていたのをよく覚えている。私達は自己紹介もなく、ただ顔見知りになっただけだと思う。最初の発言は、彼は私に、「こんなんじゃ勉強できないよ」と言ったのを覚えている。
「こんなきれいな髪を前にして......」。他の子ならバカバカしいと思ったかもしれない。しかし愛想笑いを浮かべるウィル・Pには、それがちょうど良く合っているように思えたのだ。(落ち着いていてお世辞がうまい子だったのだろう)
その後、古い「会議室」でノートを書いたり、「会議室」で勉強したり、楽しい日々が続いた。ノートを交換し、冗談を言い合って笑い、その後で歩いた。一緒に学校から帰った。今となっては夢のような話だ。
1896年3月14日(土曜日)
H.L.カレッジ
...今週はずっと論文を書き続けている。退屈で、面白くもない。この仕事にどんな利点があるのか、私にはわからない。火曜日、ヘラルド(新聞)の編集者、デニス氏から手紙が来た。彼は今度ダルハウジー特別(編集)版で、"The
Experi-Thanks" という記事を書いてほしいということだ。
ダルハウジーでの女子学生の経験」。やりたいのだが、これ以上ないほどの(上物の)依頼である。これ以上ないほど不便な時期に来た。
1896年3月21日(土曜日)
H.L.カレッジ
今週はずっと風邪をひいていて、何もする気になれなかった。学期が終わろうとしているのが実感できない。大学での時間の流れ(の速さ)は呆れるほどだ。先週の月曜日の朝、「ザ・ワールド」社から12ドルの小切手が届いた。
Youth's Companionに送った "Fisher Lassies" という詩に対するものだ。編集者はまた、かなり良いこと(講評)を書いている。というのもとても励みになるからだ。コンパニオン(雑誌)はいいものしか使わない。
1896年4月2日(木曜日)
H.L.カレッジ
今夜は勉強できない。落ち着かない気分で、落ち着いて勉強できない。メイ・テイラーがここに来ておしゃべりしているところです。彼女はレディース・カレッジの女の子(生徒)だ。(モンゴメリはレディース・カレッジには寄宿しているだけ)
このようなH.L.C.の女の子は、いつもとは対照的にとても親切で賢い。パール(同室者)は、ドレスと美女と食べ物のためだけに生きているようだ。
今日、また嬉しいことがあった。詩「りんご狩りの時間」に対するGolden Days(雑誌)の報酬30ドル。先週の日曜日の夜、エディス・マクラウドがやってきて、私と一緒に寝た。私たちは二人で寝た。ベッドは1つだが、H.L.C.のコット(簡易ベッド)はかなり狭いので、それを維持するのは芸術の域に達している。とはいえ、私たちは「おいしい」時間を過ごし、昔ながらのことを話した。月曜日の夜、私は彼女と一緒に寝た。私は今日はイゾベルと寝るつもりだ。
今夜はイースターホリデー(復活祭の休日)なので、寝まくりだ。もちろん他の時期には許されることではない。イゾベルは今、ここでガーターにボタンをつける縫い物をしている。彼女はケープブレトン(P.E.I.より北にある島)の女の子で、とても陽気な人だ。火曜日は最後のフランス語の講義とシニア英語での最後の講義があった。私は英語を卒業するのはとても残念だ。このクラスはとても楽しくて、とても得をした。昨日最後のラテン語の講義があったが、私はそれを後悔している。ダルハウジーでの私の講義は、あと1回だけだ。
月曜日
1896年4月8日(水曜日)
昨夜、デニスさんがオペラのチケットを送ってくれた。ミス・クラークと私は行った。演目は、オペラ「乞食学生」はとてもきれいで、とても楽しめた。
私はいつもそうだが、オペラって楽しいと思うんだ。決して家庭的な日常生活に嫌気がさして後味が悪くなることもなく、それどころか、新たな活力とスパイスを得てまた元の生活に戻れる。
1896年4月11日(土曜日)
今朝はイゾベル・Mと公園を長い間散歩した。それは美しい苔むした松の廊下をぶらぶらと歩きながら、目に映る梢を眺める。
真珠のような港の水は、その上の銀色の霧の下でクリーム色に輝き、震えている。
帰ってきたら荷造りを始めなければならない。Lem Dyslantsと一緒に2週間過ごすことになり、私の部屋が他の女の子に使われることになったのだ。私の貧しい部屋の絵も絵も本もニコニコマークも全部なくなり、はぐれた衣服や日用品が散乱しているだけだ。私の哀れな幸せだった小さな部屋、昔の夢は出てくるのだろうか。
もし、人が夢や考えを抱いた部屋から離れるとき、その部屋と喜び、苦しみ、笑い、涙を流した。目に見えないけれども、それ以上にリアルな、声の出る記憶のようなものが残っていないだろうか。
1896年4月17日(金曜日)
ハリファックス
今週はチェスナットテラス5番地に住んでいる。月曜日の朝、私は英語の試験が2つあって、まあまあできたと思う。昨日の午後、私はフランス語の補習を受けた。そして今日の午後、私は上級試験を受ける。ダルハウジーで受ける最後の試験というだけでなく、英語の追加試験だ。おそらく、私が受ける最後の試験だろう。私は初めて受けた試験を覚えている。
フレーザー先生がキャベンディッシュで教えていたときの歴史の授業だ。そしてその間、この12年間はそれぞれ別個に繁栄してきたのだ。
私の疲れた目の前にある試験用紙のクォータ。最初はあの愛すべき古い校舎で失われた子供時代。昔はよく試験で大騒ぎをしたものだ。自宅の2階の部屋の小さな引き出しに、昔の試験用紙の大きな束を保管している。
成績が良くなろうとどれだけ心配したか、どれだけ真剣に問題を論じたか。その後、先生から結果を発表されたとき、どれだけ誇らしい気持ちになったか。それからP.W.C.の試験もあり、メアリーと私はよくその前に座っていた。(勉強机であろう)
夜中まで塾通い。そしてあの恐ろしく、決して忘れることのできない「一週間の恐怖のライセンス試験(教員の免許試験)の週だ。あの一週間をもう一度生きたい。
今日、マクメシャン教授から、私が立派なシニア・イングリッシュの論文を提出したと聞いた。
1896年4月25日(土曜日)
ハリファックス、チェスナットテラス5番地
木曜日の夜、エイミー・ヒルの家でちょっと素敵なパーティーに参加した。昨日と今日はとても忙しかった。私は水曜日に帰郷する。ジョージ・マンロー、ダルハウジー大学の大恩人が亡くなった。島の学生たちの招集で何かと慌ただしくなりそうだ。
公開召集は行わないそうだ。あまりに腹立たしい。わざわざ1週間以上も待ったのに。
1896年4月29日(水曜日)
プリンスエドワード島州、シャーロットタウン
"再び祖国へ"――ここに着くまでまるで1日以上かかったかのようだ。
今朝は6時に目覚まし時計に起こされた。着替えて、一人堂々と朝食をとる。7時45分にタクシー(辻馬車)が来たので、「おはようございます」。と別れを惜しみつつ、H.L.C.を最後に見て、門を出た。霧のかかった灰色の朝。
私が列車に乗ってから数分後、ロジャーソン氏が現れ、私にくっついてきた。朝から晩まで。私は彼に我慢できないので、他の場所に行ってほしいと思いた。
ピクトゥ(港)でスタンレー号(連絡船)に乗り、寒くて荒れた海を渡ったが、私は平気だった。船酔いして、5時にCh Townに到着した。ローラとハリーが出迎えてくれて、メアリーおばさん(シャーロットタウンに住んでいた、偏屈だと言われていた)のところへ。今日の夕方、ジャック・S(サザーランド)とジャック・ゴードンがやってきて、私に会いに来た。私たちは楽しい時間を過ごした。
1896年5月5日(火曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
旧友に会うのに忙しかった。日曜日は教会にいた。とても不思議な感じがした。アーチボルド氏(牧師)を見なかった。代役のジョージ氏は、なかなか良い説教をした。彼はしばらくの間だけここにいるのだ。
今夜は特にすることもなく、二階で古い本をたくさん読んだ。ル・タースーネートもその中に含まれている。学生時代。あの頃が鮮明によみがえる。私はもう一度自分が女学生になったような気がした。今はばらばらになってしまった同級生たちと一緒に学校に通い、強い憧れを抱いた。
バラ色の霧の中に人生が見えた、あの懐かしい陽気な日々に戻りたい。希望と幻想に満ち溢れ、過ぎ去ってしまった不定形の何かを持っている。
永遠に"栄光と夢は今どこに?"
あの頃の光と影とともに消え去り、二度と戻らない
夜明けの新鮮さは一度しか訪れず、失われた輝きは何も思い出すことができない。
1896年6月30日(火曜日)
おじいちゃんとおばあちゃんは街に出てしまったので、「モンティ」は一人で留守番をしていた。二人が帰ってきてから大いなる栄光を手に入れたのだ。送ってもらった些細なものを手に入れた。
ドット柄のクリーム色のベールで、気の抜けたような縁取り。私は大好きなベールに弱いのだ。正しいベールの種類を持ち、その種類を熟知している女性が、そのベールを身につけることができます。(正しい女性は下賤な者には顔を見せないのだ)
その着こなしは、いつでもきちんとした印象を与えます。しかし一部の女性のベールは、そしてその付け方が!!! ぐにゃぐにゃで、スカスカな女性を見ると、鼻先まで伸びたベールを引きずり、そこに(鼻先に)しがみつくようにする。(引っ掛かっている)
私は、手を伸ばしてそれを引き剥がし、嘲笑と軽蔑の対象として掲げたいと思う。そのようなベールをかぶった女性は、本当に社会的な犯罪を犯していると思うのだ。正当なベール殺人であろう。(正当なベールの品位を貶めます)
1896年7月8日(水曜日)
キャベンディッシュ
今日の午後、ケイトと私はベリー(イチゴ)を探すために森に戻り、ベリーを見に行きました。「ケンタッキーとワイアンドの切り株。お椀がいっぱいになってしまいましたが、そのために働きました。
藪をかき分け、恐ろしい柵を登り、そして炎天下の中焼かれる。
ネイトは今家にいて(ネイトはバプテストの牧師の子であった)、今日バイク(自転車であろう)で降りてきた(我が家に来るときは降りてきたという表現を使い、別の施設に行くときは上がったという表現を使っている)。私たちは楽しいおしゃべりをした。彼はとても痩せていて、本物の口ひげがある。大人っぽく見えるけど、「これはこれでいいのでは?」
今日、ゴールデン・デイズ(黄金の日々、雑誌)から短編小説のために5ドルの小切手をもらった。人々はうらやましがる。(5ドルったって5万円と見なければならない)
このようなちょっとした成功に、「よくぞ言ってくれました」私は皮肉な笑みを浮かべ、それを聞いて、私は、彼らは一つの成功にどれだけの失望がつきまとうかわかっていない。彼らは成功だけを見て、すべてが順調な旅に違いないと思っている。
1896年7月20日(土曜日)
キャベンディッシュ、P.E.L.
今日の午後、アルマ・マクニールがやってきた。昔と同じ金色の髪をしたアルマは、今も昔も変わらない。窪んだ頬と甘い微笑み。彼女は3年前にボストンに行きましたが、今回は初めて帰国した。
4月にMcClure Syndicateに記事を送ったのだが、ちょうどそれが受理されたところだ。シカゴ・インター・オーシャンに掲載された。もうすぐ大金持ちになるように小切手が届くと思う。
(モンゴメリは21歳の頃にはぞくぞくと成功していた)
1896年7月26日(日曜日)
そろそろ夕方の礼拝の準備に入らなければならないようだ。今朝は出かけていたので、正直なところ、一回行けば十分だと思っている。
どんな日曜日でも、教会に行く。日曜日は安息日であるはずですが、実際にはどの日曜日も同じように一生懸命働いているのだ。
一週間のうちのどれでも(どの日でも)いいので。料理をして、食べて、洗い物もたくさんする。着膨れした服装で(キャベンディッシュの人々に誇るためにいい服装をする)暑い中教会まで歩いて行き、長くてつまらない説教を聞かされても良くはない。
頭痛がし、苦痛のために非常に悪意を感じるので、私の頭の中には、本当に良い理想の日曜日があるのだ。ただ私は臆病者なので、そのようなことはできない。それを現実に置き換える(その理想の日曜日の過ごし方を実行する)のではなく、型にはまった流れに流されるしかない。
しかし、日曜の朝にはどこか偉大な荘厳な森の中で、シダの間に腰を下ろし、シダの仲間だけで薄暗い苔むした通路に、木々や木枯らしが響き渡り、まるで広大な大聖堂の賛美歌のようなものです。そして、私は何時間もそこにいて、一人で自然と自分の魂とを通わせる。そうすれば本当にいいことがあると思うんだ。しかしなんという非正統的で奇妙なことだろう。(私の考えなど披露すれば)地元の亭主たちは恐怖のあまり死んでしまうだろう。(キリスト教の正当な教義からは外れている)
1896年 8月18日(火曜日)
パークコーナー、P.E.アイランド
土曜日の午後ここに来た。土曜日の朝、エドウィンとアルフ・シンプソンが我が家を訪れ
た。エドは今年からベルモントの自分の学校で教えている。
この夏、10月から大学に行くことになった(エドウィンは大学に行くため、その後任として私に推薦した)。私はこの学校に応募していたのだが、彼が私の合格を告げてくれた。私はとても嬉しかった。
このままでは学校(の教職に就けない)と思って、落胆していた。
昨日の朝、ステラの学校へ(ステラが教職をしている学校だろうか)一緒に行き、昼までそこにいた。その後、ロバート・サザーランドおじさんのところへ行った。ジャック(サザーランド、幼馴染のスナップ)は飛び入りで家に来ていて楽しい時間を過ごした。彼はもうすぐオタワに行き、そこで職に就く予定だ。(牧師になっていた)
私は今日の午後までそこにいたが、帰るのが残念だった。とても素敵なところだった。理想的なカントリーハウスで、大きくて広々としていて楽しい。
1896年8月20日(木曜日)
パークコーナー
ソファで昼寝をしていたら、なんだか目が覚めてしまった。愚かな、だから台所のテーブルの上に座って、字を書くことによって、その疲れを癒そうと思う。古い青いチェスト(大型の箱を机代わりにしたのか)何だかとても昔のような気がする。
ベルモント、P.E.L.
1896年10月21日(水曜日)
金曜日の午後、ルゥと私はケンジントンに向けて出発した。にわか雨が降ったので、私たちはかなりドロンコの悪いドライブをした。しかし午後4時ごろに到着し、ミセスPidgeon夫人のところで一晩過ごした。土曜日の朝私は汽車に乗って、シンプソン氏がいるミスクーシュに行った。エドの父親で、一族の間では「サム」シンプソンと呼ばれている人が出迎えてくれた。
ベルモントは、ミスカウシュから5マイルのところにあり、かなりきれいなドライブコースなのだが、その道は険しい。道路は車軸まで泥まみれだった(泥まみれになるような道)。ベルモントは湾に面しているため、かなりきれいなところだ。
しかし、私は、一般的に知らない原住民は不気味で、(何かが身体を)這うような予感がするのだ。
下宿を見つけるまでシンプソンさんのところに泊まっている。彼らは学校からあまりに遠くに住んでいるので、ここで下宿することはできない。シンプソン夫人もキャベンディッシュ家の出身で、シンプソンは、当然のように従兄弟と結婚し、親切で温和な人のようだ。が、やや憂鬱な性格の女性だ。
メアリー・ローソン大叔母さん(祖父アレクサンダーの妹)が遊びに来ていて、とてもくつろげた。
今、家には3人の男の子がいる(もう大きくなっている子)。フルトン、アルフレッド、バートンです。どの子もエドがその美貌を吸収してしまったようだ。
フルトンは完璧な巨人で、今まで見た中で最も巨大な手をしている男だ。彼は(フルトンは粗暴で考え無しだった)背骨までシンプソンで、シンプソン主義の真髄が凝縮されている。(自分たちは偉いという誇大な考えを持っている)
アルフは、3人の中で一番いい人だと思う。彼は陽気で、他の人ほど「シンプソン的」ではない。
他の人について言えば
バートのことはよくわからない。彼もまたオールマイティなシンプソンだが、ひとつだけシンプソンズにはない特徴、それはとても静かであることだ。
15歳の少女ソフィーがいる。彼女は私が今まで会った中で最も生気のない人間である。それ以上に私は彼女のことを全く理解できない。私は本当に彼女が全く正常なのか、メアリー叔母さんは「一つの品種に偏りすぎている」(ひとつの考えに固執している)と言うが、その通りだと思う。
日曜日は朝からずっと雨が降っていた。昼食後雨は少し上がった。フルトンの提案で、セントラル16番地にある長老派教会に行くことになったんだ。3マイルほど離れたところだ。出発してすぐにまたもや猛烈な勢いで雨が降ってきた。私たちがどんなに気持ちよくドライブできたか、想像できるだろうか。(皮肉か)
月曜日の朝もまだ雨が降っていて、フルトンは私を学校まで送ってくれた。途中、サイモン・フレイザーの家に寄って、そこで搭乗(寄宿)できるかどうか確認しました。
学校から4分の1マイルのところにある、なかなか立派な店だ。しかし私はその人たちにあまり好感を持てなかった。私が引き出せたのは部屋を貸せるかどうかを検討し、年末までに連絡するということだった。
学校は、これ以上ないほど殺風景な丘の上にある。眺望はリッチモンド湾の源流を見下ろす絶景だ。校舎の建物はとても小さく、家具もそこそこ揃っている程度だ。玄関に入ると、寂れた光景が私を迎えてくれた。評議員たちが、薪をくべているところだった。
パイプ(ストーブの煙突)があり、子供たちが身を寄せ合っている。私は、うんざりするほど、じめじめした気持ちでずっと待っていた。ようやくパイプが立ち、火が焚かれ、私が先生になる書類が出来上がった。
そして管理委員会は去った。私は大きく息を吸い込み、「ホーズ・イン」(仕事に飛び込む)した。もう3日も教えている。ひどい天候のせいで、出席者(生徒)は16人を超えることはなかった。前任のフレイザー先生は名鉄砲と言われたにもかかわらず、子供たちはひどく後ろ向きだ(やる気がない)。このような子たちを、私はあまり好きにはなれないと思う。ほとんどが貧しい家庭の出身だ。
大きな女の子もたくさんいる。マリー・モンローは新入生だ。最近この集落に来たばかりの新米学者だ。彼女の叔父のダン・キャンベルは、どう見ても学校の評議員である。マリーは、P.W.C.の入学試験(卒業試験か?)には合格して、今は二級(教員試験か)に挑戦するつもりだ。
これは、私には全く不都合なことだ。この学校ではやるべきことがたくさんあるのだ。P.W.C.でやるはずの仕事(教員試験の為に試験勉強をする)をしなくても、無学年の学校(小さい子に向けてだけの授業)でもできるのだ。しかしどうしようもない(マリーの試験勉強を見てやらねばならない)。マリーの印象は奇妙な女の子だ。エキセントリックだ。彼女の最初の挨拶は、
「あなたには大いに期待していますよ」「物心ついたときからあなたは模範的な人でした」ということ。
正直なところ、私はこれに対して何も答えることができなかった。私は彼女のことを聞いたことはないし、彼女の人脈を推測できるものは皆無である。彼女は私を知らない。それなのに、なぜ、どのように、どのような形で、私を取り上げられたのか。彼女の「模範」となるようなことは私にはわからないし、これからもわからないだろう。マリーに聞くことはないだろう。
今朝は、自分の家から閉め出される快感を味わいました。
学校まで3キロの道のりを歩き疲れた後、学校に到着すると、そこには困ったことが待っていた。その原因と結果の謎に迫った結果、このようなこと(学校に入れない)になったとわかった。火を起こすはずの少年がサマーサイドに行き、鍵も一緒に持っていったことがわかった。その結果11時近くまで待たされることになったが、その間にウィリー・キャンベルは合鍵を取りに帰った。私たちは冷え切ってしまうところだった。
.jpg)
ベルモント校
.jpg)
私と生徒たち
1896年10月22日(木曜日)
ベルモント、P.E.アイランド
今朝、私はフレイザー氏の家をたずね、いずれにせよ彼らから明確な答えを引き出そうと決心した。彼らは最終的に私を乗せる(下宿させる)ことに同意した。私はしかし、それは単に「ホブソンの選択」(ほかに道がない選択)であり、私は彼らをどのように好きになるだろうか。
他に行くところがないのだ。郵便局は彼らが持っている(私設郵便局を開いている)ので、便利だろう。
少なくとも、この見捨てられた土地では、週に2通しか郵便がないのだ。手紙はどんなに人を元気づけるか、見知らぬ土地で見知らぬ人になり、生活のためにがむしゃらに働いている時に、見知らぬ土地で見知らぬ人が、このような死んだような田舎で生計を立てているとき、手紙はどれほど人を元気づけることだろう。ビデフォードの教師は好きだったが、ここが好きになることはないだろう。
1896年10月25日(日曜日)
ベルモント
今日もひどい風雨の一日だった。でも、夜には晴れてきて、フルトンとソフィーと私は、セントラルのメソジスト教会まで車で行った。しかし牧師は来なかったので、私たちはそこを離れ、キャンベルという名の3人の乙女が住む家へ行った。最年少のディエムは、おそらく45歳を迎えることはないでしょう。しかし彼らは少し変わってはいるが、とても親切でいい人たちだ。
私は明日フレイザーのところに移ることになっている。寂しくなるのは分かっている。私はただ、彼らが私が期待するよりも良い方向に向かうだろう。(フレイザー家の人が私に慣れてくれるように)
1896年10月27日(火曜日) ...私は昨夜、学校からここに来た。そして、私は今、この家族の一員だ。 そこは一言二言の説明でも不都合はないだろう。 さて、「私たち」の最年長者は、年老いた老婆である。 80代の坂道で、耳も聞こえず、ほとんど目も見えず、しわだらけでよろよろ歩いているが、それでもなおしかし、哀れな老人は、私を楽しませるために、震えるような声で天気や「風邪が流行っている」という発言をする。私は彼女がしかし、しつこく話しかけてくるので困ってしまう。 ナーバス(神経質)になる。 そして私のホストとホステス(囲ってくれた人)、サイモン・フレイザー夫妻の登場である。サイモンと彼の美しい妻は結婚してまだ数年だが、最初の若さはとっくに過ぎていて、もちろんとても素敵なのだが、年を重ねるにつれて明らかに見劣りするようになった。サイモンについて、私は まだほとんど見ていないが、彼はどちらかというと知的で、懐疑的な傾向を持っていると私は思っている。 サイモン夫人の厳格な長老派の性癖でさえも正すことができない。 サイモン夫人自身は「色白で太っていて40歳そこそこ」である。彼女の文法は耐え難いもので、そしてそのマナーは決して洗練されてはいない。まるで恐ろしくてたまらないかのように振る舞っている。 畏敬の念を抱きつつも、とても親切な方です。 この将来有望な夫婦には娘が一人いて、ローラという甘えん坊で青い目の小さな娘がいる。 4歳の猿。 サイモンの弟のダンは、年老いた独身男で、その状態は、私にはこのままではいけないと思わせた。サイモン自身は、決してアポロだが、ダンに比べれば "サテュロスに対するハイペリオン" だ(勇者に見えるほどだ)。哀れなダンの欠点は男らしい美しさは、幼少の頃、"侍" であったこと(暴れん坊だったのか)に起因すると私は理解している。 父親から切り株を投げつけられた。ダンはこの言葉のミサイル影響から回復することはなかった。彼は郵便局長で、その職を大きな責任のあるものと考えているようだ。 そしてジェシーと呼ばれるフレイザー嬢は、独身という恵まれた境遇にありながら母親になることを拒んでいない。彼女は、ここと娘の 娘のマクローリン夫人の家を等しく行き来している。 今の私の部屋は嫌な感じのする狭い部屋だ。クローゼットにもならない。部屋にはテーブルもない。 小さな洗面台があり、その上には自分が映るガラスが吊り下げられている。 私は他の人がそうでないことを切に願っているのです。私のトランクはベッドに残されたスペースをすべて飲み込んでいる。 この部屋には釘が一本しかなく、そこに何かを掛けることができる。 食事は座敷で一人きりでとる。これまでのとこ食卓は公平であった。 シンプソン夫人は立派な女性だがしかし、彼女は料理や給仕の仕方を全く知らない。 私の「書斎」には、ひとつだけ救いがある。窓からの眺めが最高なのだ。 湾岸から20メートルほどしか離れていないので、真珠のように輝く一面の海を眺めることができる。真珠のように輝く水面から、遠く紫色の霧のかかった海岸まで見渡せるのだ。 しかしそのおかげで、昨夜はベッドで凍死しそうになった。 その時私は毛皮のコートがあったのを思い出した。 そのコートは、おそらくサイモン(この家の主人)のもので、応接間の壁にかかっていた。這って出て、それを取ってきて、その下に広げました。 (寝床に広げた)
1896年11月4日(水曜日)
今夜は疲れた。マリー・モンロー(受験生)のせいで、学校の授業がとても重いのです。彼女には
できない問題がたくさんあって、学校でやる時間がまったくないから家でやるしかなくて、今晩は3時間もかかってしまった。(学校では他の生徒を教えなければならない、マリーの家に行ったのか)でも、マリーは変わった子だけど、全体的に私は好きです。マリーには賢いところがある。マリーのことは嫌いじゃないけど、余計なことをさせるのは嫌いだ。田舎の学校では余計な仕事は必要ない。
私は今、少しばかり文学的な仕事をしようとしているが、あまりに困難な状況なので、半ば落胆している。私は「束縛され、這いずり回り、閉じ込められ、」ているのです。
私は、「囲い込まれ、はさまれ、閉じ込められ」ていて、何事にも都合よく手を出すことができない。そのうえ、私はここの家族のために持ち物をすべて閉じこめて隠しておかなければならないのだ。この家族は、私が留守の間に私の部屋や持ち物を物色するのが常であることがわかった(どれどれ先生さの持ってる物はどうかな、と)。鍵と錠前を発明した人に祝福あれ。
1896年11月7日(土曜日)
...今日、エド・シンプソンから手紙が来て、彼と連絡を取るように頼まれた。彼はなかなか気の利いた手紙を書いたので、私は時々文通することに同意しようと思う。大学生活との接触を保ち(エドは大学に行っていた)、この死んだような、しかし生きているような存在にちょっとしたスパイスを与えてくれるからだ。
『アメリカン・アグリカルチュリスト』誌が、私の詩を受け入れてくれた。
1896年11月14日(土曜日)
私は本当にあなたのところに来なければならないのです、古い日誌よ少し慰めてください。私はひどくあなたをを必要としている。ところで、これを私の日記ではなく、"不平の書"
と呼ぶのは、いい考えではないだろうか?
気にするな! 私はここで愚痴をこぼすだけで 外には漏らしませんから
今夜の不満は 凍えそうなことだ。今日一日、一分たりとも暖かくなかったからだ。厳しい寒さと突き刺すような風がこの狂ったような古い家を、まるで紙で作ったかのように突き刺す、ドアも窓も一つもきちんと閉まらない。寒さは私を縮こまらせるようだ。他のことはほとんど我慢できるのに、寒いと身体的にも精神的にも何もできなくなるのだ。
1896年11月20日(金曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
もう1週間が過ぎた、おかげさまで私は先週の土曜日の夜まで何とか生き延びた。日曜日の午後、私はシンプソン氏の家に逃げ込み、そこで48時間ぶりに徹底的に暖かくなった。昨日の夕方、キャンベルさんのところに行き、一晩中過ごした。また暖かくなりました。それが今の私のこの世の至福の最高の理想です。
今朝学校に行くと、火はついておらず、火をつけても、朝からずっとすねていた。寒さも厳しかった。私は今まさに半分凍っている。
この一家とより親密な付き合いになってからも、とても良くなったとは言えません...。彼らは今、私に対してそれほど畏敬の念を抱いていないようで、ある意味でこれは良いことなのだが、ある意味ではそうではない。ひとつには、私たちはよく一緒に食事をするようになったが、私はそれが好きではない。
いや、私は潔癖症ではない。男たちがどれほど粗野で無骨で汚いか知ったら、どうして私が食事ができるのか不思議に思うだろう。
しかし、食事はまだ公平であり、もし私が暖かくなることができれば、他の不自由なことに不平を言うことはないだろう。なぜかというと、先週の日曜日の夜、雪が降って、枕が窓から流れてきた雪で覆われた。というわけ。
サンクスギビング 1896年11月26日
プリンスエドワード州、ベルモント
フム! どうにかこうにか、足を突っ込んでしまったようだ。いずれにせよ、私はかなり不快に感じている。部分的には感謝祭のガチョウの食べ過ぎの影響からかもしれないし、昨夜の出来事からかもしれない。そのせいではないだろう。
少し話を戻すと、ソフィーとフルトンと私がミス・キャンベルの家に行った日曜の夜。そのとき私は「わかった」と答えた。その後、彼は(フルトンは)すぐに体調を崩したが、私はそれ以上何も思わなかった。
アルフと私がメソジスト教会に行った夜、ここに寄ったところ、彼らは私たちに夕方行くように言いました。そして日曜日の夜、家に帰るとアルフが言った。「雪が続くようなら水曜日の夜にキャンベル家に行こう
もちろん承諾した。フルトンはまだ数週間は外出できないほど体調が悪いと知っていたし、それはとても重要なことではないと思った。誰が私を連れて行くかは重要でないように思えた。それにアルフと私は他の誰とも関係なく自分たちの勘定で招かれたんだ。昨夜アルフはサマーサイドからの帰りに私を迎えに来てくれ、彼の家まで連れて行った。私が中に入るとフルトンは大丈夫だったのだが、私がどこへ行くかを知ると――もちろん、彼の母が私にラップを脱ぐように言ったので――部屋に入り、ドアを閉めた。メアリー叔母さんが出て来て、フルトンは狂ったように部屋に入ってきて大騒ぎをしたと言った。アルフに嫌なことを言ったと。
当然ながら、私はひどく不快に感じ、喜んでその場を離れた。車を走らせキャンベル家へ行ったが留守だった。そこで私たちは車で戻ってきた。アルフは感謝祭に一緒に帰ろうと言ったが、フルトンの振る舞いを見て、もちろんそんな気分にはなれなかった。
フルトンのせいで 気分が乗らない。だから家に帰った。感謝祭は退屈で暗い一日だった。とても寂しかったよ ベルモントは何て惨めな所なんだ! ビデフォードとは大違いだ
1896年12月5日 土曜日の朝
プリンスエドワード、ベルモント
なんとか生きている。この寒波もそろそろ終わりなので生き残る希望はある。しかし、この1週間はとても貴重なものだった。
以下が私の毎日のプログラムである。
7時に起床し、着替えと髪を整えるために、数分おきに外に出て麻痺した体を温める。焚き火で(リビングにある暖炉のことか)痺れた体を温めながら、服を着て髪を整える。それから朝食を食べる。そして部屋は寒くて耐えられないので上着と手袋をを着込んでベッドを作り、書斎にこもる。(二階で暖炉も無かったのか)
これが終わって、もう一度解凍されると、座って学校の時間まで書き物をする。風が強くなる中、急いで学校へ向かう。
学校が終わると、家に帰り暖をとり、そしてまた学校へ行く。帰宅して暖をとり、9時まで、比較的快適な時間を過ごす。
氷の箱のような寝室に入って、冷たいベッドにもぐりこむことを予期して、また震え出すのだ。
しかし、何度も体が縮こまり、寝床に入り暖まり、そして、ようやく眠り、一日が終わった。
昨日の夕方、メイ・キャンベルと私はアランフレイザーの家に行った。彼らはベルモントの人たちの中では、かなりいい人たちです。
1896年12月7日(月曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
土曜日の午後、私は約束の訪問をするために、不本意ながら席を立った。ソフィー・シンプソンにライル氏の家へ一緒に行くよう頼んでいたのだ。蛍の明りで目を覚ますことができる。
私たちは時間通りにそこに着いた。その日はとてもいい天気で、失われたインドの夏の名残りだった。しかし散歩はとても長く、私は疲れてしまった。午後はというとこれほど憂鬱な時間はない。ライル夫人は悲痛な声で話す女性の一人だ。泣きじゃくるような声で話す女性で、今にも泣き出しそうでハラハラを期待してしまう。まるで人生は涙の谷であり、笑いはともかく、微笑みは筋肉と時間の浪費であり、実に非難されるべきものだという印象を与える。
娘たちは皆、痛々しいほど静かだ。ソフィーは快活とは正反対の性格で、私はめったに世間話をすることができないが、今日は私たちがどんなに賑やかな時間を過ごしたか、想像できるだろう。
夕方にはバートとアルフが迎えに来て、私はシンプソンさんのところへ行って日曜日を過ごした。
日曜日。
メアリーおばさんと一緒に寝たので、いくつか面白いことを知りました。そのうちのひとつはフルトンはアルフにひどい恨みを抱いている――その理由は聞かないことにする。(アルフが私を横取りしたと思ったか)しかもひどく不機嫌で、子供っぽい。彼はあまり良くなっていないようだ。回復が遅いのが気になるのだろう。いずれにせよ、私は最近の彼にはほとほと愛想が尽きた。紳士は彼のような行動はとらない。
日曜日は退屈で静かな一日だった。夕方からメソジスト教会で説教があった。
アルフは私に行くように言った。正直なところ、アルフと二人で行ったらフルトンが世間に迷惑をかけるのではと思ったの、アルフと二人で行くとフルトンが騒ぎ出すと思ったのでソフィーも連れて行った。アルフはその考えを快く思っていなかったが、礼拝の後、アルフが私を家まで送ってくれた時、彼は来週の火曜日の夜、天気がよければ、聖エレノアのコンサートに連れて行ってくれるって言った。
この7週間、私は生き埋めになっていたような気がしていたので、とても嬉しかった。私はベルモントとそれにまつわるすべてが嫌いなのだ。
1896年12月14日(月曜日)
ベルモント、P.E.I.
昨日の朝、私はシンプソン氏の家に行った。招待されないと行かないので。フルトンはまた胸膜炎で病気だ。ひどい変人です。彼の母親も大変ですわ。家中がそうだ。メアリー叔母さん(メアリー・ローソン)は、いつも私にその話を聞かせてくれる。
これまでフルトンは、私がいるときは、自分の気難しさをうまく隠してきた。しかし今回はそうではなかった。私は彼の退屈な病気と長期にわたる監禁の影響について、十分な手当をすることができる。
しかし、(奴は)このような不合理な、また不機嫌な態度をとる必要はない。彼はアルフに激怒し、誰彼構わず疑心暗鬼になっているのだ。かわいそうにアルフは何の変哲もない用事でも、アレフがガレージの駆け寄って、そしてアルフがフレイザーの家に行こうとして、アルフがフレイザーの家の方向に車を走らせたら(フレイザーの家自体は見えない)、シンプソン家はその日1日ずっと罰を受けることになる。(フルトンが大暴れする)(私が気をもたせたせいもある)
もしフルトンが元気だったらこんなバカなことはしないでしょう。母親がかわいそうだ。メアリーおばさんはフルトンが「もう治ろうが治るまいがどうでもいい」と言ったそうだ。フルトンはどう思う?
私は彼と楽しく話し、彼と彼の妹と一緒に一度だけ教会へドライブに行きました。
無害な老婦人を訪ねると約束したことで、他の男や兄弟を差し置いて兄弟であろうとなかろうと、そんな馬鹿な......他に文句があるか?
しかし、私は知っている、私は彼に対するあらゆる忍耐力を失い、今後、私がそこにいるとき、私は単に無視することになるだろう。
今後、私がそこにいるときは、彼が礼儀正しく振舞わない限り、ただ無視することにしよう。
1896年12月21日(月曜日)
プリンスエドワード島、ベルモント
...哀れなフルトンは哀れな状態にある。彼は再び寝たきりになった、今度は脇腹の膿瘍だ。脇腹に膿瘍があり、医師は退院まで2ヶ月かかると言う。彼は今回はそれほど不機嫌でもなく、むしろとてもいい人だった。もちろん、私の心も和みました。
自然が許してくれる限り、私もまた親切にしました。私は彼と本当に友達になりたいと思っている。
というのも、よく訪れる家族の一員と「付き合う」のは、とても楽しいことだからだ。しかしその一方で、私は彼と友好的になることを恐れている。
というのも、そのような(恋人になる)希望や願望を抱かせないためだ。私は、これは私がここに来てすぐにフルトンが病気になったのは、本当に摂理の特別な慈悲だと思う。もしそうならずに、私が彼とドライブに出かけていたら......。彼の情熱はさらに
深まったかもしれない
私が看病できないと知ったらどうなっていたことだろう。キャベンディッシュのウィリアム・クラークは正気を失って首を吊った。母が(モードの母か)彼との関係を断ったからと言われている。そしてフルトン・シンプソンは、感情の激しさと普通の自制心のなさが印象的だった。失望と情熱に圧倒されて何でもしそうな男だと思った。
今日の学校はとても寒かった。夜が恐ろしくてたまらない。私は夜よく眠れないのは、部屋がとても寒いからだと思う。
1896年12月28日(月曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
さて、私は素敵な時間を過ごしている。昔ながらの形容詞である "scrump-tious" (繁盛している)が、唯一それを完全に表現している。もちろん、私はベルモントで過ごしたEdith
Englandからクリスマスを一緒に過ごそうと誘われ、誰かが送ってくれるならと引き受けた。(ビデフォードの)ルー・ディスタンス以外にはいないと思っていたので、「送ってあげてもいいよ」と言った。
水曜日の11時半に(ルーが)到着した。私たちは2時にBidefordへ向けて出発した。寒かったが、道は良かったので、順調に進むことができた。
ルーはいい人だったが、とても静かでした。Tyne Valleyに着くと、道は面白くなり始めた。古いValley(谷)も、Millar氏の家までの道も、すべてが自然に思えた。
またその上(ビデフォードの地)に立つのは本当に楽しいことだった。私たちは4時頃、イングランドさんの家に着きいてイーディスと私は歓喜の再会を果たしました。
その夜、エラズリーでコンサートがあり、私は朗読をすることになっていた。コンサートは単なる日曜学校の行事で、どちらかといえば平板なものだったが、私は古い友人や生徒たちに会って、エキサイティングな時間を過ごした。
その後、Edithと私は家に帰り、一晩中話をした。
翌日の午後、ルーは私たちを氷の上にドライブに連れて行ってくれました。私たちは見事なスピンをして帰りにウィリアムズさんの家に寄った。クリスマスの夜、教会で礼拝があった。ルーは私たちと一緒に家に帰り中に入った。あの子はまだ愚行が治らない。夕方までとても静かで意気消沈しているようだった。私はとても残念に思った。
私は彼をとても気の毒に思ったが、彼のためにできることは、ただ礼儀正しい親しみをもって接することだけだった。
(今日は)午前中にミラーズさんに会いに行き、午後にはルーがが出てきて、イーディスと私を彼の母親のところに連れて行った。学校を通り過ぎたとき、私は古い部屋(ビデフォードの学校)を見ようと走り寄った。私はずっと小さいベルモントの部屋に慣れてしまっていたからだ。
夕方、クリフォード、ルーサー・ウィリアムズ、ウェスリー・マッキノンがやってきて、私たちはとても楽しい時間を過ごした。WesleyはEast
Bidefordの人で、アメリカから遊びに来ていた。彼は私の時代にはいなかった。イーディスはベイフィールド・ウィリアムズと婚約しているにもかかわらず、イーディスは彼ととても仲良くしているようだ。彼女は私にそう言った
彼女はウェスに夢中だ。
しかし、彼が真剣な相手であるはずがないことに気づいている。彼は彼女に夢中だ。ベイフィールドの留守中、二人は愛のお菓子をつまみ食いしています。二人は愛を育んでいるのです。それはある種の危険な遊びである。
イーディスはやり過ぎないようにします。ウェスリーに1、2回のキスをし、一緒に散歩やドライブをしてそして、彼がアメリカに帰ったとき、悲劇的な別れのシーンを迎えるのだろう。二人とも忘れてしまい、ベイフィールドは(今いないのでこのことを)知る由もないだろう。というのがイーディスの見方だ。ベイフィールドに何か良いことがあるわけではない。彼は悪名高い浮気者だ。私が理解できないのは
エディスがウェス・マッキノンのような男に引かれることだ。
日曜日はとても寒く、空気は霜でいっぱいだった。ルーと私は夕方にベルモントへ向かった。ちょうど夕暮れ時で晴れていて、穏やかで、さわやかで、ドライブにはもってこいの季節だった。しかし、かわいそうにルーは元気がなく、私はベルモントに戻るのが億劫で、あまり爽快なドライブとはいかなかった。
イーディスの話では、ルーはかつてないほど酒を飲んでいたそうだ。そこで私は勇気を出して、そのことを話した。彼は否定したが、言い逃れのような形で、私の疑惑を晴らすどころか、むしろ増大させるような言い方をした。
私への愛が人生を狂わせたのだとも言った。私は愚かにも涙を流した。(愚かなことはダメよ)
「あなたが普通の女の子だったらそうかもしれないけど、あなたのような人にはもう二度と会えない」と彼は言った。
「もっと素敵な人に出会えるよ」と私は少し焦りながら言った。ルーが自分の運命を嘆き始めると、ある種の嫌悪感を覚えるからだ。
私はうんざりしていた。ルーは自分の運命を嘆き始めると、何かうんざりしてくるのだ。彼の生まれや育ちの悪さが、そのとき露わになる。
私たちは7時半ごろベルモントに到着した。ルーは一晩中いて、今朝家に帰った。私は学校に行った。徒労に戻るのは辛いと言わざるを得ない(こんな学校の仕事は徒労だと)。大変だった。訪問が続くうちはいいのだが、いつか必ず清算の日が来るのだ。
1896年12月30日(水曜日)
どうなるんだろう? 昨日今日と4月のような穏やかな日が続いている。明日から半年ごとの試験(生徒の学習の進展度を見るために評議員がする試験)を受けるため、このところ学校でだらだらと授業している。
というのも、私は何のプログラムも持っていないからだ。私はプログラムを用意する時間も体力もない。(プログラムに沿った教え方ができないため、行き当たりばったりに教えていたのか)多くの人が来るとは思っていない。(生徒の試験を見るために参観者も来るのか)
今晩はシンプソンさんのところに行った。フルトンは脇腹を槍で削ったそうです。だいぶ良くなったようだ。
夕方、アルフ、ミルトン、シャーロット、ソフィーと私は、キャンプさんのところへ行った。ベルズ SadieとOlive Fraserが来てくれて、想像以上に楽しい夜を過ごすことができた。
猿と天使" を演奏することができた。私たちがS氏(シンプソン氏宅)に戻ったのは11時だった。立派な時間だ(このくらいの時間なら放蕩とは言えないのよ)。しかしフルトンはそれをひどく不適切なものと考えているようで、今朝、自分の意見を述べ、すべての家は夜の(遊び女を締め出す)ために10時に鍵をかけるべきだと主張した。私は彼の将来の家族に同情する。。
1897年
1897年1月2日(土曜日)
本当に97年になるのだろうか? この世紀は、あと3年しか生きられないのだ。
木曜日の午後、私は試験を受けて(教員がしっかりやっているかの試験)、うまく乗り切りました。放課後、私はレポートを作成した。そして、Caleb
Leeのパーティに行った。
もちろん、厳格なバプテストの家庭で、ダンスはありませんでしたが、私たちはかなり楽しい時間を過ごすことができた。
(夜)1時ごろに解散し、家に帰るともちろんすぐに悩みが始まった。私はベッドに入ると骨の髄まで冷え切って、一晩中その状態が続き、一睡もできなかった。
元旦は晴天に恵まれ、(星が)きらきらと輝いていた。私はキャンベル氏の家に招待され、夕食をご馳走になって、楽しいひと時を過ごした。
昼食後、私はSimpson氏のところへ行った。(そこでは)氷の上(凍った海の上)をハミルトンまでドライブする計画を立てていた。F(フレイザーか)、Milton、Charlotteと私の4人で行くことになった。私が門をくぐるとメアリー叔母さんが突然玄関に現れ、不思議そうな顔で私を手招きした。
おばさんは私を応接間に引きずり込み、まるでダイナマイトを使ったかのようにそっとドアを閉めた。そして、共謀者のささやき声でこう言った。
私が大勢の人と一緒に(ドライブに)行くことをフルトンに知られたくなかったのだ。彼はまた病気なのでシンプソン夫人と(メアリ大叔母と)二人で、私を門で迎え撃ち、再び門からこっそり連れ出すことにしたのだ。
厨房の窓から見える範囲にたむろしている私を、玄関からこっそり連れ出すことにすると決めていた。この作戦は実行に移され、フルトンは嫉妬に苦しむ午後を過ごさずに済んだ。
私たちは湾の上を楽しくドライブした。氷は素晴らしい状態で、すべて青と白に輝いていた。湾の冷たい広がりは、美しい女性の胸に輝く宝石のような薄暗い紫色の小島と、霧のかかった紫色の海岸に縁取られていた。私たちは時間を忘れて楽しみ、目的地であるウィリアム・シンプソン氏の家には4時半ごろに到着した。シャーロットはそこに泊まったが、私と(シンプソンの)息子たちは、暗くなってから家に帰った。
私はメアリー叔母さんと一緒に眠り、楽しい話をしました。彼らはほとんどフルトンのことで消耗している。フルトンは不機嫌で、嫉妬深く、お節介で、屁理屈ばかりで、とても耐えられないのです。実際、病気や苦しみが心に影響したのでしょう。
フルトンはとても荒々しく、得体の知れない顔をしています。母に「(自分を)治す気がない、治そうとしない」と言い続け、母を苦しめている。アルフとは喧嘩をしたり、侮辱したりする以外、口をきかない。彼は今朝も、私がハミルトンに(ドライブに)行ったことを知ると、とても意地悪になった。
でも私は冷静に受け止めましたよ。私は彼に何も悪いことをしていないのに、そんなことで心配することはないのだと。
1897年1月4日(月曜日)
ベルモント、P.E.I.
さて、これは「天気の呪文」だ! 私は寒さに長い間不満を持っていた。恥ずかしながら、今更、雨、霧、泥に文句を言う気にはなれない。不平を言う勇気はない。そうでなければ私は勇気を出して遠慮します。
土曜日は、頭上も穏やかで、水平線は霧に包まれ、湾の氷はガラスのようにまぶしく、完璧だった。しかし、足元は......まあ、それは言わない方が私の決意には良い。私の決意は固まった
昨日の朝、バプティスト教会で説教があった。私が来てから初めてだ。伝道師のベイカー氏が、ここで集会を開くためにやってきたのだ。私は原則として「リバイバル」(福音の再臨運動、また新しい喜びの奇跡があったというような物)を認めないが、この地の単調な生活に変化をもたらすものであれば、何でも歓迎する。
昨日は2回説教をした。私は自分の意志に反して、オルガン...(を弾くか)自分の意志に反して、組織的に行動しなければならない。しかし私はシンプソン夫妻に、いや、むしろシンプソン夫妻に恩返しをしたかったのだ。
私は "サム"(伝道師)には興味がないので、むしろ後者です。シンプソンの香りが強い。でもシンプソン夫人は好きだし、とても親切にしてくれた。
昨日も夕食をご馳走になった。日曜日はそこで過ごすのが当たり前になっている。そうでなければ、私はここで孤独死してしまうだろう。それにメアリー叔母さんがいる限りは(シンプソン家に)行くのはとても楽しいことだ。
私のせいで二人の少年が仲が悪いという事実が、いつも私を不愉快にさせるのだ。それに私にはフルトンからどんな暴言が飛び出すかわからない。彼は相変わらず調子が悪く、不機嫌なままだが、少しずつ回復しているようだ。?
今日は雨で蒸し暑く、ひどい天気だった。学校へ行くのも大変だった。
今夜は "ミーティング"に行ってきた。サイモン(私が下宿しているフレイザー家の主人)が荷車をひいて、みんなを連れて行ってくれた。でも、学校から疲れて帰ってきた、疲れ切った
"schoolma'am"(学校の母)にとっては、完璧な恩恵だ。(荷車に乗れたから)
学校から死ぬほど疲れて帰ってきて、暗闇の中を半マイル歩いてまた出かけるのは気が引ける。暗い中、足首までの深さの泥と水の中を半マイル歩くことになるのだから。
1897年1月18日(月曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
昨日は夢だった、詩だった、シンフォニーだった、何とでも言えるが、その定義が幽玄な喜びを表現している。色彩の幽玄な盛り上がり、スリリングな栄光と輝きを表現している。霜に縁取られた丘を越えてバラ色と黄金に彩られた素晴らしい一日(雪の野も青空の元では綺麗なのだろう)。夜には月光の妖精の国に消えていった。
私は朝の礼拝の後、シンプソン氏の家へ行った。ラップ(コートか何か)を脱いで降りてくると、フルトンが部屋の窓からにらんでいた。
私は愛想よく言った、「調子はどう、フルトン?」。彼は肩越しに黒い視線を送りながら、不機嫌そうに「良くなっているよ」と言った。
私は肩をすくめ、メアリーおばさんに微笑みかけると、もっと気の合う仲間がいるところに移動した。応接間でもっと気の合う仲間と一緒に過ごすことにした。それ以来、私はフルトンと話をすることはなかった。
しかし、彼は猫のような忍び足で私を見ていた。私は不安になった。健康に関しては、彼はドクターが「良くなっている」と言っているように見える。「しかし、彼のマナーに関しては」そうとは言えない。
私たちは午後の礼拝に行き、その後シンプソン氏の家でかなりの人数の人がお茶をした。そして、アルフの運転(御者で)で、彼の野性的なグレーの雌馬「モード」(名前に似合わず!)で夕方の礼拝に行った。
私が「おやすみなさい」と言ったとき、フルトンは何も言わなかった。でも、庭に出ると、明るい台所の窓からシルエットで外を覗いているのが見えた。私がどうしているかを探ろうとしているのだろう。どうやらうまくいかなかったようだ。私たちが家の前の道を走ったとき、彼は居間の窓に張り付いていたのだから。そのため、このように早く到着することができたのだろう。
今夜の教会はとても混んでいて、私はずっとオルガンのスツール(小椅子)に座っていなければならなかった。そのせいで背中が痛くなりそうだった。
今日は一日中雨が降っていて、物事が不愉快になるような大暴れ(の天気か)でした。
1月27日(水)1897年
ベルモント、P.E.I.
このところ、いろいろな冒険をしている。"私の悲哀の物語を聞いてください"。
火曜日の夜、アルフと私はポートヒルで行われる大分会の会合に出席するため、湾を渡って出発した。ポート・ヒルで行われたグランド・ディビジョンの会合に出席するためだ。霜が降り、風が強かったが、順調にウィル・モンゴメリーの家に着いた。
そこにはフルトン、ハミルトン(場所の名)のウィリアム・シンプソン、そして私の特別なペットがいた。シンプソン家の中でも特に私のお気に入り、キャベンディッシュのアーサー・シンプソンもいました。
みんな朝から行っていた。大師団はシンプソンズ抜きでは成り立たない。
フルトンがスピーチをした――彼は本当によくなっているようだ。月曜日の昼過ぎに、彼はソフィーに続いて学校に来た。"ソフィー"
と呼んだだけで私の存在に気づかなかった。だから私は彼がもっと不機嫌になることを期待していた。
しかしおそらくは、(学校という場所の)その親しみやすい効果のためか、あるいは私の親族や自分の親族の前で悪い自分を見せびらかしたくないためかとても愛想がよくて、アルフの存在に冷静に耐えているようだった。やっと正気に戻ったかな? と願っています。
(モードはたくさんの男たちと付き合い、気を持たせた)
ホールにはイーディス・イングランドやルー・ディスタント、その他にもたくさんの人がいた。Bidefordの人たちと、とても楽しい時間を過ごした。
コンサートの後、みんなでウィル・モンゴメリーの家に行って夕食を食べたが、とても満足のいくものだった。私たちは11時頃、3つのそりで出発した。フルトンは家に残った。氷の上までずっと快晴で穏やかだっが、氷の上を1マイルも走らないうちに、突然氷が割れてきた。
しかし、氷の上を1マイルも走らないうちに、突然目もくらむような雪が(吹雪が)降ってきたのだ。あっというまに白い渦に包まれ、茂みから次の茂みまで見えなくなった。30分近くも藪をかき分けたが、道には出られない。私たちは完全に混乱し、ついにベルモントまで2回行けるほどの距離を走ったところで、車を停めて作戦会議を開いた。
あの三人は、嵐の中で、なんと吠え、叫び、一度にしゃべりまくったことか。それぞれが異なる意見と計画を持ち、自分が正しいと確信していた。シンプソンズの意見が一致しないとき、誰が決めるのだろう? 彼らはどのような行動計画にも同意できなかったので、私たちは30分ほどその場にとどまり、晴れるかどうか様子を見ました。
アルフは、私が寒さを感じないようにバッファローのコートを着せてくれた。
そして、スコール(夕立ちの意味だがここでは吹雪の意味)は相変わらず激しく、私たちは風を切って出発することにした。もし、風が変わらなかったら......これは、かなり重要な「もし」だ。
マルペケ岬を横切れば。もしそうなら......そのまま海峡に突っ込むかもしれません。
しかし、そう長くはかからず、私たちは陸地にたどり着いた。最初、男たちはそれが道だと思った。しかし、しばらく走ると、そうではなく、ここがどこだかわからなくなった。ようやく、野原にかすかな明かりが見えたので、そこへ向かうことにした。道路を探しても無駄だ。ただ道を作るしかない。私たちは
土手に出て、柵を破り、2つの畑を横切った。ここはまずまずの道だった。
しかし、次の畑は湿地帯で、霜が降りて、芝生が巨大な塊になった沼地だった。
このひどい場所を、どうやって何もかも壊さずに通り抜けたのか、それは私にはわからない。私は
ランナー(橇の枠)が "バキッ" という音がするんじゃないかと思ったほどです。私は半分凍りつき、完全に怯えていました。
でも、アーサー・シンプソン(Arthur Simpson)が「どこにいるんだ!」と絶え間なく叫ぶのを聞いて、私は笑いに震えました。どこに連れて行くんだ、アリー? どこに連れて行くんだ、アルフィー?"。彼は私たちよりずっと前にいて夢中で走っていたので、「アルフィー」が彼をどこかに連れて行ってくれるようには見えなかった。
アルフィー" は彼をどこにも連れて行かないようだ。馬はそりの揺れに恐怖を感じ、つかまることも縛ることもできなかった。
しかし、結局、私たちはこの道を通り抜け、次にぶつかったのは堤防だった。他の2頭の馬はうまく乗り越えたのだが、「モード」(が乗っているソリ)はひるみ、飛び跳ねついには蹴ってしまった。蹴られた...。(ひっくり返ったのか)私たちのトレースは壊れ、私は外に出て、アルフがそれを修理する間、待たなければならなかった。
そりを持ち上げて堤防を乗り越えたが、まだ雪が舞っていた。私は冷え切ってしまった。でも結局、また出発して、あと10分もすれば、あの祝福された家に着くのだ。
――
どこだと思う? 14番地のジョン・マッカーサーの家だ、私たちが出発したところから半マイルも離れていない。風向きが変わったんだ! そしてずっとベルモントに
向かっていると思ったのに! 一晩中そこにいることになった 疲れと寒さで一睡もできなかった。その上宿泊施設(ジョンの家)はとても貧弱だった。私たちは朝早く出発し、すぐに家(シンプソンの家)に着いたが、その冒険はそれほど悪いものではなかった。
私はこのような会合(グランド・デイビジョンの会合)は終わればいいと思うほどだ。というのも私は自分の仕事にひどく遅れをとっているからだ。それでもこの場を少しは活気づけてくれる。週に2、3回でいいんだ。今夜はベイカーは発言しなかった。マクラウド氏が話したが、彼は狭量で無教養な狂信者であり、極めて不愉快なタイプである。
1897年1月30日(土曜日)
さて、今朝はあることが起きました。サイモン夫人は、重要な雰囲気を漂わせながら二階の部屋、つまり長い間約束され、ほとんど絶望させられていた部屋が用意できたと言った。もし私が気に入れば、すぐにでも引っ越すことができる。
私が気に入ったのは確かでしょう。この惑星で私が嫌いな場所があるとすれば、それはあのアイスボックス(私が元借りていた寒い部屋)だ。ここに来てからずっとあの氷の箱で寝ているのだ。
2階の部屋はベルモントの中ではかなりいい部屋だ。広さもちょうどいい。
パイプ(薪のストーブから出ている煙突が通っていたのか)で暖められ、テーブル、洋服ダンス、マントルピースがある。今日の午前中は "飛び回る"
(部屋を私向きに飾る)ことに専念し、正午までにすべてを可能な限り整え、居心地のよい場所にした。私は新しい生き物になったような気分です。
1897年2月2日(火曜日)
ベルモント、P.E.I.
昨日、私は今まで受け取ったどの手紙よりも驚いた手紙を受け取った。エドウィン・シンプソンからの手紙だ。彼から文通を申し込まれて以来、2、3回手紙を書いたが、その結果、3通の手紙が届いた。その手紙はとても興味深く、巧妙なものでしたが、文体はやや退屈なものだった。
昨日の手紙は、数ページにわたる長いものだった。始まりは私の最後の手紙に対するコメント、大学のニュース、そして連休中に彼がハリファックスを訪れた時の話と、何の変哲もないものだった。
5ページの真ん中あたりまでは。そして彼は突然、次のような文章を残して、突然途絶えてしまった。
なぜ、私に文通を申し込んだのか。
目のトラブルでハリファックスに行くことにならなかったら、Xmasに話すつもりだった。そして、「その時、私は今、あなたに話さなければならないと感じていることを、個人的に話すことができたでしょう。それは、あなたを愛しているということです"
私は驚いて、手紙を落としそうになった。エドはさらにこう続けた。5年前にパーク・コーナーで会ったときの友情は、今も続いていると。その印象は決して忘れないと。徭蛍(遥かな過去の記憶)で恬っている。
彼は私に会おうとしなかったが、それは彼のような立場の人間(学も自尊心もある人間)がそのような誘いをするのは馬鹿げていると思ったからだ。しかし今、彼は「自分の道が見えてきた」という。今は、「自分の道は "人生の活躍の場"にあると思う」し、「以前の空想は、抑えがたい情熱に深まった」。
こんなことが本当にあるなんて信じられない。他の男性に愛されたことがあっても、しかし、エドウィン・シンプソンが私のことを気にかけているとは思いもしなかった(モードはお人形のように可愛いから)。私たちはこの4年間、ほとんど他人だった。この4年間は、パーク・コーナーの時代にあった私たちの小さな
"情事" は何の意味もありませんでした。
当時はレムほど好きではなかった(ちょっと遊んでいただけ)。去年の秋、彼が私に文通を申し込んできたときでさえ私はレムほど彼を好きではなかった。私は彼が私に文通を申し込んできたのも、私が楽しい手紙を書き、家庭の事情もすべて伝えることができると知っていたからだと思っていた。彼の母親は、彼の唯一の文通相手だ。
母親は唯一の文通相手で、彼女の手紙は面白いものでもゴシップでもないでしょうということだ。
明日、彼の手紙に返事を出さなければならないんだが、この仕事は全く気が進まない。私ができるのは私は彼を愛していないからです。彼を大切にすることを学ぶ機会がなかったからだ。
この夏彼がうちに来たとき、私は彼を面白く思い、彼がとても成長したと思った。でもそれ以上のことを考えたことはない。私は彼の世話をすることを学ぶかもしれない。と思っていた。彼はハンサムで、賢くて教養があり、私たちの好みは多くの点で似ている。私が世話をすれば、とてもうまくいくでしょう。
しかし、私の家族は、少なくとも祖父と祖母は、それを認めないだろう。祖父と祖母はシンプソンズ(シンプソン一族)を嫌っているし、祖父は、股従兄弟が結婚するのを熱烈に反対している。
エドはバプティストです。私自身は、どちらの理由も本当の愛情に反するものではない。でも家族の顔色をうかがっても仕方がない。
.jpg)
私が世話をする旦那さんは優しくて頭がよくて家柄もいい人でなければだめ
1897年2月3日(水曜日)
プリンスエドワード州、ベルモント
エドからの手紙に返事を書く時間を作るために、今夜のミーティングは家にいることにした。エドの手紙に返信する時間を確保するためです。ベーカー氏はそれを正当な言い訳と考えるだろうか!?
私はエドに、彼の手紙にはとても驚いたし、彼を愛しているわけではないことを率直に伝えました。彼のことをそんなふうに思ったことは一度もない。私はもし彼がしばらく待ってチャンスを得ることを望むなら、私は彼のことを気にかけるようになるかもしれないと言った。
でも、もし彼がすぐに最終的な答えを出したいのなら、それは「ノー」でなければならないでしょうと言いた。(すぐにはダメよと)こう言う返事をだしたので本当によかったと思う。
1897年2月7日(日曜日)
ミーティングはまだ続いている。ベイカーは明らかにベルモントに罪人を残したくないと決心しているようだ。サイモン夫人の言葉を借りれば、みんな「いい子になる」しかないのです。
昨夜からベイカー氏には用はない。"二次会" で彼が言い出したのは、浸礼について偏狭な説教をした。私は密かに激怒していた。毎週毎週彼のためにオルガンを弾いてきたのに、彼が私の前でそんなことを言うなんて、侮辱だ。
明らかに彼は恥ずかしさを感じていたようで、演奏が終わると、私に向かって屈辱的な笑みを浮かべ、こう言った。
「もちろん、皆さんはバプテストの信者でしょう。そうでないならそうなるべきだ」。(信仰告白をしてから洗礼を受けてバプテスト派に改宗しなさいと)
私は微笑んで答えることはできなかった。私はスコットランドの長老派の曽祖父と同じように気難しい顔をしていた。(私は民主的・合議的に教会を運営すると考えている長老派だ)
ベイカーがバプテストの人たちだけに話しているのなら、なぜ浸礼について話すのでしょうか。彼らは納得する必要はないのだ。
しかし、今夜はベイカーやバプテスマとは全く関係のない私の理由(小説に使う経験を得る為か)から再び集会に行った。アルフと私は帰宅後、恐ろしく動揺しました。帰ってきてから道路がギャンブルの門で曲がるところで、ひどい斜面があり、そして雪が積もっているのです。
雪が降ってきた。私たちはすごいスピードで走っていて、雪崩にぶつかったとき、そりがきれいにひっくり返った。アルフと私と私の毛皮は山のようにこぼれ落ちた。それは幸運なことでした。
その時、シャフト(橇の座席)に座っていたのが、おだやかな「レディ」であって、あの「モード」でなかったのは幸いでした。そうでなければどうなっていたかわからない。アルフと私は後ろの子供たちの嘲笑的な叫び声に耳を傾けながら立ち上がり、カッターに乗り込み走り去った。この出来事は10秒で終わった。
1897年2月17日(水曜日)
月曜日の夜は、ここでのサービス(伝道師の説教か)はなかった。だからベイルとアルフと私はセントラルに行った。Mr.マクロード氏は魔法のランタン(聴衆を惑わす仕掛け、幻灯機のことかもしれない)を持っていた――リバイバル・ミーティングのための最新のごまかしだ!――そして会場は満員だった。彼の絵はとてもすばらしかった。(後ろの壁にスライドを投影しながら説教したのか))
特に、改心していない人の心を写したものは、大きな赤いものが真ん中を切り裂かれ、様々な種類のもので満たされていた。ヘビ、ハイエナ、オオカミ、その他の不快な生き物で埋め尽くされている。
もし、ガリラヤの厳格な教師がそれを見て、マクラウド(宣教師)のヒステリックな叫び声を聞いたら、どう思っただろうね。
火曜日の夜、アルフと私はS'Side(サマーサイド)の "Birthday Social"に行ってきた。私たちは楽しいドライブをし、社交界も楽しかった。帰りはワイルドなドライブになった。アルフとウッドランド・シモンズはずっとレースをしていた。WoodlandとAlfは共にベーカー(宣教師)の手ほどきで「改心」し(シンプソン家は福音派だったので宣教師の説教で感動した)、前者は毎晩のように声高に証言している。しかし、どちらも馬肉の問題で叩かれるのは納得いかないようだ。
「名誉のために、互いに好意をもって」というのは、自分の好きなトロッターが問題になっているときには通用しない。私としては、一瞬であの野原を飛び越えて氷の上を滑るように走り、他のソリをわずかな差で見逃してしまう。
この夜、ベイカー氏は、"ディアボロス" と呼ばれるディアボロス・スライドを開催した。今晩、ベイカー氏の告別式(この地を離れる送別会)が行われた。彼はここからキャベンディッシュへ行くそうだ。そこでは、私が間違っていなければ、もっと感受性の低い(宣教師の演説には感動しない)人々が見つかるだろう。アルフと私はその後で楽しく回った。
1897年 2月23日(火曜日)
今日はとても荒れた天気だった。学校には16人しか生徒がおらず、まるで遊びのようだった。 しかし、私はここで教えるのが嫌でたまらない。とても大変な仕事だし、ほとんどの子供たちは愚かで、無知で、乱暴です。これは彼らがどのような家庭で育ったかを考えれば、驚くことではない。
私が楽しく仕事をしていた頃のビデフォードとは大違いだ。
今夜、私はモリーに長い手紙を書いた。ベルモントには友達がいない。それが何より寂しい。10代前半の頃、半分子供で半分少女だったあの頃が、今はどんなに遠くに感じられることでしょう。
10代前半の頃、半分は子供で半分は少女だった。でも、もしどちらかを選ぶとしたら、あの頃に戻ろうとは思わない。私は今あの頃よりも幸せだと思う。どんな時代にも悩みはある。私の場合、私の子供時代や少女時代にも、今の時代と同じように悩みがあり、現実的だった。だからもう戻りたくないのだ。
とはいえ、先の見えない苦労や努力に嫌気がさすことはある。ということで結局は戻りたいとは思わない。
1897年3月1日(月曜日)の朝
寒波がやってきて、水銀が氷点下20度まで下がった。今、新しい物語を1時間書き終えたところだ。
指が冷たく痙攣して、ペンを持つことができない。本当に私は困難の中で文学を追求しなければならない。今日学校に行くのが恐い。部屋はひどく寒いだろうから。
金曜日の夜は、シンプソン氏の家で合唱団の練習があり、私はオルガン奏者として行かなければならなかった。私がそれをどんなに嫌いか、誰も知らないだろう。私は一晩中いた。フルトンは土曜日にキャベンディッシュへ船旅に出かけた。長い旅になることを願うよ。彼と私はこのところ、「達観した不活性主義」を貫き、「通り過ぎるときには決して口をきかない」という方針をとっている。私は、不当に侮辱されるのが嫌になったので、もう彼のことは気にしないことにした。この育ちの悪い野暮天を相手にすることはなくなった。
さて、そろそろ学校へ行かねばならない。夜までに凍えないことを祈るのみだ。
おやすみなさい。
いいえ、私は!硬く凍ってはいないが、その寸前まで行ったので面白みがない。
しかし学校は今日で終わり、私はここに座って暖かくしてから仕事に取り掛かろうとしている。(文学が私の主な仕事)
今夜、エドから手紙が届いた。彼は私の返事を最終的なものと受け止めず、もう少し待つと言った。
私の返事を最終的なものとして受け入れるのではなく、将来より有利な返事が来ることを期待して待っているとのことだった。彼は私に以下のことを懇願している。
今回の件が私たちの友情に影響を与えないよう、文通を続けていきます。友好を深めよう。
1897年3月8日 月曜日の朝
昨日の夜、アルフとバートと私はセントラルに行き、"轟音ビリー"の講演を聴いた。 彼は1時間半以上にわたって、鉄道の汽車に例えた興味深い話をした。
彼の定義による鉄道車両とクリスチャンの類似性について、1時間半以上も語ってくれた。 昨日の朝サイモン夫人と私は、ヒギンズ氏のバプテスト教会での説教を聞くために車を走らせた。
ヒギンズ氏は身体的な面では驚くべき人物である。 H(ヒギンズ)氏は肉体的には驚くべき生物である。彼は端から端まですべて間違って組み合わされた残骸から作られているようだ。
しかし彼はそれほど悪い前段階ではない。でも悪い説教者ではありません。
夕食後、私は招待されたS氏の家に行き、アルフ、バート、ソフィーと一緒に箱そりでドライブした。 箱そりに乗ったソフィーはよくある "不機嫌"
な状態で話もしない。彼女は私が今まで出会った中で最も奇妙な人間だ。私は彼女がいるときは、彼女が機嫌の良いときでさえ、決して快適ではない。しかし、私は沈黙の痙攣に悩まされることのない少年たちとおしゃべりをした。
午後、アルフと私はS'Side(サマーサイド)に行った。その日はとてもいい天気で、楽しいドライブができた。 私たちは友人たちとお茶を飲み、夕方には長老派の教会に行った。
月夜のドライブの後、10時に家に帰った。 しかし火が消えていたので(暖炉の火か)、私は冷え切った状態でベッドに入ることを余儀なくされた。 その結果私は一晩中寒く惨めに眠り、今朝は薄気味悪く感じた。
しかし人は楽しむために、常に何らかのペナルティを支払わなければならないのだろう。 私はいつもそうだ。時には倍返しだ。 アルフと私は来週金曜日、天候と道路が許せばキャベンディッシュへ行く予定だ。
その夜ルゥがパーティーを開くので、それに参加したいのです。(モードは遊び歩いていた)(社交だ)
火曜日の夜 1897年3月9日
私は恐ろしく疲れている。火曜日と木曜日は学校ではいつも大変な日なのだが、この特別な火曜日は7人の悪魔に取り憑かれているようだ。
しかし今日、2つの小説の受理があり、少し元気が出てきた。ひとつはアーサーズ・ホーム・マガジンから、もうひとつはフィラデルフィア・タイムズからである。
やれやれ、人生に価値はあるのだろうか? 今のように疲れているときには、そうもいかない。
1897年3月15日(月曜日)
金曜日の午後、アルフと私はキャベンディッシュに向けて出発した、しかし最近の雨と雪で道路は大変なことになっていた。しかし私たちは非常にうまくいき、3時にクリフトンに着き、ウィリアム・モンゴメリーの家でお茶を飲んだ。そして家に着いたときはちょうど暗くなっていた。到着したときはとても驚いた。
その後 パーティーに行ったが、楽しかったとは言えない。アルフは踊らない。ダンスは許されない罪だと思っている。知らない人たちの中に彼を置き去りにするのは好きではない。だから私もあまり踊らなかった。
夜通しクロキノール(駒をはじいて対戦するボードゲーム)で遊んだが涙が出るほど退屈だった。私はダンスが好きで、クロキノールが嫌いなのだ。(パーティーは夜通し)
日曜日の午後にCavendishを出て、Park Cornerに行き、アンクル・ジョンCの家に一晩中泊まっていた。今朝は早くから出発しなければならなかった。天気は良かったのだがとても寒かった。
昨夜は雪が降ったので道路はとても重かった。
マルペケに着く頃には風が吹き始め、吹き荒れる北西の風と吹雪の中、湾内を走らなければならなかった。ここに着いたとき、私は半分凍っていたが、ベルモントでは疲れを癒すことはできない。
ベルモントでは休む暇もない。急いで学校に行き、まるで猫が運んできたような気分で一日を過ごすことになった。
1897年3月17日(水曜日)
ベルモント、RE.I.
今回帰ってきてから、とても寂しく、ホームシックになった。この家はキャベンディッシュでの滞在の後、より粗く、より下品になったようだ。私はこの人たちは何のために存在するのだろうとよく思う。何の喜びもないように見えるが、充分満足しているようだ。生まれつきの盲人は視力を失うことはないのだろう。(目の見えない苦労も知らない)(私のように風流を解する人間でなくてどうすると言っている)
シモン自身にも言えることだが、この男には何の楽しみも多様性もないように見える。隣人たちと同じように、何一つ楽しみがない。彼は奴隷のように働くがしかし彼は貧しい。彼はどこにも行かず、教会にも行かない。彼らは決してこの土地に仲間がいることもなく、他の土地に行くこともない。彼の日々は、絶え間なく続く雑務に費やされている。
サイモン夫人は、主君と対をなす女性なのだ。ダンに至っては、人間とは思えないほどだ。もし彼に魂(趣を感じる心のことか)があったとしても、それはとっくの昔に萎えてしまったのだろう。
そんな人たちと、私は当然ながら何の共通項も持てない。私は彼らの中で生き食べ、眠り、話すが、どの接点においても、私は彼らの仲間ではない。
1897年4月9日(月曜日)
ベルモント
この一週間が終わって本当にうれしい。というか、歩いていたので疲れた。この先も長いと思う。
私は精神的な苦痛に呻吟する準備ができている、私は確信しているので私は耐え難いほど孤独だ。
淋しさに耐えられなくなりそうだ。だからもうそりの旅はしない。ベルモントでもう1年教えるのはやめようと決心している。フレイザーズでの仕事は大変でもう1年も続けられない。私はベルモントが嫌いだ。
人々は、3つの家族を除いては、完璧な野蛮人だ。そうですね、他の学校を探すのは大変だろうけど、ここで健康を害するのは意味がない。私は最近とても神経質でよく眠れないし、いつも風邪をひいている。冬の間、二人の教師の仕事(マリーの受験勉強を見ることもあり)をこなし、半分凍えていたせいで、いつも風邪をひいているようだ。
私はまだ執筆(自分の仕事、小説書き)に励んでいる。文学の道は、はじめはとても遅いものだ。しかし、昨年のこの時期からずいぶん進歩した。――遅かれ早かれ成功すると信じて――、忍耐強く努力するつもりだ。
今、自分の部屋にいるのだが、その様子を書き留めようと思っている。その姿を記憶にとどめておくためにね。
ダークブラウンに明るい色の縁取りが施されたドアには、ピンクのダスターバッグ(ゴミ袋)、ビーズの洋服ブラシポケット、そして様々な写真から切り取られた写真が貼られている。雑誌から切り取った写真のメドレーも貼られています。マントル(暖炉)の上の壁には、ジャック・サザーランドの小さな写真と、リアンダー伯父さん(が牧師をしている)教会のカレンダーがかかっている。
マントルには、「サンビーム・フォト」、数年前にウェル・ネルソンから貰ったチャイナドッグ、花瓶、箱類、そして......奇妙な品物が並べられている。
花瓶、箱、瓶、クリンパー(缶の蓋を締める道具)、シンブル(指ぬき)などだ。隣の壁には、3つのおしゃれなカレンダーと針の本、カーリングトングホルダー(髪をカールするための焼き小手を掛ける取って)、写真などがかかっている。私の小さなテーブルの下には、数冊の本とスタンドミラー、マドンナ(聖母子像)、そして私の宝石箱がある。
その隅にはカーテン付きの棚があり、その棚には驚くほど赤いキャラコでできたドレープ(襞の付いたカーテン)が私のドレスを飾っている。上の棚は帽子で埋め尽くされ、下の棚は雑誌や学校の教科書で混雑している。窓には同じくターキーレッドのランブレキン(折りたためる飾りカーテン)がかかっている。
その前には私の洗面台(水差しと、排水用のバケツが置いてある棚)とその付属品がある。その窓からはシモンの台所の屋根が見えるが、その向こうには美しい港が見える。片方には12×6の大きさの鏡があり、私のベッドの上には、時計のポケットとカレンダーがある。Xmasになると友人たちはカレンダーをよく使う。ベッドの足元には、私のトランクがある。
(まさしく花開く19世紀の調度ですね)
1897年4月15日(木曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
今日、私はとてもショックを受け悲嘆に暮れている。私はなぜウィル・Pが私の最後の手紙に返事をくれないのか、この3ヶ月間ずっと不思議に思っていたのだが、今日ローラから手紙を受け取った。
ローラから手紙が届き、ウィルは4月2日に亡くなったと告げられたのだ。
それは私にとって大きなショックだった。もちろんこの忙しい年月の間に、ウィルと私は互いに距離を置くようになった。
しかし私たちはずっと文通を続け、私は同志のような愛情をいつも感じていた。彼が死んでしまうなんて。彼はとても生命力に溢れた人でした。彼はインフルエンザにかかり、長く苦しい合併症の末に亡くなった。ローラの話では、彼の苦しみは大変なものだったそうだ。彼の苦しみはひどく、彼は死を覚悟していたそうだ。
ローラは悲嘆に暮れ、彼の両親もその衝撃に打ちひしがれている。ウィルは模範的な息子であり兄弟であり、家族は彼をかなり崇拝していた。
私は泣き叫ぶと、トランクから10年前のウィルの手紙(10年後に開けて読むことにしていた未来への手紙)を取り出した。書いてからまだ6年しか経っていないが、理解としては、このような事態になった場合、――しかし、我々はそれが起こるとは夢にも思っていなかった――その手紙は読まれることになっていた。
封筒を開けたときの私の気持ちは、言葉では言い表せないほどであった。その手紙は、まるで死者からのメッセージのように思えた。それは愛の手紙であり、彼が普通の手紙に書くよりももっと分かりやすく語っていた。それを読んで貧しい孤独な私は傷ついた
ウィリーが死んだ!遠い草原に埋葬されたんだ。そんなはずはない! ありえない。
私たちが高校でノートを書き、冗談を言い合って笑ったっけ? 歩いて帰ったのは? 6月の紫の夕暮れに川沿いを散歩したのも、つい昨日のことではなかったか。6月の夕暮れ、ブルーベルが咲き乱れる大草原を歩き回ったのは、つい昨日のことだろうか? そして乙女湖でピクニックをし、湖畔のポプラの木に名前を刻んだのはつい昨日のことだろうか? 残念だが6年も前のことだ! ウィルは死んだ
ローラは彼を失ってどれほど寂しいか。彼らはお互いにとても献身的だった
1897年4月19日(月曜日)
ベルモント, P.E.L.
親愛なるローラへの長い手紙を書いた 金曜日に書いていてとても慰められた。今日は春の陽気で、まろやかな南西の風が吹いている。
氷はすっかり溶けて、湾は青く輝き、庭の片隅には小さな緑のものが顔を出している。
《リーガル版日記原書、第一巻の終わり》
1897年4月25日 日曜日
ペンシルベニア州ベルモント
日曜日の午後、私はベッドに丸まり、眠くなり、眠気に襲われながら、文章を書いている。
私は食後の仮眠から目覚めたばかりで、かなり頭が重い。何もすることがないので、日記にくだらないことを書き込んでいる。いたずらしないようにするためだ。
今朝は4月の愛すべき日の一つであった。暖かい南風、かすんだ地平線、全体的な夏らしさを感じさせる空気だった。地面がもう少し乾いていれば、散歩に出かけられるのだが、ベルモントは、いつでも一人で散策できるような場所ではない。キャベンディッシュやビデフォードのように、緑豊かな小道や人里離れた野原はここにはない。
キャベンディッシュやビデフォードのような唯一の場所は湾岸で、そこは遊歩道としてはやや湿っぽく、沼地になっており遊歩道には向かない。遠くから、青く輝く水と紫に覆われた海岸の新しい美しさを味わうことで満足しなければならない......。
テーブルの上の小さな花瓶に、銀色に輝く柳の枝を2本挿して飾っている。お化けの森」にあった柳の木を思い出す。
そして、果樹園のポプラの木には、ネコヤナギがたくさん生えていてポプラを思い出す。私は木が大好きです。まるで木と私が一体であるかのように、木の生命と癒しが体中の血管を通り抜けるのを感じながら、木に顔を近づける。故郷には、私がとても愛している木があります。指の一本でも切り落とされるのを見たいくらいに。
庭の白樺、家の裏の高いバルサム・ポプラ、裏のトウヒなど。井戸の裏の古いスプルース、小路の桜の木などです。
私はP.A.にいた時、孤独な時にそれを見て言いようのない慰めを得たことを思い出す。芝生の自慢の一本、門のところにある葉の茂った西洋カエデだ。そして大草原では、いつも白い茎のポプラに親近感を覚えた。
まるで、その樹液が私の血液と混じり合っているような気がした。もしかしたら......。そうかもしれない。もしかしたら、私は他の存在形態では木だったのかもしれない。だから私は木が好きで、森の中にいるととても落ち着くのだ。
私はいつも、転生という古い教義に傾倒しているようなところがある。自分がどこかで生きてきたと
私は以前にもどこかで暮らしたことがあると信じて疑わない。
そろそろ5月の花の季節だ。私はその光景を待ち望んでいる。夏の国からの小さな淡い巡礼者たち。五月、花を探しに「荒れ地」を彷徨い歩いた昔の春の思い出とともに。甘く香り高く、恥ずかしがり屋で、スプルース(松の木立)の隙間やくぼみにひっそりと咲いていた。
キャベンディッシュ、P.E.I.
1897年5月12日(水曜日)
先週の土曜日に家に帰りた。汽車は「学徒兵と政治家」でいっぱいだったと誰かが言っているのを耳にした。祖父がケンジントン駅で出迎えてくれて、寒い中家路についた。
日曜日は教会に行った。私は、キャヴェンデッドにいる他人のように感じ始めていることに気がついた。キャベンディッシュ教会にいる他人のような気がしてきた。日曜日の夕方、私はバプティスト教会に行き、ベイカー氏(宣教師)の話を聞いた。彼はここ数年、ここで集会を開いている。
しかし、予想したとおり、C.(キャベンディッシュ)の人々は「シックスティーナーズ」ほど感受性が強いとは思えなかった。
月曜の夜、私は再び訪れ、ジャック・Lが一緒に帰宅した。私たちはとても陽気な散歩をした。
1897年6月3日(木曜日)
プリンスエドワード、ベルモント
土曜日の朝、私は家を出て5時頃ここに着いた。私はひどく疲れました。とても疲れていたので、眠ることができず、一晩中落ち着きなく翻弄されました。朝、私はその後、Simpson氏の家に行った。
月曜日の朝、私は(ベルモントの)学校に戻った。冬の間に鍵をなくしてしまったので
ドアも窓も釘付けにされ、誰も開けられないので、私たちは中に入ることができなかった。土砂降りの雨の中1時間近く待たされた。私はうんざりして、これが私の最後の学期であることに心から感謝した。やっとのことで窓をこじ開け、中に入って仕事に取り掛かった。
学校が終わってから、私はミスクーシュに向かった。一刻も早く出したい手紙があったのだ。木曜日まで郵便が来ないので、ミスクーシュまで歩いて行って、そこで投函することにした。ミスクーシュは5マイル離れているので、(往復では)10マイル歩かなければならないが私は元気に出発した。晴れた日の夕方、私は元気よく歩いたので7時半にここに戻ってきて、2時間半あまりで全行程を終えた。
しかし、もちろん、私はとても疲れていて、眠れないほどであった。
夜が明けることはないだろうと思った。水曜日の夕方、私は若い人たちと海岸に行き、帆を張ろうと思ったのだが、あまりにも荒れていました。昨夜はよく眠れたので、今日は自分らしく過ごせた。今日は野原を楽しく散策し、心の底から楽しめた。
1897年6月30日(水曜日)夜
ベルモント、P.E.アイランド
前回のエントリーの終わりにペンを置いてから、何年も経っているようです。その間に、その時から今に至るまで苦しみと恐怖の一世紀が広がっている。
"心臓の鼓動で時間を数える" 6月3日に書いた少女は、まるで芝生が飛び越えたかのように死んでいる。復活の可能性もなく、死んでしまった。私はその(元気な)少女が彼女であったとは。そして実際、私はそうではなかった。今、私が何であるか、誰であるかは知らない。ただ私が知っているのは、私が物事をひどく混乱させ、地球上で最も惨めな生き物であることだけは確かだ。すべて自分のせいで、死んでしまいたいくらいだ。
私は恐ろしい夢の中にいたようで、自分自身の個性を完全に失ってしまったようだ。完全にまるで未知の世界にいるようで、外見も内面も、すべてが絶望的に思える。
午前7時のモード・モンゴメリーではない。私はまるで突然現れたような気がする。遥か昔に生きた、この世界とまったく共通点のない別人であるかのような気がする。
新しい私。私は全く、完全に、惨めなほど小さな愚か者でした。今、そのすべてがわかった。手遅れになった今はっきりわかった。このような事態を招いた出来事や動機について、明晰な説明を書き残すことができるかどうかわからないがやってみよう。書き出せば、自分の力になるかもしれない。
話は戻るがエドウィン・シンプソンから届いた手紙には、私は条件付きで "いいえ" と答えた。冬の間、私はそのことについて何度も考えた。春に会えば、きっとまたこの問題が出てくるだろうと思ったからだ。考えれば考えるほど私は彼を愛しているわけはないのだ。
彼を愛してはいないけれど、愛せるかもしれないと思ったのだ。しかし、私は今まで誰も本気で愛したことがなかった。そしてそれを経験することなくここまで来てしまった。
私は、現実の世界でも小説の中でも、ある種の(破廉恥な)人々がするような恋愛は、自分にはできないと結論づけようとしていた。小説の中でしかできないような恋愛は、自分にはできないと思いかけていた。私はエドのことを考えすぎて、彼に夢の中の想像上の恋人のような、奇妙な非人間的愛情を感じるようになっていた。
彼は、私がこれまでに出会った多くの男性よりも、そして私と愛し合った誰よりも、知的な面でより親しみやすい人だった。これまで出会ったどの男性よりも、また、これまで私と愛し合ったどの男性よりも気さくな人だった。要するに彼との生活はとても満足のいくものだと思った。
満足できる存在だと思った。エドは賢くて学問のある職業を目指して勉強していた。その結果、彼の妻は良い社会的地位を得て、私の好みに合った人生を送ることができるだろう。彼には悪い癖や性格の悪さはない。なによりも私の孤独な人生において、このことはとても重要なことだった。彼は私を愛してくれていた。私は愛と保護が欲しかった。このところ私の前途に暗い影を落としていることがあった。前向きに考えていた。定まった家庭と地位という考えは、とても魅力的だった。
この春は体調がすぐれず、疲れやすく、気落ちしていた。冬の間、学校では大変な苦労をさせられた。だから私はこの生活をを抜け出すと約束されたものに手を伸ばしたくなった。
もちろん、エドウィン・シンプソンとの結婚を決めたことで、自分自身に多大な重圧をかけていることは承知していた。自分にとって大きな問題であることもわかっていた。私の仲間はこの結婚を好まないだろうと思っていた。
エドウィンがバプティストであることと、私のまた従兄弟であることが理由だ。これらのことは私にとっては大した問題ではなかったが、他の問題に比べればの方がよかったと思う。
しかし、祖父や祖母がこの結婚に反対することはわかっていた。祖父と祖母は、この結婚をエドが私のいとこであるかどうかと同じくらい、次のことを重大に考えるだろうと思った。
特に祖父は、彼がモハメッド人(アラブ人なのか)であることを病的なまでに嫌っており、親戚が結婚することを病的なまでに嫌っている。しかし結局のところ私は、彼が帰ってきたときに、私が彼を十分に気にかけることができると思えば、彼を受け入れることにしたのだ。(キリストがいた頃からキリスト教徒だったという中東人はいる。エドウィンも先祖の時からキリスト教徒であったろう。しかしスコットランド人ではないのだ)
前回書いた6月5日の土曜日の夜、サイモン・フレイザーが、エドが帰ってきたと言うのを聞いた。私は翌朝教会に行った。翌朝私はエドが家に着いたと聞いたので、何となくわくわくしながら教会に行った。私が教会に入った時、彼は壇上で日曜学校の生徒にに向かって演説していた。彼は元気そうで、よく話していた。"確かに"
私は彼の世話をするのは難しいことではないだろう」と思った。
教会が終わると、彼はやって来て握手をした。S(シンプソン)夫人は私に夕食に行くようにと言った。アルフとエドと私は、一緒に夕食に行った。エドと私は歩いている間、そして午後の間。大学の話やブラウニングの話など、その他いろいろな不燃性の話題(恋愛に引っ掛からないような話題)で盛り上がった。
夕方、私たちは皆、メソジスト教会まで歩いて行き、そこで私は夜を明かした。エドはとても気を使ってくれて、私は嬉しかった。とにかく私は彼のことを大切にできると確信した。火曜の夜、6月8日がやってきた――私にとって、2つの人生の境界線を示す日である。私は祈祷会に行き、エドは私と一緒に家まで歩いた(月明かりの美しい夜だった)。
私たちはいつものように、本や勉強の話をした。その夜、私は彼が何か話すとは思っていなかったので、フレイザーズ・レーン(フレイザーの家に入る横道)に入ったとき、私はすっかり驚かされた。
エドが突然こう言ったのだ、「去年の冬、私の手紙を受け取って驚いただろう? と突然言ったのだ。
そのとき、私は何が起こったのかがわかり、めまいがした。もしエドがあの時、何も言わずに......もし彼が2週間か1週間でも放置していたら......
そのころには、私は彼のことなど気にかけられないと悟り、私に降りかかったすべての事態を避けることができたはずだ。しかし彼は話し、私は自分の愚かさを封印した(変な浮気心は出さないわよと)。
私たちが何を話したか、はっきり覚えていない。私たちは昔の思い出を語り、私は私が彼を気にかけていて、(私が彼のことをお世話しなければならないのかなー)、と思っていたと言った。
彼は私にキスをし、"ありがとうモード" と言った。私達はそれから入って来た(フレイザーの家にか)。私は呆然としながら帽子とマントを脱いで、彼の希望で、私が身に着けていた花をエドに渡した。すべてが夢のようだった。
楽しいことも辛いことも、何の感情も意識しなかった。私たちは窓際に座り、6月の月光が下の湾を揺らめかしているのを眺めながら未来と過去について語り合った。彼が去ってから私は二階に上がり、長い間考え込んでいた。私は全く不幸だとは思わなかったが、幸せだとも思わなかった。結婚を約束した相手と別れたばかりの少女が感じるべきものではなかった。
次の晩は水曜日だった。私たちはロブスターの缶詰工場に集合し船で出かけた オリーブ・フレーザー メイ・キャンベル マリー・コンプトン、アルフ、バート、ソフィー、エドマンド、その他が参加した。もちろん、エドもいた。
その夜、私は彼の欠点を見ずにはいられなかった。それはとてもまぶしく、残念なことにそれは私が最も嫌いな欠点で、シンプソン家の多くの人に共通する欠点である。
シンプソン一族の多くに共通する欠点だ。彼はあまりに自意識過剰で、効果を上げるための言動をするのが好きで、はっきり言ってうぬぼれすぎだと思った。
しかし私は、自分自身が非常に不完全な生き物である以上、彼が完璧であると期待することはできないと思い直した。そのような小さな欠点ではなく、人格が重要なのだと自分に言い聞かせた。
しかし私はまだ、常識よりもっと高い法則があることに気づいていなかった。その法則とは、私が今まで全く無視してきた自然の本能の法則である。(気質が合わないのだ)
私たちは一緒に野原を歩いて帰った。エドは家に来て、遅くまでいた。私は無感情で淡々とした気持ちを持ち続けた。もちろ彼は私によくキスをした。
それらのキスは、他の女の子が私にキスをした場合と同じように、私の中に全く感情を起こさせなかった。彼が離れて行ったとき、私はこのことを反映して鈍くベッドに入ったた。彼は私の恋人だったとしても、私と一緒に座って非常に愚かなパフォーマンス(演技)だった。翌日は眠くて仕事にならなかった。
その後、2、3日、彼とは会わなかった。その後私はシンプソンさんのところで合唱の練習をした。
彼は私と一緒に歩いて帰ってきた。その夜私は、彼はなんと落ち着きのない神経質な人間なのだろうと思った。
その夜、私は彼の落ち着きのなさに驚いた。手も指も足も、絶えず動いているに違いない、トントン、ピクピク......。
私は疲れていたのだが、彼のこの習慣は私にとんでもなく大げさな影響を与えた。
彼がじっと座っていないと、私は叫ばなければならないような気がした。彼が去っていくとき、実際私は、まるで途方もない肉体的緊張を通り抜けたかのように疲れ果てていた。もちろん私たちは会話の中でいくつかの詳細を議論していた。
私たちは、婚約は長いものでなければならないので、少なくともすべての人にしばらくは秘密にしておくのが最善であると判断した。少なくともしばらくの間は、親しい友人以外には秘密にしておこうと決めた。そのため私はしばらくは婚約指輪をしないことにした。
エドの本当の計画を知ったとき、私は明らかに動揺した。私はてっきりエドは法律家か大学教授になるつもりだと考えていたし、エドの手紙でもそうだと思わせていた。しかし今、私は彼が聖職に就くつもりであることを知った。私はこのことをそれほど気にはしていなかった。
牧師夫人の生活はいろいろと大変だと思うが、もし彼が長老派や他の宗派であれば、それほど気にならなかっただろう。
徒党を組んだりバプテスト以外の宗派であれば、それほど気にならなかっただろう。しかしバプテスト派の牧師と結婚すると、浸礼による再洗礼を受けることになり、それは私の感情や伝統に全く反したものだった。
もちろんエドは、もし私が彼の職業選択にどうしようもない異議を唱えるなら、それをあきらめるだろうと言った。しかし彼は、そのようなあきらめは、自分にとって重大な「不都合」であることを隠そうとしなかった。
私は、このような重大な問題について、私には彼の選択に勝手な制約を加える権利はないと思った。そのようなことはとても自分勝手なことだと思った。だから私は最終的にそれを受け入れる、できるだけ誠意をもってエドにそう告げた。
6月の半ばになると、私は奇妙な非現実感から立ち直り始めていた。麻痺した私の感性は、残念なことに復活しつつあった。漠然とした疑問や恐怖、困惑が私を悩ませ始めた。特に6月17日の夜のことは、はっきりと覚えている。
エドの愛撫を嫌だと感じるようになった最初の夜だったからだ。それまでは無感情に受け入れていた。今までは無感情に受け入れていたのに、それが私を苛立たせるように思えた。身体的な反発を感じるようになった。私はこのことを自責し注意深く隠していた。
しかし、私の気持ちは、私を悩ませるだけでなく、心配させ始めていた。
6月17日木曜日の夜、私は学校が終わってからアラン・フレーザーの家に行った。私は疲れていて、物事全般に退屈していた。お茶を飲んだ後、オリーブと私は彼らの沼地に植物観察に行った。オリーブはベルモントの他の人々と同様に、エドと私に関する邪悪な好奇心に蝕まれ、多くのヒントを投げかけたが、私はそれを機械的に処理した。
私は、エドについてからかわれることが、私を悩ませていると知って、驚いた。彼は、そこで私に会うと約束し、日没とともにやってきた。私たちはそこで夜を過ごした。私は気だるく物憂げで、エドはいつも通り饒舌だった。彼はシンプソンの癖で話しすぎてしまうのだ。
私たちが家を出て暗い道を一緒に歩いたとき、彼はずっと話し続けていた。私がその声に飽きるまで話し続けた。家に着くと彼は入ってきた。私はといえば、突然氷のような恐怖にとらわれた。私は彼の抱擁とキスから身を引いた。私は文字通り、彼の接触に私のすべての神経を震わせる反発に怯えていた。
私は文字通り、彼のタッチが私のすべての神経を震わせる反発で恐怖した。それは私の中で眠っていた何かが突然目覚めたかのように思えた。
私はすべての私の人生の中で眠っていた何かが突然目覚め、反乱の情熱で私を振るわせていたかのように見えた。私の手かせ足かせに対する反抗の情熱で私を揺さぶったようだった。エドが立ち去ると、私は急いで二階に上がりベッドに飛び乗った。なんてことだ、私は何をしたのだろう。もしかして、私はひどい間違いを犯したのだろうか?
私はあの恐ろしい夜のことを思い出すとまだ震えてしまう。私の目からベールがはがれたような気がした。私は自分の目で完全な私の心を見て、そして私がそのようなことに耐えられないことを見た。
結婚を約束した人に触られただけなのに!
この恐ろしい訪問は、当時の私にはまったく不可解に思えた。今思えばあの夜の私の気持ちは、婚約した最初の夜から続いていた無意識のプロセスのクライマックスに過ぎなかったのだとはっきりとわかる。
今にして思えば、それは私の全本質が、偽りの束縛から突然反旗を翻したのである。私の本性が、その本性を知らないで、押し付けてきた偽りの束縛(旦那さんをお世話する物だよという束縛)から、突然反旗を翻したのである。
私の殉教が始まったのだ。それ以来私が受けなかった苦しみは何だったのか。(嫌と決めたらもう苦しまない)
次の日どうやって乗り切ったのか、私にはわからない。私は学校でも外でもひたすら働いた。それが唯一の救いだった(マリラの態度に類型がある)。考えることを、考えないようにするためだ。
夕方、セントラルのマッキノン少佐のところで合唱団の練習があった。行かねばならなかった。エドとフルトンは、今では私にとても礼儀正しい人だ。私を呼んだ。グラスの前で帽子をかぶりながら、私は不機嫌に思った。
エドはその夜、自分の婚約者の姿を特に誇らしく思っていないだろう、と。私といえば、これほど惨めな姿はないだろう。私はまるで死体のように青白く疲れた目の下には黒いクマがあり、死体のように青白い。頭がズキズキと痛んだ。
私たちはオリーブを呼びました。この小さな群衆の笑い声と会話が、私にある種の刺激を与えてくれた。私は少なくとも体裁を保つのに役立った。しかし、私が輝く星の下、エドと二人で、薄暗くシブい道を歩いて帰っている自分に気がついた。薄暗く、音も静かなトウヒの道を、エドと二人で歩いて帰ると、憂鬱な気分が戻ってきた。彼はそれに気づかないのだろうかと思った。しかし彼はそれに気づかず、ただ延々と話し続けた。
家に着くと、私たちは窓際に座った。エドは私に腕をまわして私にキスをした。突然、私はそのキスが私を耐え難いほど焦がしたように感じた。
恥ずかしかった。彼が再び頭を曲げたとき、私は急に席を立ち、彼の腕を押しのけた。もし彼がその瞬間にもう一度キスをしていたら、世界中のすべての決心はできませんでした。(どんなことだろうともうイヤーッとなったろう)
私は彼から離れた。彼はこれを単に私の一部でコケティッシュ(可憐)なビット(反応)であると取った。彼はこれを私のちょっとしたお世辞だと思い、背もたれに寄りかかり、訝しげな笑みを浮かべて私を見ていた。しばらくして、私は自制心を取り戻した。
エドは全く疑っていなかった。私はそのことに感謝した。もし彼が疑うようなことがあれば、それは私にとって耐え難い屈辱であるように思えた。(体裁もあるのでこの時点では私が翻意したなどと思われないように)
その夜、彼はその夜私がとても静かだと思いそう言ったが、それは長い散歩の疲れによるものだった。しかし彼は私が疲れていると思ったからと言って滞在を控えようとはしなかった。私は彼は決して帰らないだろうと思った。彼はまだ残っていて、私たちの将来のことを話し続けた。これ以上の拷問はないだろう。
私は言葉の端々に魂を揺さぶられたが(やめてーやめてーと)、自分をしっかりと持っていた。
私は再び私の冷たい、無反応の顔を彼のキスから回しませんでしたが、彼がやっと行ったとき、私は息をひそめて「神よ、お助けください」と言いながら自分の部屋へ上がった。
どうにかして、私は土曜と日曜を乗り切った。私はシンプソン氏の家に行ったが、その夜は雨に降られた。その日、私はエドウィン・シンプソンを愛していないだけでなく、決して愛せないという最終的な確信を得ました。
月曜日の朝は雨で、エドが私を学校まで送ってくれた。彼のそばにいる青白い少女の脳裏にどんな思いが渦巻いているのか、彼は夢にも思っていなかった。エドは他のシンプソンズと同じようにエドもまた、あまり知覚がない(繊細な神経などない)。彼は、自分のことを話すのに精一杯で他人の気分や態度に気がつかない人だ。その点、私はありがたかった。
無理にアニメーションを作る(喜んでいる態度をする)必要がなくなったからだ。私はその時この関係を壊そうなどとは考えもしなかった。(世間体を崩すなど不敬だ)

さあモードぼくたちの将来についてじっくりとじっくりと話し合おうではないか
婚約――するのが怖かった。フルトンの非常識ともいえる行動を思い出しながら、エドがどうなのか、そのようなことが彼にどんな影響を与えるのか、あえて推測する必要はなかった。
推測する勇気がなかった。私はやがて彼に対する身体的嫌悪感を克服し(この人の体質はイヤ)、少なくとも満足できるようになるという希望にしがみついた。
少なくとも満足はしていた。幸せはもう望めない。 婚約してわずか2週間で、このような心境になるとは!? 確かに。しかし私にはそれが理解できないのだ。
(幸せな未来を)見ることができない。ただ悲劇を見るだけであり、感じるだけである(作家に没頭できない未来は不自由であろう)。
その雨の月曜日の次の火曜日は女王(ビクトリア女王)の誕生日で休日だった。 メイキャンベルはカーテン島へのピクニックを計画していた。ピクニックの参加者は
ライルズ家、シンプソン家、キャンベル家、フレイザーズ家、そして私だ。私たちは9時に出航した。その日は晴天だったが風が強く吹いていてとてもエキサイティングな船旅になった。その波の上や水しぶきをかき分けて進む爽快な運動と肉体的な喜びが私は一種の偽りの活力を得た。結局のところ......私は病的だったのかもしれない。
カーテン島に着くと、私たちは森を抜けて反対側へと歩き出した。 ボロボロになって出てきた(藪を抜けてきたので)。夕食後エドは私を草の生えた岬に連れて行き、私たちはそこに座って長い間話をした。 私は本や勉強のことに必死になって長い話をした。 個人的な要素には耐えられなかったからだ。もし結婚が知的な話題についての一連の会話だけを意味するのなら、私はエドとうまく結婚できただろう。 彼とそのような話題で話すのは楽しい。 しかし私たちのおしゃべりが、私の意に反して、個人的な話題に傾きかけたときタイミングよく 雷雨がやってきて、私たちは小さなロブスターの小屋に避難せざるをえなくなった。 そのあと2時間ほど雨が降り続き、私たちは泥まみれ、湿気だらけ、ベトベトの状態になった。帰路につく頃には風も弱まり帰路に着くと風は止み、湾はガラスのように(平らに)なった。
私には帰りの船旅が長く感じられた。私は憂鬱のどん底にあり、ほとんど倒れそうな状態だった。 私の容貌が悲惨ですよと聞かれた。私は死ぬほど疲れていると答えるしかなかった。エドはそのことを気にかけてくれ、しかしそれでも彼は私に、一緒に祈りの集いに行こうと言った。
私はエドにサマーサイドまで一緒に歩こうと言われたらそうするのと同じように。私は彼が私に望むことはすべてしなければならないと思った(どんな無謀な事でも聞いてやらねばならない)。
呼吸をするたびに、自分がしている(心にもない)悪事を少しでも償うために、彼の望むことはすべてしなければならないと思った。
私はエドに不義理をしたいわけではない。彼が善良で容姿端麗で賢いことは認める。 もし私が彼を愛していたら、彼の欠点や不完全さに気づかなかったと思う。
少なくともそれが私に厳しく突き刺さることはないだろう。しかし私は彼を愛しておらず、時々、私はすぐに彼を嫌いになりそうだ。私が自分を憎み軽蔑するのも不思議ではない。己を憎むのも不思議ではない。
また休めるかしら? いつも疲れているような気がする。昔のように毎日の仕事をこなすのは大変なことだ。私はそれが嫌なのだ。私はそれらに興味を持つことができず、機械的にこなすだけだ。
私の周りの外界は公平である、とても公平である。しかし私はその美しさには何の関心もない。私の魂と自然との間にベールがかかっているようだ。これは最も耐え難いことだ(私は夢が見られなくなった)。
耐えなければならない。 水曜日と木曜日もほとんど同じように過ぎていった。夕方エドがが来た。なんという悪夢だろう 耐えようと思ったのは一つだけ。

容貌が悲惨ですよ
それは、少なくともしばらくの間は(エドと会うのも)これが最後だろうということだった。エドが土曜日にノバスコシアに行くので、その前に私はベルモントを離れることになる。これが私の唯一の慰めだった。彼が私たちの別れが近いことを嘆きながらも、私がどんなにそれを切望していたかを知らないのだ。彼は私の気持ちを自分の感情で判断し、それを当然のこととして受け止めていたのだ。
私は常に誇り高い女だ。私の心境を推測して嘲笑したり、憐れんだりしたら、私は死んでしまうだろう。誰もそんなことはしていないことを私は知っている。
この家の人々には、いつも通りの私が、より静かで、より重々しく見えたことだろう。(平静を装う)
社交界でも私はいつもの私であった。私は笑い、冗談を言い、他愛のない話をしてきた。些細なことを話したり、かじる狐(おそらく心の動揺)にプライドという外套をかぶせたりしてきた。スパルタの少年と同じように、にこやかに、誇らしげに。
その夜の翌日、私は学校の試験(教員の仕事が進んでいるかを見る試験)を受けた。私はほとんど何もしなかった。無関心に生徒たちを見送った。それが最後だからということは全く気にしなかった。私はここの生徒が好きではなかったが、たとえ好きであったとしても、その時だけは別れを感じなかっただろう。手足が引きちぎられるようなものだ。
もちろん、中には好きな子もいたが、大半はとても好きになれない子たちだった。とても愛せない、粗野で、無知で、怠惰な子供たちだった。長い、そして悔いのない別れだ。
その夜、私たちはキャンベル氏の家で開かれた小さなパーティーに招待された。私たちは愚かな時間を過ごした。ほとんどの客は退屈で疲れているように見えた。私自身はといえば熱狂的な歓喜に包まれた。私の目は爛々と輝き、頬は熱く紅潮していた。(わあしばらくエドから離れられる)エドは、ソフィーに頼まれて帰り道、私の体を曲げて(私の帰り道を変更させて)、シンプソン氏の家で一夜を過ごした。こんなに遅くに歩いて帰るには遠すぎるからだ。
エドはこんなに美しい私を見たことがない。その夜の私の顔をいつまでも覚えていると囁いた。このような恋人のようなお世辞は、本来ならうれしいこと。しかし、私は冷や冷やし、震え上がった。悶絶して彼の腕から離れました。
土曜の朝、私は元気がなく俯き加減で起き上がり、前の晩の熱く反抗的な情熱は、くすんだ白い灰になり果てていた。私が出かけると、海岸に行くはずのエドがキャナリーロードまで一緒に歩いてきて、そこで立ち止まって別れを告げた。
そこで立ち止まってさよならを言った。私は受け身で彼に手を差し出し、冷たく顔を持ち上げて彼の別れのキスを待った。別れのキスをした。彼は海岸沿いの道を歩きながら、「さようなら、私の愛しい人よ」と言った。
私は安堵の息をついて歩き出した。なんという安堵感だろう。そしてなんと恐ろしいことだ。その夜私はミシュランに乗り、アルベルトンに向かった。教師大会に出席し、ネッティ・モンゴメリーを訪ねるためだ。私はこの訪問に何の喜びも感じなかった。何に対しても喜びを感じる力を失ってしまったようだ。
汽車に乗った私の前には、マッキンタイアとトロウズデールという2人の教師が座っていた。二人とも、エドがパーク・コーナーに通っていたころ、そこで教えていたのだが、不思議なことに、二人はエドについて話し合っていた。彼らは、後ろにいる私に気づかなかったか、気づいても、私が彼らの会話に特別な関心を抱いているとは思わなかっただろう。
彼らはエドが好きではなかった。彼らはエドが嫌いなのは明らかで、彼のことをあれこれと言いふらした。
私でさえも腹が立って、彼の擁護のために彼らに向かって飛び出さずにはいられなかった。
そして私は(そうした場合の)、彼らの驚きと憤りの心象風景を思い浮かべて惨めに笑ってしまった。
私がそんなことをしたら、きっと困るでしょう。しかし私の怒りに反して、彼らがエドに言ったことは本当だった。
エドが賢いのは事実だが......」というのが、彼らの言葉の本質のような気がした。彼はほとんどの人に、私にとまったく同じように影響を与えるようだ。
ネッティが列車で出迎えてくれて、私は今日の午後までそこにいた。私はとても疲れを感じていたのだが、このような陽気な社会に身を置くと、憂鬱な気分も幾分かは晴れた。
月曜日の夕方、ネッティーと彼女の父親と私はドライブに出かけた。馬が驚いて逃げ出し、私たち全員を投げ出した。幸いなことに私たちは誰も大きい怪我をしなかった。ネティは頬を少し切った程度で済んだが、私はショックを受け、まだ完全に回復していない。
今日、3時半にアルバートンを出発したのだが、ミスクーシュまでの道のりが大変で、ずっと頭が痛かった。ミスクーシュでようやく降りたとき、私はただ座って子供じみて泣きたい気分だったと断言します。
しかし、帽子がそうさせない。ベルモントまでの5マイルを気ままに歩き始めた。やがて雨が降り出し、私はその中をひたすら歩いた。途中ジョンとネッティ・ライルに追い越され、フレイザーの家の門まで送ってもらった。
私はここに到着すると、以前のような憂鬱な気分が戻ってきた。この場所は私が一歩足を踏み入れた途端、気分が悪くなるのだ。玄関に入った途端に気分が悪くなる。
人々はとても奇妙で、環境はとても粗く、荒々しく、今まさに張りつめている私の性質のあらゆる部分を刺激する。ちょうど今、神経過敏になっているところだ。
私は2階の自分の部屋に行き、ベッドに身を投げ出して思い切り泣いた。その涙はこの恐ろしい時間の中で初めて流した涙だった。
私は泣いて、泣いて、疲れ果ててしまったが、精神的な安堵感は言葉にならないほどでした。私は脳から何かが取り除かれたような気がして、初めてまたペンを取り、この日記を書くことができるようになった。
私は土曜日に家に帰る。私はこの貧しい古い部屋に座っている。私はこの部屋を離れるのが残念でならない。ベルモントで唯一、ここ(私が借りていた部屋)を離れるのが残念だ。
古い部屋を去るのはいつも残念だ。人が眠り夢を見、嘆き、喜ぶ部屋はその過程と切り離せない関係になり、その部屋独自の人格を獲得するのだ。この部屋は決してきれいでも可憐でもないが、いつも私の隠れ家であった。
ベルモントで唯一、一人静かに自分の魂に浸ることのできる場所だ。私の魂が宿り、世間を忘れられる場所であった。そして今私はそこを去り、別の場所に行かなければならない。今までいくつの部屋を出てきたことか。まだあるのだろうか
私は家にいたいと思う。休みたい、休みたい、休みたい 今の私には全く無理だ。冷静沈着に考えることができない。合理的な判断ができない。私の精神的なバランスは、あまりにも無残に崩れ去り、正常な態勢を容易に回復することができない。
自分の状況のことを考えると、自己嫌悪に陥ってしまい言葉にならない。私は自己卑下と屈辱の溝にいる。自己卑下と屈辱と自責の念とが、自分が招いた運命への抗いがたい反発と混じり合っている。
私は今、自分がどこで最大の過ちを犯したのか、はっきりと分かっている。私の最大の過ちは それは真の愛がなければ、どんな親密な絆も胆汁(苦い)になることを定めた法則を無視したことだ。
私が無知で罪を犯したことは小さな慰めであり、何の助けにもならない。この3週間を振り返ってみると、よくもまあ気が狂わずに生きてこられたものだと思う。(神経質なのだ)
身体的な影響ははっきりと出ている。私は痩せて顔色が悪く、目がうつろで神経質で。精神的、感情的な損害については、誰が判断できるだろうか。
ああ、どうしたらいいのだろう。そしてアドバイスや助けを求めることができる生身の人間もいない。
私は一人でこの怪事件を解決しなければならない 母が生きていれば!
エドが何も疑わず、私の態度の変化に気づかなかったのは不思議なことだ。本当に、「神々が滅ぼそうとする者は、まず盲目にする」のです。
でも、私の場合盲目の日々は終わったのだ。その光景は、私の魂の視界を永遠に奪うかもしれないものである。この春まで、私はかなり幸せな人生を送ってきた。私は若く、野心的であったので、人生は公平で有望に見えた。今、すべてが変わり、暗くなっている。
今夜、エドは遠く離れていて、私のことを愛おしく思っていることだろう。哀れな私を!そして私は?鏡に映る自分の顔を殴ることもできる。
自分の愚かさを罰するために、惜しげもなく肩を鞭打つことができる。それは肉体的な苦痛を与えることで、精神的な苦痛を和らげることができるだろう。
私は時々ペンを捨て、両手を握りしめて部屋の中を荒々しく歩き回る。外では六月の湿った匂いのする夕方の雨が屋根に降っている。I畜舎の暗がりの中で、男たちが呼び合う声がする。遠くには、カーテンの隙間から雨とたそがれのカーテンの向こうに、湾が灰色に見えている。
朝、私は服を着て髪を整え、笑顔で挨拶をして、今回の訪問について話し、ビジネスライクに出発の準備をする。
しかし、この貴重な小一時間の孤独の中で、私は仮面を捨て、自分の裸の魂を見つめることができる。嘲笑うことはない。私は乱暴で気が散るような文章を書いていることは承知している。でも、自分の惨めさを言葉にするととても安心する。
私はとても疲れている。私が軽快で、ゲイで(元気で)、野心的だったのは、もう100年も前のことのようだ。
野心的! 笑っていられたのに! 今、私の野心はどこにあるのだろう? その言葉は
何を意味するのだろうか? 野心を持つとはどういうことか? 人生が目の前にあると感じることだ。
自分の名前を成功の文字で刻むことができる、公正な、書かれることのない白いページ(未来への希望)が目の前にあると感じるのは? これからの年月、自分には王冠を勝ち取る願いと力があると感じられること?
足元に大金を積んでくるのを感じられるか? 私はかつてそう感じることを願った。
私はまた床を歩き回った、いつまでもじっとしていることができない。外はもう暗いし、雨は幽霊の指先のように窓ガラスを叩いて奇妙なメロディーを奏でている。ああ、他の人たちもこんな風に苦しんでいるのだろうか。もしそうだとしたら、どうやって生きられるのだろう。
このまま家(キャベンディッシュ)に帰ったら、また平穏な生活が送れるかもしれない。少女時代の枕にもう一度頭を乗せれば、その呪文が私を静寂の道へと誘い、荒波の上で「安らかに」とつぶやくかもしれない。
今夜はそのような眠りはない。私は暗闇の中に横たわり、何時間もその中を眺めている。灰色の夜明けが湾を覆うとき、私は退屈で重い眠りに落ちるだろう。思考も感情も完全に疲弊し、黄金の朝に再び目覚める......。美と喜びの世界では、私は不幸の黒く見苦しいしみに過ぎないのだと感じている。私は寒く、疲れ、消耗しているのだ

のちのモンゴメリ、リースクデールにて
落ち着いたのか、もうこわばった顔はしていない
1897年10月7日
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
"収穫が終わり 夏が去った"(アンの青春で言われた言葉)
ついにこの日記を書き上げた。何ヶ月も放置していたのだ。書けなかったからだ。もう夏も終わりだ。10月、秋になった。霞がかかり、紫色に染まり、刺激的で芳醇な空気が漂い、素晴らしい夕日が沈む、楽しい秋の一日だ。
そして、稀に見る黄金の薄明と、銀色に浮かぶ月夜が続く。カエデやシラカバは深紅と黄金に輝き、野原はその余韻にひたる。しかし今は秋で、すべてが美しいが、それは腐敗の美である。朽ちていく美しさ、終わりの哀しみに満ちた美しさだ。
今年の夏は長かったようで短かった。私は幸せでも平穏でもなかった。苦しみは絶えなかったが、それは私に良い結果をもたらした。私はある面では大きく成長し、物事の本質に大きく近づいたと思う。
私は去年の春まで少女だったが、今は女になり少女時代が永遠に終わったと痛感している。
私は人生の表面的な喜劇の下にある悲劇を見ることを学んだ。私は人間らしくなった。もはや孤立した利己的な単位ではなく、自分と同族が一体であると感じるようになった。自分の人生と他人の人生をより深く見ることができるようになった。私は人生を理解し始めた。
ある人が「生きることの無限の悲しみ」と呼んだものを実感し、私たち一人ひとりがどれだけそれを、そして、その悲しみを増大させたり軽減させたりする力が、私たち一人ひとりにどれだけあるのかを理解するようになった。
私は人は自分のために生きているのではない」ということが、ようやくわかった。私は7月1日にベルモントを後にし、何の後悔もなく帰宅した。私はベルモントが嫌いだった
あの場所は辛かった。学校が決まらないのでこの夏はずっと家にいた。学校はいつも大変なのだよ、自分の努力だけが頼りだから。祖父はいつも私が教えることに反対している。私のためというわけではなく、昔から教師というものに対して不条理な偏見を持っているからだ。
というのも、祖父は教師という職業に不条理な偏見を抱いていて、その昔ここに寄宿していた教師が祖父と喧嘩して出て行ったことがあるからだ。
彼女(イジー・ロビンソン)は憎むべき存在だったが、しかし、その喧嘩の原因は彼女だけでなく、彼自身にもあったのだ。この夏彼(爺は)は一度だけ私にクリークの店に入るよう勧めたが(店番募集しとったぞと)、私はそんなことはしない。彼は(学校に勤める為に)評議員を訪ねるための馬を持たせてくれないので、手紙に頼らざるを得ないのだ。
教師はいくらでもいるし、個人的に応募するのがいちばん有利なのだが。しかしついにローワーベデック校を手に入れ、2週間後にはそこを任されることになった。
この夏、キャベンディッシュはとても静かだった。リアンダーおじさん一家が来て1ヶ月間滞在した。チェスリー・クラークとジャック・レアードの二人は西に行ったので、私はとても寂しい。
この夏、ローラから一度だけ連絡があった。私がその手紙を開けると、そこには小さな包みが入っていて、そこには糸が切れそうなほど(縁が鋭くなっていたのだろう)磨り減った小さな金の指輪があった。その指輪は6年前に私がウィルにあげたもので、彼が死ぬまでずっと身につけていたものだった。私はもう一度それを指にはめて、これまでのすべての変化、来たるべきものと来たるべきもののことを考えこの指輪を最後につけて以来、来ては消え、来ては消えを繰り返してきたすべての変化を思い浮かべた。それはまるで金のつながりのように思えた。
私と失われた自分の間、現在と過去の間。かわいそうな指輪。私はあの懐かしい日々を思い出しながら、いつも身に着けていることだろう。その輪は永遠と永遠の友情の象徴である。
きっと、ここでお互いをよく知り合った人たちは 来世でも再会できるだろう。リアンダーおじさんの2番目の妻、アニーおばさんが、昔、私が12歳のときにくれた指輪だ。ウィルに渡すまで私の指から外れることはなかったし、擦り切れるまで二度と外れることはないだろう。アニー叔母さんが少女時代に身に着けていたものだからとても古いものなのだ。
この夏、私たちが行った唯一の社交行事は祈祷会だった。 忠実な古い習慣である。しかし今日の祈祷会は以前とは全く異なっている。 しかしそれは、「クリスチャン・エンデバー・ソサエティ」に進化しているのだ。私はこの変化を肯定することはできない。 今までの人生を振り返ってみると、私はかなり特殊な霊的体験をしてきたと思う。 私は「宗教家」ではないが。 霊的なもの、永遠なもの」に対する深い好奇心を持ち続けてきた。私はそれを知りたいのだ。 だから、いつも信条や宗教のことを調べたり、死んだり、生きたりすることの中に、どのような真理が埋まっているのかを知りたいと思うのだ。 不滅の真理が埋もれているかもしれない。私は幼い頃、つまり8歳か9歳の頃、このようなことを深く考えるようになり、多くの苦しい精神的葛藤を経験したものだ。
そのようなことは、周りの人たちには一言も言えなかった。私の神学は非常に原始的なもので、すべてを文字通りに受け止めていた。天国は黄金の家と街路がある街だと思っていた。
ハープや王冠を持って歩き回り、いつも賛美歌を歌い、金色の家や通りのある街だと思っていた。 讃美歌を歌いながら歩く、「終わりのない安息日」のような場所だと思っていた。しかし私は
それはひどく退屈なことだろうと思わずにはいられなかった。地上での日曜日は終わりがないように思えたが、では本当に終わりのない日曜日はどうだろう? しかし私はこうも思ったのだ。これはとても邪悪なことだとも思った。
天国には何の魅力も感じないのに。でもとにかく地獄よりはましだろう。 火と硫黄の湖で、悪魔とその天使が取り憑いていると信じていた地獄よりはましだろう。
その天使たちが取り憑いているものだと暗黙のうちに信じていたのだ。
天国は青空の向こう側に広がっているという漠然としたイメージはあったが 地獄は南東にあるような気がした。 南東に私はネルにひどく怯え、その恐怖に駆られてしばしば
クリスチャンになろう」と必死になっていた。 苦い季節もあった。10歳くらいのときに、カトリック教会が唯一の教会だと思い込んでしまったのを覚えている。
10歳くらいのときに、カトリック教会だけが正しくて、その外側にいる者はすべて異端者であり、刑罰の対象になるのだと思い込んでしまったのだ。
このような考えを持つようになったのは、「カトリック世界」という新聞の見本がきっかけだった。 郵便で届けられた "カトリック世界"
という新聞の見本で知ったのだ。 その内容はあまりにも独断的で、権威あるものとして私に印象づけた。そのために私はどんなに苦しんだことだろう。今にして思えば滑稽でもあり、情けなくもある。しかしその当時はとても現実的で、どうしようもないことだった。そして私はとても惨めに孤独で、助けを求めることができる人は誰もいなかった。
(誰かに聞いても)その時私は笑われるか、せいぜい独断的なことを言われるだけで、何の役にも立たなかっただろう。沈黙と秘密の中で 自分の戦いに挑み、泥沼の中でもがくしかなかった。
どうにかこうにか、母なる教会に対する苦手意識を克服していったのだが、しかしどうしようもなく別の問題につまずくことになる。学校の中でバプテスト派と長老派の女の子たち、つまり「大きな女の子」たちは、いつも教義上の点で、特に次のように論争していた。
バプテスマ(洗礼)を受けた後、バプテスマだけが正しいのではないかと心配になり、バプテスマを受けなければ必ず「失われる」(お前の魂は)のではないかと思うようになった。
私は眠れぬ夜の枕元でこのことを心配し(子供のころは思い込みが激しかったのであろう)何週間も眠れぬ枕で悩み、自分自身と激しく議論した。 しかし、ついに私はこの影からも抜け出した。
夏には良心の呵責に悩まされることはなかったが、時々――いつも冬に――「罪の確信にとらわれる」ことがあった。
私は「罪の確信に落ちた」、つまり地獄のことを思い出して怖くなったのだ。 泣き、祈り、「良い人」になろうと必死に決意した。 絵本よりも聖書を読むのが好きで、教会で疲れないように、つまり「退屈」しないように、そして日曜日を嫌いにならないように。 そのうえ、幼い本能を100回も抑制し、否定することを厳しく実践するのだ。 そのうえ、幼い本能を100回くらい否定するようなこともしていた。
例えば、テーブルセッティングの時、良心的にあるナイフを自分のために使うと思っていた。去年の冬、私は初めて「アフリカの農場の物語」を読んだ。この作家は、まさにそのような子供時代の体験を綴っていた。その時私は、私たちは朝食のとき、割れたコーヒーカップを意識的に自分たちのために置いた」という一文に、私は身を乗り出して笑ってしまった。まるで、思いがけず自分の顔が
まるで、鏡から自分の顔を覗き込んでいるようだった。このボーア人の少女は、何千キロも離れた南アフリカに住んでいて 私とまったく同じ経験をしたのだ(自分を抑制するためにいつも決まったナイフを使うというようなやり方)。
そうなんだ。本当に私たちは想像しているほどお互いに違ってはいないのだ。
話は戻るが、この病気は数週間で治るが、 次の発作が起きるまで、また「邪悪」と「無関心」に戻ってしまうのだ。 私が成長するにつれて、このようなことはすべてなくなった。そんなとき、町でB・フェイ・ミルズ(今は亡き人物。
ミルズ、彼はその後、ユニテリアンに移ってしまったが)が、それをひっくり返した。 何がきっかけで「教会に入る」ことになったのかよくわからない。(社会の)空気全体が
その影響に抗うのは難しい。 特に私のように非常に敏感で感受性の強い者は、その影響に抵抗するのは難しい。 それから、メアリー・Cは本当に「カミングアウト」したがっていて、私がしない限りカミングアウトしない(本心を吐露しない)のだ。
だから彼女のためでもあったし、私がうんざりしていたせいでもあった。 リバイバリスト(福音派になれと演説する人)がやってくるたびに催促され、説教され、うんざりしていたので私は降伏した。
「カミングアウト」(心境を吐露した)したのです。私はそれが間違いだったと思う。「教会に入る」ということは、ある教えに同意することであり、私はそれを受け入れることができなかったのだ。
その教えを暗黙のうちに信じなくなったのはいつなのか思い出せない。 その過程はとても緩やかなものだった。文字どおりの火と硫黄でできた古い地獄を信じるようになったのはそのときからだ。
それを最初に信じ、他のものは、成長した殻のように、いとも簡単に捨て去られたように思えた。 ある日、それが消えて久しいことに気がつくまで、私はそのことに気がつかなかった。
私はまだ、手放した信念の代わりになるような、実用的な信念を打ち立てていない。 まだない。おそらくそれはやがてやってくるだろ。こういうものは、他のものと同じように、成長しなければならない。
この夏、私は物語をたくさん書いたし、いくつかの作品は採用された。詩はマンゼーに採用された。この雑誌は良い雑誌なのでとても励みになる。 昨日はハティ・ゴードンの古い手紙を読み返した。どんなに会いたいか。彼女がこの学校で教えていた頃私たちはどんなに油まみれだったことだろう。学校は変わってしまったし、昔の生徒もほとんどいなくなった。今そこに通う子供たちは
私たちの楽しみの半分も味わえないだろう。 しかしそれ以上に多くのことを学んでいることは間違いない。
最近、新しい本を何冊か読んだ。"The Gates Ajar"(狭き門)にはかなり興味を持った。 著者の天国についての考え方は参考になるし合理的なものだと思う。この著者の考えでは、私たちはより高度な発達を遂げ(人間がさらに進化して)、あらゆる障害や束縛から解放されながら
その結果地上のあらゆる障害や束縛から解放される。 私たちの願望は、あらゆる助けや妨げを受けながらも、ますますそれに向かって発展していくものだと考えている。これは楽しい考えで、私はそれをしっかりと信じたいのだ。
信じたいという気持ちだけでは十分ではない。 「世間知らずの女のラブレター』も新しい本で、私にとっては新しい本だった。 この本は、『ゲート』とは全く違う。この本は地上のものであり地上の情念を扱っている。
この本は人間の多面的な性質の一面に強く訴えかけてくる。それはすべての人生、すべての生活が多かれ少なかれそうであるように人生に忠実であり、それゆえに悲しく悲劇的である。
しかしある種の人生は、他の人生よりも本質的に悲劇的であるように思われ、私は自分の人生がそのようなものであることを恐れている。 現在の私の見通しは実に陰鬱で、束縛され、狭められている。
手紙から引用すると、「あらゆる可能性の扉を閉ざされた囚人のような気分だ」。 9月に展覧会に行った。もちろんメアリー叔母さんの家に泊まった。 女友達の陽気な人付き合いの中で、しばらくの間自分の心配事を忘れた。 不健全な考え事や思索を忘れることができた。 この夏私の生活は不健全なものだった。この夏はあまりにも多くのことを本や幻影や夢で囲まれ、世間的な人間関係が十分でなかった。 それは あまりにも自己中心的で分析的だった。 メアリー・Cも来ていて、一緒に楽しい時間を過ごした。私たちはある晩オペラハウスに行き「カインの呪い」を観た。 アマチュアの下手な演技だ。しかし最後の「虹の踊り」は、少なくとも私の目には本当に美しかった。 私は色彩をこよなく愛している。私にとっての色彩は、音楽がその信奉者にとってのものであるかのようだ。
ある日、メアリーと私はマクロード夫人に会いに行った。ホテルは今は空家なので、メアリーと私はマクロード夫人の鍵を借りて一通り見て回った。今は空っぽのホテルだが、
コミカルな思い出がたくさん詰まっている。あの古い家では確かにトラブルや苦難があった。 しかし時の流れに身を任せると、それは単なる愉快な出来事に過ぎなくなる。
そして私たちはそこでも楽しい時を過ごした。
ジャック・ウィアーとフローリーが使っていた古い応接間を探検した ジャック・ウィアーとフローリーが よく出入りした居間も、勉強した古い居間も探検した。マクミラン母さんの怒りに触れず階段を駆け上った。そして最後に私たちの古い部屋を探検した。
書いて、読んで、友人をもてなし、不満を語り合った場所だ。 しかしそれはもう過去のことで、屋根の上の小さなコロニーは(友人たち)遠く離れた場所に散らばってしまった。
フローリーはジャックと結婚し町に住んでいる。哀れな「アイレック」はアメリカのどこかにいるし、「メアリー・マクミラン」もそうだ。 平和のためにこの二人が100マイル以内にいないことを祈るばかりだ。
バーティ・ベルは西部に、スチュワート・シンプソンはマギルに、ジム・スティーブンソンはチャイニーズにいます。 マクミラン夫人はスタンレーにいる。
マクマホン夫妻はどこにいるか知っている。ノーマンとメアリーは教師で、私はと言えば......いや、流されているのだ。 運命に翻弄され、嘲笑されているのだ。
1898年
ローワーベデック、P.E.アイランド
1898年1月22日
新年以来、この日記を書くつもりでいたのだが、しかし残念なことに、地獄への道は舗装されているというが、私は最近その舗装に少なからず貢献しているのではないかと思う(私は偽りの道を進んでいるのだ)。しかし、私は今晩を「地獄の道」に捧げようと思う。
今晩は、もっぱら「ジャーナリズム」(日記書き)に専念するつもりだ。前回書いたとき、私は家にいて、夢を見、分析し、不健全に沈思黙考していた。そしてベデック(ここローアー・べディック)にやってきて、それまでとは正反対の生活をしている自分に気がついた。その反動(気分転換)は必要であり、健全なものであることが証明された。でも、もし今の生活が長く続いたら、きっとこのままでは、前者よりもさらに悲惨な結果をもたらすと私は確信している。
私は、エドウィン・シンプソンとの惨めな出来事について、十分に告白する(この日記に告白する)つもりだ。前回のエントリーでは、そのことについて何も言えなかった。
そのことについて言及することさえ、生傷に触れるような痛みを伴うからです。しかし今は多少落ち着いている。というわけで、私の惨めな気持ちを冷静に書き出したらどうなるのか見てみよう。
この夏、私がどのように苦しんだかを説明するのは無駄だろう。私は知っていた。エドウィン・シンプソンと結婚する気にはなれないとわかっていたのに彼に言い出せずにいました
自分の臆病さが嫌で嫌でたまらなかったけど克服できなかった。
エドは定期的に手紙をくれたが、そのたびに私は自分の絆をより憎むようになった......。私はその日が来るのを恐れたが、手紙を読み終えたとき、熱い安堵の息をついた。返事を書くのもまた絶妙な苦痛だった。
悶々としていた。まあ、「ラブレター」は書かなかった。しかし私は友人として書こうとしたし、エドはその不足に気づかなかったし、気づいてもコメントしなかった。
私は、彼のために何か不親切なことを言うのは嫌だ。でもこれは文字通りの真実なのです。彼を知る者は誰も否定しない文字通りの真実である。
エドが愛情を注いだ女性は、最高に幸せでうっとりしているに違いないと、冷静に確信していることは、彼を知る誰もが否定できない事実である(うぬぼれ男ではないか)。
ベルモントでの夜の会話で、彼はこの確信を無意識のうちに何度も繰り返していた。私が帰宅して間もなく、エドはキャベンディッシュを訪れていた。日曜日の午後、アルフと一緒に私たちの家に来て、お茶を飲んだ。またもや恐ろしいほどの反発を覚えた。
私は30分ほどで失礼したのを覚えている。彼らが来てから30分後に失礼して、自分の部屋に駆け上がり、そのまま身を投げたのを覚えている。床に突っ伏して、何度も何度もつぶやいたわ。
"絶対に、絶対に、絶対に結婚できない" とね。その暴言が私を救ってくれた。そして落ち着いてお茶を飲み、服を着て、教会に行くことができたのだ。それ以来木曜日の夜、クリスチャン・エンデバーに行くまでエドに会わなかった。彼は降りてきて(家にやってきたという事)、集会の後、私たちはドライブに出かけた。それはひどいものだった。
翌日、エドはミラマーチに出かけたが、戻ってくると以前にも増してひどい状態になっていた。 彼の私に対する態度は、すぐにキャベンディッシュでゴシップを耳にするようになった。
彼はキャベンディッシュに大勢のいとこを従えていて、そのほとんどが私を嫌っている。 そのためか彼らは私を八つ裂きにしようとしました。でも結局、彼はベルモントに戻って私は比較的自由になった。
彼が大学に戻った後、私がここベデックに来たとき、私は心に決めていたのだ。 来春彼が戻る前に真実を告げようと。
彼の手紙は定期的に届く。 相変わらず愛想がよくて腹立たしいが、私の手紙はというと... ますます冷たくなった。彼がそれに気づかないのが不思議なくらいだ。私は彼がその理由を聞いてくれば、私が屈辱的な真実を告白する道が開けると期待していた。 そのため私は、彼が自分の立場に満足していないのであれば、この話を切り出すのは簡単なことだと思っていた。
クリスマス休暇が近づくにつれ私は休暇を恐れるようになった。 もちろんそれは彼がベデックを訪れることを意味する。しかしついに 私は大きな安堵を覚えた。翌週の木曜日ヘレン・レアードと私は、放課後、彼女の妹を訪ねるためにセンタービルまで車で行き、暗くなった頃に帰ってきた。
私はすぐに2階に上がった。すぐにヘレンがやってきて言った。 「居間に誰がいると思う?」 私はとても恐ろしい予感に襲われた。 「なぜ、誰が? と言ったが、答えは「エド・シンプソン」であろうことは分かっていた。
幸いなことに ヘレンは夕暮れの中で私の顔を見ることができず、もし見れたならさぞかし驚いたことだろう。 しかし全く怪しまれることはなく、彼女は、彼がS'Side(サマーサイド)に来たが、誰も会う人がいなかったと言った。 そのため一緒に一晩過ごすことにしたそうです。 アル・レアードの息子の友人で、ベデック村で教師をしていたそうです。 アル・レアードの息子と親しかったので、この話はもっともらしく聞こえ、レアードもその実態を疑うことはなかった。
彼女が行った後、私は麻痺した頭を奮い起こそうとした。心臓が悪くなりそうだった。 しかししばらくして私は十分な自制心を取り戻し、降りて行って彼に会うことができた。なんとなく
という具合に、その夜は更けていった。レアード一家は、私たちの間に何かあるとは夢にも思っていなかったので、私たちを放っておこうとはしなかった。
ありがたいことです。
数日前、私は彼からクリスマス・プレゼントを受け取っていた。 私のイニシャルが入ったきれいな銀色のペーパーナイフだった。彼の慣れ親しんだセンスで「自己犠牲の上に成り立っている」と書いてあった。想像してみてほしい。
指が火傷しそうだった。でも私はお礼を簡単に書いて、エドに渡した。
エドに渡しておやすみなさいと言った。 もうこんな夜が来ないことを祈るばかりだ。私はそこに横たわり、両手を握りしめて声を出さないように唇を噛みしめた。私は涙の救済(泣いて気分を落ち着けること)を拒否された。ヘレンが同じ部屋で寝ていたので涙を流すことはできなかった。私は朝が来ることはないだろうと思った。
しかしついに朝が来て私は解放された。 エドは朝の船に乗るために出発しなければならなかったからである。 しかしその恐ろしい夜、私はエドに再び会う前に、婚約を破棄しなければならないと確信した。
私はこれ以上この嘘を生きることはできない。彼はきっとそのことで私を苦しめる。しかし事態は悪くなるばかりで、嘘の生活で事態を改善することはできない。
私は何としても彼に真実を伝えなければならない。私はどんな犠牲を払っても私の人生から97年(この1897年と言う年を)を消せるなら、どんな犠牲もいとわない。この先もずっと悪夢のように思い出される.
ああ私はとても恥ずかしく思います。 この不幸な時代、私はどういうわけか、外見上は陽気な仮面をつけて普段通りの生活を送って書き続けてきた。 何度か採用されたがもちろん却下もたくさんあった。
9月に結婚したのは誰だと思う? ジェシー・フレーザーだ。ベルモントの "老女" だ 彼女はニューブランズウィックの年老いた男と結婚した。二人とも枯葉色に近いので
2人とも枯れ葉色の老人で 情緒不安定だ。この人はジェシーの過去をすべて知っていたのか、あるいは気にしていたのか。彼女のような過去を持つ女性の気持ちはどんなものだろう。罪の記憶の中に甘美さはあるのだろうか。
それとも苦い思い出ばかりなのだろうか? そして結婚とはなんと不思議なものなのだろう。
私はこの夏までは、漠然と、抽象的にしか考えたことがなかった。 しかしこの半年間、私は結婚をあらゆる角度から見なければならなくなったのだ。 しかし、私はこの映画をあらゆる角度から観察し、その関係を理解するために、不可解な問題と格闘してきた。結婚というものは私にとって今までとは違うものだ。少なくとも私は自分が選んだ男性と、そして愛している人とならなんという天国だろう。
どこでどのように学んだのか? まだ言えない。
ベデックに来てから表面上は最高の時を過ごしている。そして悩みも苦しみも一瞬で忘れることができたとき、私は本当に楽しかったのだ。私の前にいた先生はアル・レアードで。彼は自分が大学に行っていない間の半年間、代役を立てたいと言い出し私の応募があった。 私は彼のお父さんの家に下宿している。私は彼の父親であるコーネリアス・レアード氏の家に下宿している。 とてもいい家族です。レアード夫妻はどちらもとても親切だ。 私と同い年のヘレン・レアードもとても親切で陽気な女の子です。私たちは仲良くやっている。 とても仲が良く楽しい時間を過ごすことができている。他に2人の少女がいる。
13歳のメイと10歳のフェディ、それに男の子が2人いる。一番下のカルヴィンは18歳くらいで、セントラル・べディックに滞在している。 冬の間義兄のいるセントラル・ベデックに滞在しているが、しょっちゅう帰ってくる。大きな青い目と少女のようなピンクと白の肌を持つかわいらしい男の子である。
とてもいい子なのだ。私と彼はとても仲が良く 私はいつも彼を撫でたりかわいがったりしている。 長男のハーマンは26歳くらいで、小柄でやや色黒で、磁気のある(引き付けられる)青い目をしている。
最初はハンサムという印象はなく、彼に会ったとき、私はいわゆる取るに足らない顔だと思った。 しかし最終的にはそう(ハンサムだと)思うようになる。
全体として私はとても幸せな生活を送っている。私のプロとしてのキャリアを楽しい場所に投じることができた。
私の学校には14人の子供たちだけなので仕事に追われることはない。私が経験した大規模校とは対照的だ。しかし上級生が数人いるおかげで私はこの学校で教えるのが大好きだ。子どもたちは皆とても親切で聡明だ。学校はここから200ヤードほどのところにあり、スプルースの林の中にあるとても快適な学校だ。私はまるでずっとベデックに住んでいたかのような気分だ。人々はとても親切で友好的で社交的です。この街は
若い人たちがたくさんいて活気のある場所だ。 そして97年が終わった! これまで一年が終わることを喜んだことはなかったが、97年が去ったとき、私は恐るべき喜びで喜んだ。あの恐ろしい一年がそのすべてとともに、消えてしまったのだ。
失敗と苦しみに情けないほどの喜びで背を向けた。
さて、以上であるが、これは「ハムレットを抜いたハムレットの劇」である。いつか、もう一度、ハムレットを入れて書くことができるかもしれないし、できる気がしないかもしれない。(モンゴメリは悲嘆しても分析とユーモアを入れるのもわすれていない)
.jpg)
レアード家の人々
上段左から、ジョージー、ハーマン、ヘレン、カルヴィン
中段左から、アルファス、コーネリアス、エイミー、ミリセント
下段左から、フレデリック、メイ
1898年4月8日(金曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
日没後、古い白いヒルの島と静かな木々の上に影が濃くなっている。 静かな老木の周りに影が濃くなっている。夕焼けの最後の赤い染みが、西から消えていき
鈍い灰色の雲が再び地平線上に沈んだ。 この古い台所では、すべてがとても静かで静かで、だからとても縮こまって、いやいやながら この半年間の私の生活の忠実な記録は、恐れ多くも残念な文章になるだろうから。
この半年間の私の人生、つまり嵐のような情熱に満ちた人生を書き残すために。 。私はそれを完全に書き出すつもりだ。 たとえすべての言葉が私の心を切り裂いたとしても。私はいつも書き出すことで、少なくとも耐えられるようになるのだ。
この一ヶ月で私は何歳も年を取った。悲しみと心配と心の傷は、その仕事を徹底的にやり遂げた。時々私は自問する。 はたして昔の陽気な娘なのだろうか? それとも悲しみから生まれ苦しみの洗礼を受けたまったく新しい生き物なのだろうか。
後悔と絶望的な憧れの姉妹であり仲間なのだろうか。
3月6日、ベデックにいた私はマクニール爺さんが前日の午後に死んだという電報を受け取った。 ショックは大きかった。正直なところ私はマクニール爺さんに深い愛情を持っていたとは言えない。
ずっと怖かったのだ。 近年は一緒に暮らすのも難しい。とはいえ人はそれでも一生を人とともに生きていくのだから、ある種の愛情を持たずにはいられない。
親族の絆、長い付き合い。 死が訪れると、この絆は引き裂かれることによって明らかになり、私たちは当分の間痛烈に苦しむことになる。その結果、私はショックで茫然自失となり、人生のすべてが黒く塗り潰されたような気がした。
まさかそんなことがあるはずはない。おばあちゃんから最後にもらった手紙では、みんな家で元気にしていたのに。 電報を受け取ったのは日曜日だったので、私は(家に戻るのは)月曜日の朝まで待たなければならなかった。
レアードさんが氷の上を走ってS'Side(サマーサイド)まで送ってくれた。そこで汽車に乗り1時にケンジントンに着いた。 ジョン・C・クラークが迎えに来てくれて、ようやく家にたどり着いたのは8時だった。
アニーおばさん、エミリーおばさん、メアリー・ローソン叔母さんが来ていた。みんなと一緒だととても安心した。 祖母は当然ながら悲しげに倒れていた。おじいさんの死はあまりに突然のことだった。心不全が原因だと思われた。土曜日の昼までは元気だったのに、痛みを訴えて数分後に椅子から落ちてあっという間に逝ってしまった。
私はアニーおばさんと一緒に応接間に行き、彼の顔を見た。彼の顔は全く変わっておらず、生前よりも穏やかで優しい顔をしていた。私は感情を覚えて以来棺のそばに立ったのは初めてで、新鮮で苦い経験だった。しかし以前にも一度、その棺の顔を見下ろしたことがある。
その顔は私の母の顔だった。 私はその時まだ幼く20ヶ月ほどしか経ってなかったが、その時のことは完璧に覚えている。 ほとんど最初の頃の記憶ではっきりとしている。母は
棺の中に横たわっていた。父は母のそばにいて私を抱いていた。私はモスリンの刺繍が施された小さな白いドレスを着ていて父が泣いていたのを覚えている。
部屋の周りには女性たちが座っていて、ソファーに座っていた私の前の二人は、お互いにささやき合いながら父と私を哀れむように見ていた。 その背後では窓が開け放たれ、緑のホップの蔓が伸びていた。
その影が床の上に四角く踊っている。 私は母の死に顔を見下ろしたが、その母の愛はその後何度となく私に大きな悲しみを与えることになった。 私はその顔を見下ろした。数ヶ月の苦悩のために、摩耗し衰えたとはいえ、それは優しい顔だった。
母は美しかったが、死は他のすべてにおいて残酷であった。長い絹のまつ毛が頬をなで金色の滑らかな髪が広がっていた。 私は何の悲しみも感じなかった。それが何を意味するのか何もわかっていなかったからだ。ただ漠然と悩んでいた。母はどうしてそんなにじっとしているのだろう。父はどうして泣いているのだろう。私は手を伸ばして
母の頬に手をやりました。今でもその感触は忘れない、独特な冷たさだった。その記憶が私と母を結びつけているようだ。 母と実際に触れ合った唯一の記憶だ。
部屋の中で誰かがすすり泣きながら、「かわいそうな子!」と言った。「それは私のことだろうか? なぜだろう? 私は父の首に腕をまわした。父は私にキスをした。
その時の変わらぬ顔をもう一回だけ思い出す。 古い墓地で22年間眠っていた少女のような母のことはもう思い出さない。 海のせせらぎを聞きながら祖父の葬儀はとても盛大だった。
翌日私はベデックに戻らなければならなかった。 そこで新しい痛みでしばらくの間、死んでいた古い心の痛みが目覚め再び私を苦しめ、刺し、燃やすために目覚めた。
もちろんエドウィン・シンプソンとの惨めな出来事もその一つだ。
ああ、私はしかしその罪は苦しみによって償わなければならなかった。 人間には計り知れない苦痛を味わったからだ。感情とは呪われたものだ。私は今まで感じたことがなかったが。それを教えるには苦しみが必要なのだ。 マラーと名付けた(苦い水を飲むということか)。 ―― 私は冬の間、エドと文通を続け、魂の抜けたような手紙を書き続けた。彼はそのことに気づいていたに違いないが、気づいていたとしても何のサインも出さなかった。彼からの手紙を期待する日々は、惨めな日々であった。読むのが嫌になった。
彼の手紙は実に退屈で、衒学的(人を惑わす表現)で、込み入った内容で、しかも最悪なことに愛に満ちていた。彼の繰り返される愛情表現に私は胸が痛くなった。その手紙を読み終えると、私はそれをトランクに放り込んで二度と読めないように見えないところに鍵をかけた。
もう二度と読むことはないだろう。 こうして事態はクライマックスに達した。
私はベデックを離れるまで待つつもりだった。 告白するつもりだった。しかしある日こんな生活にはもう耐えられないと思う日が来た。 もうこれ以上の生活には耐えられない、死にたいと思う日が来た。そこで3月初旬のある日、私は自暴自棄になり彼に手紙を書いた。
乱暴で狂気じみた手紙だったが私の言いたいことははっきりしていた。私は彼にもう愛情はない。 結婚もできない。言い訳はしない。
私はは自分の弱さを全面的に認め、自分の自由を返してくれるよう私の気持ちを疑う余地のない言葉で、自由を返してくれるように頼んだ。 私はそれがエドにどんな影響を与えるか知らなかったし、想像もつかなかった。私は彼が非常に高慢なので、このことが私に彼が私を早く解放してくれるのではないか、というかすかな望みを抱かせた。
彼はすぐに私を解放してくれるだろう、嘆願することも、拘束しようと努力することもなく 私を軽蔑して解放してくれるのではと。
祖父の死の知らせを受ける直前にその手紙を郵送し数日間はその手紙が私の頭から離れそうになった。次の木曜日にエドが手紙を受け取り、おそらく日曜日に返事を出し、次の木曜日には私が受け取るだろうと思っていた。そしてその木曜日がやってきた。その夜、Y.P.ユニオンに行ったとき、私たちは郵便局に寄った。私は手紙を受け取った。でもその晩は開封しなかった。 中身が恐ろしかったからだ。内容がどうであれ私を動揺させると思ったからだ。 だから次の晩にJが学校から帰ってくるまで、読まないことにした。
金曜の一日中悪夢のようにその恐怖が私を覆い、家に帰ってもできる限り口実をつけて読むのを先延ばしにした。しかし読まなければならないので、ついに夕暮れ時に決意を固めて読んだ。 20ページもあるとても狂おしい手紙だった。 しかしそれは私が期待したものでもなく、むしろ好みのものでもなかった。私が期待していたのは、非難の手紙であったならば私の心をこれほど深く切り裂くことはなかっただろう。
というのもこの手紙は心を痛めたものだったからだ。 その手紙を読むだけで十分な罰になると思った。 彼は決して忘れることはできない、彼との愛は(ぼくたちの愛は)永遠であると宣言した。そして彼は私が彼を愛さなくなった原因について、彼はとても愚かな考えを抱いているようだった。彼のことを誰かから聞いたことがあるのだろうか?(誰かからボクの悪口でも聞いたのか?) 彼の手紙はあまりに退屈なものだったのだろうか? そんなことで愛が終わるとは思えない。もし愛が実在するならば。
今になってもう少し冷静に考えてみると......。 このような彼の問いかけは、むしろ不思議に思える。なぜ彼は誰かが自分のことを話した(のか)と思うのだろう。
なぜ私に話すのだろう(なぜ私にそう聞くのだろう)。そしてなぜ彼は私が彼の手紙を退屈に感じると思ったのか? 確かに退屈だった。でも絶対に私は彼にそうだと(あんたの手紙は退屈よと)思わせるような手紙を書いたことは一度もない。
彼が議論する難解なテーマへの言及を避けたことが彼にそう思わせたのかもしれない。 しかしこのような推測は無意味だ。 彼はあの手紙では私を自由にすることはできない、私の変身(心変わり)についてもっと情報を求めなければならないと言い続けた。
と彼はまだすべてがうまくいくかもしれないという希望を捨てるわけにはいかないと断言した。
もちろん私は彼にもう彼を気遣うことをやめた、いや、むしろ気遣うことをやめたとは言っていない。 を恬っていた。 そして私たちが会うたびに、彼が私に抱く身体的な嫌悪感(あんたの体質が嫌よ)も伝えていなかった。そのことは(軽々しく)伝えることができなかった。
彼はこの手紙の中で私が恐れていた質問をしなかった。 それは私が答えることのできない質問だった。なぜならこのときすでに ある意味別の男がいたのだが、結局のところそのような質問や告白が推し量るような意味ではないのだ(別の男がいたが浮気ではない)。私はその男性と結婚することはないと思っていた。
.jpg)
モードボクは最高の男だ
フラれるはずはないのだ
私は彼と結婚したいとは思わない。もし彼に会わなかったら。エドについても同じだっただろう。私は "もう一人の男"(ハーマン・レアード)に会う前に、彼に(エドに)反感を抱いていた。
そうでなかったら(私がエドの体質に嫌悪を覚えなかったら)、どんなことがあっても彼に忠実でいられただろう。
あのひどい手紙を書き終えたとき、私はラウンジで丸くなって自分の惨めさをかみしめながら あのひどい冬に何度も願ったように生まれてこなければよかったと思った。
彼は私を心から愛してくれていたのに私がその愛に応えられないのは、なんという逆境なのだろう。 なんという運命なのだろう。もし私が彼が私を愛するように、あるいは私が他の人を愛するように、彼を愛していたら、私たちはどんなに幸せだったことだろう。
しかしなすべきことは一つしかなく、私はそれを実行した。私は再び手紙を書き、前に言ったことをさらにわかりやすい言葉で繰り返し、私には何の価値もないので少しは哀れみと配慮をくれるように求めた。 そして最後に憎むべき束縛から私を解放してくれるように懇願した。 彼の返事は私がベデックを発つ前の金曜日の夜に届いたのだが、私はその時読まずにいた。 最後の夜を惨めなものにしたくはなかった。 だから次の日に汽車に乗るまで読まないことにした。
土曜日の午後2時頃、フリータウン駅で汽車に乗った。 席に着くとすぐに不機嫌そうに手紙を開いて読んだ。 彼の最初の手紙は、私に惨めさと自責の念を抱かせ、そして完全に屈服させ謙虚にさせた。しかしこの手紙は私を怒らせた。私はあまりに激しく苦しんだ。 その反動が理不尽なほど強く現れたのだ。
もし私が彼の手紙を床に投げつけ、その上に足を置くことができたなら、もし私がそれをズタズタに引き裂き、風に撒くことができたなら、もし車の中を野蛮に歩くことができたなら、もし大声で叫ぶことができたなら、もしこれらのことのいずれか、あるいはすべてを行うことができたなら......。言葉にならないほどの安堵を得ただろう。しかし私はそうすることができなかった。表向きは平静を装いながら、頭から足まで震えるようにそこに座っていなければならなかった。
(劇的になってきました)
汽車は荒涼とした野原や葉のない森の上を揺れながら進み、私は抑圧された感情の激しさで頭から足まで震えていた。その手紙は長く、最初の6ページはそれまでに彼が書いたものとほとんど同じだった。私が衝撃を受けた最初の文章は、「ああ、モード、私はあなたを自由にすることができません。
"十分な理由もなく 君を解放できない" "十分な理由 " だと? 私は彼を愛していないし愛せないと言った時
"愛せない" "一緒に暮らせない" "耐え難い殉教だ。私の言葉よ! それは「十分な理由」ではないというのか?
彼はさらに続けた。 「これでいいか?(こうしてやればいいのか) この先3年間は好きなように過ごしていい。 そう誰とでも結婚していいのだ。もし、もしあなたが他の人に属したり、現在と同じ考えで、私に対して同じ態度をとったりするのであれば(3年経ってもボクを蹴とばすというなら)、あなたは完全に自由です。
そして私たちは友人であり続けなければならない、文通を続けなければならないと言った。 いや、私はこれに同意することができなかった。私の屈辱と束縛の感覚はいつまでたっても和らぐことはない。
私の人生を疲弊させることになる。それにそれは愚かなことだ。 私は自分が決して変わらないこと、つまり人生の最後まで「同じ態度」でいることを、疑いの余地なく知っていた。
その姿勢でいることだ。'
家に着くとすぐに手紙(3通目の断わり状)を書き、冷静になる間もなく送った。それは私が書くべき手紙ではなかった。厳しい内容で、今となっては送ったことを後悔している。
しかし、私は罠にかかり、捕獲者の手に猛烈に噛みつく野生動物のような気分だった。そう考えると、私はあえて言えばこれでよかったのだ。きっと、1ダース以上の暗示をかけることができるだろう。
私が必死で、危険なほど真剣であることをエドに納得させるためには、おそらく何通もの懇願と自己反省の手紙よりも効果的だろう。
そして何よりも、彼の私への愛が癒され(覚める)、私とは縁が切れたという事実に目を覚ましてくれることを願っている。彼からの返事はまだない。近いうちに来るだろう。現在このような状況だ。私はこのことを書くのにうんざりしている。もう書くのも嫌になったので、この話題はやめようと思っている。
つぎの話題は、もっとつらいものになるだろう。とはいえ最初から最後まですべて書き残すつもりだ。しかし、そうすることで「書き出す」ことができるようになると思う。いつもそうなのだ。
去年の秋の夕方、湾を渡ってベデックに行き、ぼんやりとした気持ちで太陽の大きな円盤が水面の紫色の縁の下に沈んでいくのをぼんやりと見ていた。紫色の影が遠くの海岸に群がっているのをぼんやり眺めていた。(ハリソンさんが「そんな美麗美句は捨てちまいなさい」と言った情景描写から入っている)
その場から立ち去り、それ以上(べディックでの滞在に)進まなければよかったのだ。そうすれば、多くの燃える涙と苦い心痛、眠れぬ夜と激しい後悔を避けることができただろう。
後悔することもなかっただろう。しかしああ! そうなると、私もまた強烈な歓喜、言葉にならないほど甘美で繊細な幸福の数時間を知ることはなかっただろう。
しかし、そのようなことが続く間、私はそれがすべての代償を払うに余りあると思った。その10月の夜、私は何も知らず、何も恐れず、盲目的に自分の運命に向かった。
さて、ハムレットが登場する「ハムレット」である。ベデックに行くまで私は一度も恋をしたことがなかった。激しく、情熱的に、完全に愛するということがどういうことなのか知らなかったのだ。もちろん、多少なりとも
"ふくらはぎ愛" の発作はあったし、ある男性への激しい恋慕の情もあった。時にはロマンチックな白昼夢を見ることもあった。でも、恋は......。いいえ、それは私にはなかったのです!
本当に愛したことはなかったが、それでも世の中の他の女の子と同じように、私は(恋人についての)理想を持っていたのだと思う。
もちろん、ハンサムで地味な恋人を夢見る少女はいなかった。そして何より大切なのは、知性だ。その最後の部分に、私は特に力を注いだ。
そのため、私は、少なくとも次のような男性に関心を持つことができなかった。少なくとも精神力という点では、私と対等な立場で接することができない男性とは、決して相容れないと思っていた。私は、古いことわざの真理を学んた――「キスは好意でするもので、規則でするものではない」。
その夜、私がレアード氏の家に着くと、すぐにお茶の時間が告げられ、男の子たちが入ってきた。母親が彼らを紹介し、私は生ぬるい気持ちで彼らを見渡した。
最初に来たのはハーマンだった。一目見て私は彼の外見にあまり感心しなかった。彼は中肉中背で、小柄で、その時はむしろ取るに足らないと思った。カルビンは、はるかに好意的な印象を私に与えた。ハーマンよりずっと格好いいと思った。
しかし、夕食の間中、私は何度も何度も後者(ハーマンのほう)に目をやった。彼は黒髪で青い目をしていて、睫毛は少女のように長く絹のようだった。27歳くらいだが、もっと若く少年のように見えた。私はすぐに、彼の魅力には何か素晴らしいものがあると結論づけた。
それが何なのか、私は定義することができなかった。とらえどころがなく磁力を帯びていて心にしみる。表情なのか特徴なのかはわからない。(父の目に似ている)
少年たちと知り合いになるのに(モンゴメリは大きい子でも少年と呼んでいる)それほど時間はかからなかった。ハーマンは陽気で楽しくてたまらない。私はすぐに彼について決心し(この男は結婚の候補にはならない)、その決心を変えることはなかった。
彼には知性や教養や教育のかけらもなく、農園や若者たちの輪の外にあるもの(世界のこと、政治のことなど)には何の関心もない。自分の農場と彼の行きつけの社交界を構成する若者たちの輪を超えた何ものにも興味がない。冷静に考えると彼はとても素敵で魅力的な若い動物に過ぎないのだ。それなのに......。
最初の3週間は、何事もなく過ぎていった。私は新しい仕事に忙殺され、他のことを考える余裕がなかった。ハーマンと私は話し、冗談を言いからかった。家の中を歓声と笑いで満たした。
木曜日の夜は、いつもセントラル・ベデックにあるバプテスト・ヤング・ピープルズ・ユニオンの会合に出かけた(バプテスト宣教師の活動が盛んだったようだ)。楽しいドライブもさることながら、往復の道中も陽気なおしゃべりに花が咲いた。
ユニオンの3日目の夜は、11月11日にやってきた。私はこの日を忘れることはないだろう。この日は、情熱と苦痛の道への第一歩を記したものだからだ。ユニオンの後、私たちが家路についたのは、穏やかな月夜だった。私はその道の曲がり角をすべて覚えている。
セントラル・ベデックにあるコリン・ライトの家まで行き、そこから影のように長く続くブラッドショーの道を下っていった。それから、影のように長いブラッドショーの丘を下り、星の反射でゆらめく小川を越えた。あの道を曲がるたびに覚えている。そしてまた長い坂を上ってセンタービルへ、そして「ハワットの曲がり角」だ。
私はその夜は疲れて眠く、話す気にもならなかったので、私はとても黙っていた。
突然ハーマンが身を乗り出してきて私に腕を回し、微妙な愛撫のような動きで私の頭を下に引き寄せ私の頭を彼の肩に押し付けた。
私は憤然と背筋を伸ばし、何か辛辣なことを言おうとした。しかしそうする前に、ハーマン・リアードが私に及ぼした不可思議で抗しがたい影響力が、まるで呪文のように私を襲ってきた。
その日以来、ハーマン・リアードが私に及ぼした不思議な影響力は、私が逃れることも克服することもできない魅力であった。その魅力から逃れることも克服することもできず、世界中のどんな決意や意志の力にも対抗できない。羽毛の重さほどもなかった。何とも言いようのない、圧倒的なものだった。だから私は動かなかった。彼の肩に頭を乗せ、声もなく、動きもなく、私たちは静かに家路についた。
家に着くと、私は何も言わずに馬車から飛び降り、二階に駆け上がった。私は全く新しい奇妙な感情の洪水に圧倒された。理解することもコントロールすることもできなかった。私はぼんやりと、何らかの危険が迫っていることに気づいていた。
この先にはきっと危険が待っている、もう二度とそんなことはさせないとと決心した。しかしその翌日の夜、センタービルでのパーティから車で帰宅する途中、次のようなことが起こった。
センタービルでのパーティから車で帰る途中、それはまた起こった。彼は私の頭を自分の肩に引き寄せ、そのとき、私は歓喜と恍惚に包まれた。
歓喜と歓喜が私を襲い、私は言葉を失い彼を禁じることができなかった。次のユニオンの夜ハーマンはさらに一歩踏み込んだ。それはジェームス・モンゴメリーのすぐ下だった。(ジェームズ。モンゴメリーの家に入る脇道と言う事であろう)
モンゴメリーの白い家を月光が照らしていたのを覚えている。些細なことでも、私の記憶に鮮明に刻まれているのだ。
ハーマンが突然、首をかしげ、私の顔に唇を近づけたのです。私は何に取り付かれたのか分からない。私は、自分ではどうしようもない力に揺さぶられているようだった。
このような火と歓喜のキスは、私の人生の中で、経験したことも想像したこともないような、炎と歓喜のキスであった。エドのキスはせいぜい氷のように冷たいだけだった。
ハーマンのキスは、私の全身の血管と繊維に炎をもたらした。それは私に警告を発していたのかもしれない。家に帰り、一人になると私は、問題を正面から受け止めようとした。このままではいけない!」と。私は婚約していたのだと。
愛していない相手と結婚することはないだろうと思っていた。ハーマン・レアードに会う前から分かっていたことでもある。しかしそれは重要な違いではない。
自尊心のために、私は他の男性とのいかなる関係にも身を投じないようにしなければならない。この決意を守っていれば、いやむしろ守っていられたら、私は計り知れない苦痛から解放されていただろう。
その数日後、私は自分が愛しているのは自分だという熱い意識に直面することになったのだ。私はハーマン・リアードを愛しているのだという熱い自覚に直面することになった。その愛は私の全身を支配し、炎のように私に取り憑いていた。狂気の沙汰としか思えなかった
狂気! そうだ! たとえ私が自由であったとしてもハーマン・レアードは夫として不可能だった。そんな男と結婚するなど。もし私がそうしたら(ハーマンと結婚したら)...1年かそこらは幸せだがその後は不幸になる。
残りの人生、ずっと不幸なままだろう。私はこのことをはっきりと見た。私の脳は曇らなかった。私は一瞬たりとも自分を欺くことなくこの恋から何か良いことが生まれるとは、一瞬たりとも考えなかったし、期待もしなかった。
ああ、私はそれを征服しようと懸命に努力した。しかし私は山の急流を止めようとしたようなものだ。あの致命的なキスの翌日の夜、私たちは二人きりになった。レアード夫妻は留守で、ヘレンは自分の婚約者であるハワード・マクファーレンを応接間でもてなし、娘たちはベッドに入った。8時頃ガチョウ狩りに出かけていたハーマンがやってきて、ソファに座って小説を読んでいた。
私はテーブルの横に座って書き物をしていた。私たちは何も話さなかったが、空気全体が電気的に興奮しているように思えた。
30分もすると、ハーマンは焦って本を投げ捨て、目が痛くて読めないと言い出した。そこで、書き終えて他にすることもない私は、音読を申し出た。彼は承諾し、私はその本を手に取った。その夜、私はあまりうまく読めなかったと思う。
ハーマンは手を伸ばして私の手を握り、温かく包み込むような圧力をかけてきた。私は葉っぱのように震えずにはいられなかったので、自分に腹が立った。
彼はそれに気づいたに違いない。6回ほど声がかすれ、頭がくらくらし、文字が目の前で踊っている。ついにハーマンは「もう読まなくていいよ」と言って、本を取り上げた。そして私を自分の横に引き寄せ抱きしめた。
その腕は私を包み込み、顔は私の顔に押しつけられた。30分ほど私たちはそこに座っていた。
時折、私にキスをする以外は何も言わず、動かず、そこに座っていた。そして、私にとっては彼のキスは、すべての天国を開くように思えた。恥ずかしくないの? そうかもしれない。でも私の愛は強く
優れていたので彼の愛撫に従うのが当然と思えた
でもその後 後悔が始まった。二階の自室に戻ると私は何時間も起きていて、何度も何度も、昔のようなやりきれない戦いに挑んだ。己との戦いに明け暮れた
私は自分が愚かで邪悪であることを知っていた、そしてハーマンもどう思うだろうか? もちろん、私がエドウィン・シンプソンと婚約しているという噂は聞いていた。私はそう思っていた。
彼はそのことを決して口にしなかったが、私はそう確信していた。でもヘレンは知っていたのだから、間違いない。だから私は彼が単に娯楽としていちゃついてるのだと思った。しかし私は彼が私を支配するのと同じくらい彼を支配していたのだ。ハーマンはゲームで指を火傷した
自分もそうだが、火の粉が飛んでくる。しかし彼の態度には私には理解できないことがたくさんあった。もし私が彼によく話し合うように勧めていれば理解できたかもしれない。でもそんな危険は冒せなかった。彼は私を乱暴者だと思ったに違いない。
愛撫を半ば強引に受け入れつつも、感情を口にしようとするといつも冷酷に切り捨てる。もし私が彼を完全に理解できなかったとしても、私もまた彼を困惑させたのだと思うと、残念な満足感がある。
一人でいるときは何もかもが苦痛だったが、彼と一緒にいるときは他のことを忘れて、錯乱するほど幸せだった。次の夜土曜日、私たちは夕方二人きりになったが、同じことの繰り返しだった。日曜の午後も、私は居間で一人ソファで本を読んでいた。ハーマンが入ってきて私の横に座り、腕を組んで私に顔を近づけてきた。話す必要はなさそうだった。
私たちは二人きりになるとほとんど話をしない。
夢のような、うっとりするような沈黙でそこに座っているだけで十分だった。そのとき私たちはほとんど話をしなかった。そしてまた彼の腕の中に戻って、彼の頬の暖かさと磁気の圧力を感じたい。彼の頬を私の頬に押しつけ、彼の茶色の毛を私の指でなでる。
愛しているのに愛してはいけない男と同じ家に住むのは恐ろしいことだ。誘惑に打ち勝つチャンスはあるのだろうか?
こうして、ユニオンのドライブや、余韻に浸るひとときが続いた。11月28日が来るまで日曜の夜、ハーマンはヘレンと私をセンタービルのメソジスト教会まで送ってくれた。私はその夜憂鬱な気分だった。その悩みは、生きているものには一言も話せず、にこやかな顔で隠しておかなければならないものだった。
そして、日に日に強くなる自分の不幸な愛について。ヘレンには話す気になれず、私はあまりに惨めで、ハーマンは静かだった。ハーマンは普段は静かな人だった。しかしハーマンは私をバギーから降ろすと私の耳元でささやいた。
"今夜は一緒にいてくれないか?"
断るべきだった。私たちは常に正しいことをするべきだ。でも残念ながら、そうできない人もいるようだ。誘惑はあまりにも強く、その前になすすべもなく身を伏せ気絶したようにつぶやきました。
同意してしまった。
私は夢の中にいる少女のように、その中(誘惑)に入っていった。ヘレンは急いでベッドに向かった。ハワードが来なかったことで、彼女はかなり機嫌が悪かった。
ハーマンを待つことにした。その瞬間私は言葉では言い表せないほどの幸福感に包まれ、同時に恐怖も感じていた。ハーマンの足音が聞こえてくるのを心待ちにしながらも、その足音が聞こえてくるのが恐ろしかった。
ついに彼は入ってきて、帽子とコートを脱ぎ捨て、私のところに来てその冷たい顔を私の火照った顔に押し付けた。私たちは、暗がりと静寂の中で一緒にそこに寄り添っていた。
危険な? それはあまりにも弱い言葉だ。 私は自分が破滅の瀬戸際にいることを知っていた。しかし、私は引き返すことができなかった。
私は、夢にも思わなかったほど愛していた男の腕の中にいたのだ。私たちが別れたあと、私は自分の部屋へ行き、後悔と羞恥心に打ちひしがれた。
私は自分の弱さの代償を払うことになったのだ。夢のように日々が過ぎ去った。私が生きている時間はハーマンと一緒にいる時だけだった。それ以外の時間は相反する情熱に引き裂かれていた。
長い苦悩の日々が続き、眠れぬ夜が健康を害するようになった。健康を害するようになった。しかし、一度でもハーマンの手や唇に触れれば、他のすべての感情は疑う余地のない幸福のひとつに融合された。
こうして時は流れ、私は二重生活を送ることになった。生徒たちを教え、書き、読み、社交界に出かけては話し、笑い、冗談を言い合う。そして、情熱と苦悩に満ちた、その流れとともに、目に見えない見えない内面が、隣り合わせで流れていた。
ハーマンと私は、常に一緒にいる機会を見つけたり、作ったりしていた。当然ながらこの新しい予期せぬ展開は、エドウィン・シンプソンに関して、さらなる苦悩の種となった。不誠実だという惨めな気持ちと相まって、私の婚約はこれまで以上に悪夢のように耐え難いものとなった。
その頃、エドが休暇の計画を書き始めたとき、私はすべてを失った。その時の私の心境では、彼に会うということに直面できなかったのだ。ところであの古い玉石の皮肉は、不思議なことに運命の皮肉というか......エドがいたからこそで、
私がベデックに行ったのは、エドはアルフ・リアードを知っていて、私がそこの学校に教職を申し込むと、アルフに頼んで、私のために影響力を行使してくれた。その結果、私は学校を手に入れることができたのだ。そして12月11日の土曜日、私は彼から手紙を受け取った。私は安堵して泣いた。
その晩は暗い雨模様だった。私が居間で書き物をしているとハーマンが入ってきた。ヘレンはオルガンを弾いていた。
ハーマンは私に覆いかぶさり、「今夜はしばらく一緒にいてくれないか」とささやいた。私はうなずき、彼は出て行った。私は自分が何を書いているのかわからなくなりながら、書き続けた。他の人たちが寝静まった頃、私は台所へ抜け出した。ハーマンが待っていた。彼は読んでいた本を投げ捨て、私に会うために前に出てきた。
前にも述べたように、エドが突然ベデックにやってきたとき、その時の私の心境は、言葉では言い表せないほどだった。同じ屋根の下に二人の男がいて、そのうちの一人は私が愛しているが決して結婚できない男だった。
一人は愛しても結婚できない人、もう一人は結婚を約束したが愛せなかった男。あの夜私が味わった恐怖、恥辱、恐ろしさは語られることはない。私の本性にあるあらゆる暗い情熱が解き放たれ、暴走したように思えた。その争いに殺されなかったのが不思議だ。
ハーマンがどう思ったか私にはわからない。それ自体が疑わしい。しかし彼の考えを推し量ることはできる。
ハーマンはそれ以来、時々、情熱的な衝動に駆られたときを除いては、二度と同じことはしなかった。
しかし彼の考えを推し量ることはできる。彼は私がエドと婚約していると思い込んでいて、(ハーマンとのことは遊びで)楽しんでいるのだと思ったのだろう。彼がそう思っても文句は言えない。私の振る舞いがそう思う権利を彼に与えたのは確かだ。きっと彼は私を、一人の男と婚約しながらもその男に不誠実な女、他の男とたわむれることができても、言葉では約束しない女と見ていたに違いない。(私はハーマンには辛辣な事を言っているのだが)
ハーマンがそう思っていることを信じなければならないのは大変なこだが、彼が真実を知るよりはましだった。そう冷徹な好みで言えば、私はむしろ彼が私が無鉄砲な浮気者で、無鉄砲な限りを尽くしていると思われることより「彼を劣等と思いつつも
激しく愛していることを 知られるよりはいいと思うのだ。頑固なプライドがそうさせるのだろう。
クリスマスの前の水曜日の夜、ハーマンはS'Side(サマーサイド)に行き、一日中いなかった。
私は部屋に戻ると馬車の音が聞こえたので駆け出し、雑誌を受け取ったかどうか尋ねた。彼は何も言わず、そのため私は部屋に戻ってから憂鬱な気分になってソファーに座り不機嫌になった。ヘレンは不在で、私はブルーの深淵の中にいた。
やがてハーマンが2階から私の部屋のドアまでやってきて、手に2冊の本を持っていた。彼はそれをチョコレートの箱といっしょに私に投げつけ、「それは君にだよ、モード」彼はそう言って、私がお礼を言う前に立ち去った。
クリスマスイブがやってきた。ヘレンはまだ不在で、その夜ハーマンがホールで私を待ち伏せした。その夜もしばらく一緒にいてほしいと頼まれた。私はエドの訪問以来、彼の態度が微妙に変化したことに痛みを感じていたが、以前のような関係に戻ったことに喜びを感じていた。
しかし、明晰な頭脳と容赦ない良心の両方が、そうしない方がずっとよかったと私に告げた。
私は、モンゴメリ家の情熱的な血と、マクニール家の清教徒的な良心とが混ざり合っている。どちらも完全に支配できるほど強くはない。
ピューリタンの良心は、熱い血の思い通りにならない部分もあるが、すべての快楽を毒する(厭な気持にする)ことができる。
情熱は言う、「続けろ」。幸せのカケラを拾いなさい" 科学は言う、「望むならそうしなさい。血に染まった殻で魂を養いなさい。と言う。
その晩もまた、前の声だけを聞いて、詐欺の後遺症に値する――そう、十分に値する――幸福な数時間を過ごした。科学的な話だ。私はそう思うから、そう言うのだ!
次の日は日曜日だった。カルと彼の従兄弟が一日過ごすためにやってきて、夕方、ハーマンは彼らをセントラル・ベデックまで車で連れて行った。帰ってきたのは夜の11時だった。私は部屋で本を読んでいたが、今はラウンジで不機嫌に座っていた。ハーマンは2階に上がると彼が入ってきた。彼は言い訳にもう一冊の本とチョコレートの箱を持っていた。彼はそれらを私に渡すと、ソファーの足元にある椅子に座った。
私は疲れていて孤独だった。暗闇の時間が恐ろしかったし、彼を追い出す気にはなれなかった。彼はそこに座り、私がキャンディーをかじっている間、私に話しかけた。そしてついに彼は立ち上がり、ランプを取りに寝台に向かった。私の頭のそばの椅子まで来て、腰を下ろし身を屈めて、私の横のクッションに頭を置いた。
私は、これは行き過ぎだと思いできるだけ無頓着な口調で言った。「これ以上起きていると、明日は眠くなるぞ」と。この状況をさらに深刻にしたくなかったからだ。
ハーマンは私の意思表示に異議を唱えたり無視したりすることはめったになかった。そしてその時間帯に私の部屋にいる筋合いはないことを、私と同じように理解していた。彼は一瞬躊躇したが、「そうしよう」と言い、私にキスをするために身をかがめておやすみなさいとささやいた。私は抵抗の力を送り出し、それを拒むことはできなかった。
私は衝動的に彼の首の周りに私の腕を投げつけ彼にキスをした。そして、彼が去った後マクニールの良心が私に何か言ってきたのだ!
97年が去り、98年が来たとき私は自分を奮い立たせ、物事を正面から見ようとした。このままではいけないと思った。このまま問題を放置しておくと、次の2つのうちどちらかが必ず起こると思ったからだ。
このまま事態を放置しておけば、必ずや二つのことが起こるに違いない。私の健康やもしかしたら私の理性そのものが、あるいは、私が立っている断崖絶壁の縁を越えて、奈落の底に落ちていくだろう。そして私はどんな犠牲を払ってでも、どんな苦しみを味わってでも、私を縛っている鎖(愛欲の鎖)を断ち切ろうと誓った。
この決意が固まったのも束の間、それは破られた。私は一人、応接間にいた。新年の夕暮れ時、ハーマンが入ってきてまた私と愛し合い始めた。その時の幸福感に、私の決意は忘れ去られた。しかし溺れるようにもがいた。
私はハーマンの邪魔をしないように、可能な限り避けようとした。しかし誘惑には勝てなかった。しかし、それはなかった。ハーマンは3週間も私を放っておいた。彼は私が避けるのを感じ憤慨したのかもしれないし、エドの訪問の影響かもしれない。いずれにせよ私たちはそれ以上「シーン」を持つことはなかった。脳は冷たく「神様ありがとう」と言い、良心はそれを承認した。しかし、心は......ああ!!!」。
しかし、突然、別の体験がその境を再び破った。1月下旬の嵐のような金曜日の夜だった。夕方、ヘレンは台所で手紙を書いていた。私は火のそばに座り彼女が寝るのを待っていた。ハーマンはラウンジに寝転がって、犬のジンクと遊んでいた。
私たちは皆、冗談とたわいのないおしゃべりを続けていた。そしてついにヘレンと私は、お互いにある冗談について謎めいたことを言い始めた。
ハーマンは謎を嗅ぎつけ、ハーマンは謎を嗅ぎつけ、それが何なのか知りたがった。しかし私はそれを拒否し、私たちがふざけている間にヘレンはいたずら心で立ち上がり、ランプをひったくりドアを閉めて走っていった。
その夜、ハーマンは私に泊まれと言うつもりはなかっただろうし、私もそんなことは考えもしなかった。しかし私たちはどちらも、このように突きつけられた誘惑に抵抗できるほど強くはなかった。その結果、3週間の苦闘は無に帰し、私たちは再び元の生活に戻った。
日曜日の夕方、私は頭が痛くなり居間のソファーで丸くなった。ハーマンが入ってきて、私の足元のソファーに座り、本を読むふりをした。メイが部屋にいる間、ハーマンは私の手を握って熱心に読んでいた。
私のショールの下で、ずっと私の手を握っていた。その手を握り、指で撫でる。その指先の小さな愛撫が私の顔を紅潮させるほどの喜びを与えてくれた。ハーマンの目を見ることは、私には決してできないことだった。あの日、私は彼の紅潮した頬、長い黒いまつげ、くすんだカール、そんなものをぼんやり眺めていたら、彼がふと振り向いた。
しかし、私がその魅惑的な視線から私を引き離したとき、彼はまだ私を見下ろしていた。
その時、彼はまだ私を見下ろしており、私が再び顔を上げようとしないことに気づいて、私が顔を上げるまで私の手首を揺さぶった。
そして、メイが出かけてしまったので、彼は本を投げ捨てると素早くしなやかな動きで私の横に寄り添い、彼の腕は私の周りに投げ出された。
彼の黒い頭が私の肩にのった。私は動くことも話すこともできなかったが、どちらも望んでいないほど幸せだった。
月曜日と火曜日は雪に閉ざされ、郵便物は届かなかった。ハーマンは火曜日の夕方、郵便物を取りに行った。ハワード・マクファーレンも現れ、彼とヘレンは応接間でくつろいだ。私は仲間を失ったので2階の自室へ。ハーマンは11時に帰ってきた。2階に上がると私の手紙を運んできました。私はラウンジで本を読んでいた。彼は私の横の椅子に座り、手紙とチョコレートをくれた。私はあまりに寂しかったので彼を追い払うことができなかった。私は手紙を読み、クリームをかじり、彼とおしゃべりをした。
しかしハワードが行くのが聞こえたので、それを合図にハーマンはヘレンが来る前に部屋を出て行った。金曜日の夜、ヘレンとハーマンは、セントラル・ベデックでのコンサートの練習に出かけた。ヘレンはそこに一晩泊まるつもりだった。ハーマンが帰宅すると、またもや郵便物を持って私の部屋に来た。彼はいつものように座って、最初の30分は郵便物に目を通したり、セントレジスの嘘の行動についての噂話をしたりして、無難に過ぎていった。
私は、会話を続けようと必死に努力した。しかし、とうとう私はもう話すことがないことに気がついた。ハーマンも同じように沈黙した。私は彼に出て行けと言うだけの決心をしようとしたが、彼が突然私の横に滑り落ち、私の顔に顔を埋めた。
私は、ハーマンが私の横にすわりこんできて、私の肩に顔をうずめた。声が出なくなりそうだったが、なんとかこう言った。"もう行ってください"
彼は言葉では何も答えず、ただ一瞬頭を上げて私の目をまっすぐ見つめた。彼はそこに、強い願いと気絶しそうな意志の惨めな告白を見たのだろう。
その時彼は再び腰を下ろし、私の周りに腕を回し、私の顔に顔を押し付けた。
狂気? そうなんです。その時も今と同じように鮮明に覚えていた。しかしその知識は何の役にも立たなかった。危険は承知だった。経験した者だけが理解し許せる致命的な呪縛の中にいたのだ。
経験した者にしか理解も容認もできないが、私は彼を追い出すことができなかった。それは彼の腕の中にいるのは天国であり、私はその喜びに身を委ね、他のことは一切忘れた。蝋燭の火は弱く、部屋は半光沢になった。私たちは何も話さず、何もしようとしなかった。しかし、もし彼が行ってしまうのなら......。
そして、最後にハーマンは私の耳元で一つの言葉を囁いた。その意味は誤解のしようがない。
私は怒ってはいなかった。怒る資格はない。その上、私は彼をあまりにも愛していたので、彼の言動に腹を立てることはできなかった。しかし彼の言葉は私に救世主のような衝撃を与えた。その言葉は無言の愛撫のような陰湿な誘惑にはない反撃の衝撃を私に与えた。
「ダメダメ」と私はあからさまに叫んだ。「すぐに自分の部屋に戻りなさい ハーマン...」「ハーマン......とっくに帰ってるはずだ。行って!」。
私は泣きながらそう言った。ハーマンはすぐには行かず、それ以来、1、2分は何も言わなかった。そして長い間、しがみついていた。そして床に膝をついて、私の顔を引き寄せ、長いキスをし、去っていった。
私は恥ずかしさのあまり、クッションの間でうずくまってしまった。ああ、私は何をしたのだろう。彼は何を言ったのか? それは物事がどのようなパス(転換点)に来ていたということは可能か?
ヒステリックな「ノー」というかすかな声だけが、私と不名誉の間に立ちはだかっていたのだろうか。その夜私は決して眠れなかった。あの時の苦しみは、今も私を震え上がらせている。朝が来ると私の最悪の罰がきた。下へ降りて、彼と対面することになった。私は...彼が出かけたと思うまで待ったが、私が降りた時には、家族全員が朝食中だった。私はハーマンの向かい側に座らされ、決して目を上げることはできなかった。
目を離してはいけない。彼もそうだったと思う。それ以来私たちはこの出来事を無視し、何の説明もしなかった。それから一週間、彼はほとんど留守で私はひどく淋しかった。その寂しさに私は怯えた。私たちの最後の別れを思うと、惨めで目をつむった。
しかし、その長い一週間は過ぎ、彼は土曜日に帰ってきた。日曜日の夜彼は教会へ行き、11時頃戻ってきた。私はその夜彼が私の部屋に来ることを恐れていなかった。なぜなら郵便物がなく、その結果彼が来る言い訳ができないからだ。だから、彼が私の部屋のドアまで来て、「ヘレンの手紙を預かってくれないか」と言ったときには驚いた。
ヘレンのランプが見つからないので、貸してほしいと言うのだ。私は「もちろんです」と答えると、彼は部屋に入ってきて火をつけた。しかし彼は外に出ようとはしませんでした。彼は私の指輪を試着したりと、何かと理由をつけて事務室の周りをウロウロしていた。明らかに彼は帰りたくないと思ったが、残るためのもっともらしい口実がないことに気づいたのだ。
私はといえば、この一週間、ほとんど彼に会っていなかったので彼の存在を心底待ち望んでいた。
彼の笑顔、彼の愛撫。しばらくすると、彼はやってきて、私のそばに座り、数分間とりとめもなく自分のことを話した。
しばらくすると、彼は私のそばに座り、S'Sideへのドライブについて、数分間、とりとめもなく話した。私は夢の中にいるように背もたれに寄りかかった。私は夢の中にいるように身を乗り出し、顔は熱くなり、心臓は息が詰まるほど激しく鼓動していた。
私は彼をそこに滞在させることは間違っていて、十分愚かなことだとわかっていたが、それは以前ほど危険ではなかった。しかしヘレンはいつ起きるかわからないし、ハーマンはそれを知っているから、前ほど危険ではない。もう「シーン」とすることはないだろう。
私は自分を弁護するつもりはまったくなく、ただ起こったことを話しただけだ。私はハーマン・レアードが好きで好きでたまらなかった。彼がそこにいるだけで、私は言葉にできないほどの幸福感に包まれた。私は良心の呵責に耐えかねて、それを突き放すことができなかったのだ。
だから、ハーマンは留まりますます近くに寄り、私を抱き、唇にキスをした。私は再びその歓喜に身をゆだねた。
私は再びその歓喜に身を任せ、愛する男の腕の中にいることの喜びだけを心に抱いた。彼の巻き毛をなでると、彼はその手をひったくってキスする。まるですべてのキスが最後であるかのように。手首と指に焼きついたキスを、私は今感じている。
12時になると私は言った "坊や、もう帰る時間よ" 彼はすぐに従った。お休みのキスをしてくれた。
その週の木曜日の夜がやってきた。ヘレンはまたもや留守だった。ハーマンはセンタービルでの講演に出かけた。カルビンを連れて帰ろうとセンタービルで講演をした。彼は11時頃に帰ってきて郵便物を持って私の部屋に来て、やっぱりカルは帰って来なかったと言った。もちろん、また同じことの繰り返しだった。私は怖かったし、でも嬉しかった。
そう私は幸せだった。あの小さな部屋は、私にとっての天国でありハーマンの世界でもあった。彼は私を抱きしめ、何度も何度もキスをし私の額の髪を押しやって頬を寄せた。こうして書いていても、彼の腕が私を包み込むのがわかる。
彼の腕が私を包み込み、彼の愛しい巻き毛の頭が私の胸にあたたかい圧力をかけているのがわかるのだ。
12時になった。時計が鳴ったとき、私は言った、「今の聞いたか?」
「また、あの音か」という気持ちの悪い憧れを抑えることも、耐えることもできない。
"なんだ"
時計が12時を打つ。それはあなたが行くための時間だ。"彼は声にならない呟きと、より強い圧力以外何も答えなかった。私は数分間、黙っていた。そして、私は彼を押しのけようとした。
「ハーマン、私が言ったことが聞こえなかったのか」と囁いた。彼は頭を上げ私の目を見下ろした。"眠いのか?"と彼は言った。"眠いんだ"
と言う彼は出て行ったと思ったがそれは嘘だった。
彼はそれを知っていたのだろう。彼はしばらくためらい、私の時計を見てそしてまた私を見た。そして、長いため息をつきながら、もう一度、私の横に滑り落ちた。私はその時、彼を追い払うのを諦めた。私は沈黙のうちにそこに座っていた――ああ、神よ、このような沈黙を。
沈黙。それは千の舌で雄弁に語っていた。私の種族で過去に愛したすべての女性たちが私の中で語られた。ハーマンの燃えるような息が私の顔にかかり、彼の燃えるようなキスが私の唇にかかるのを感じた。
私の唇に熱いキスをした。そして、私は彼が以前と同じ要求をするのを聞いた。ベールに包まれ、半分聞こえないが、はっきりとした一年のような一瞬の間私の人生全体が揺れ動いた。最も恐ろしい誘惑が私を襲った。その恐ろしい力を今でも覚えている。「彼をそのままにして」「せめて一晩だけでも」「彼の肉体と魂になりたかった」
何が私を救ったのか? 何が私を押しとどめたのか。善悪の判断はしない。私はそんなことはどうでもよくなっていた。伝統も訓練もない――本能的な情熱の前に
すべてが崩れ去った。本能的な情熱の狂奔の前にすべて終わったのだ 女が払う代償を恐れることもない。
ハーマン・リアードの不名誉な前菜から私を救ったのは、ハーマン・リアードの軽蔑への恐れだった。もし私が降参したら彼は私を軽蔑するかもしれない! 彼の憎悪や無関心には耐えられるが
しかし、彼の軽蔑には耐えられない。もし、若者のためでなかったら無謀にも情熱の淵に飛び込んだことだろう。もし、そのことがなかったら、たとえ私のその後の人生が苦悩に満ちた悔恨のものであったとしても。
私は、しがみつく彼の腕を押しのけました。
「ハーマン、行け」 私は叫んだ 「すぐに行け、すぐにだ!」
"ダメだ" と彼はつぶやいた
その一言に込められた彼の哀願を表現する力はない。
またしても、誘惑の衝撃に目がくらむ。恐怖というか、決意というか、自暴自棄になり懇願するように息を吐いた。
「はい、はい、行ってください。あなたはここにいてはいけないのです。今まで誰もいなかった さあ、ハーマン、行け!」。
彼は黙っていた。私の腕に唇を押し当てたまま、もし彼が(行くのを拒否したら......もう一度、懇願したら......だが、神に感謝することに彼は拒否しなかった。最後に彼は低い声でこうつぶやいた。よし行こう。次の瞬間、彼はいなくなった。
その夜からハーマンは変わった。怒りのせいなのかはたまた情熱のせいなのか。何だろう。当時も今もエドに関する私への不信が原因だと考えている。
私たちが立っている崖っぷちに彼の目が開かれたのだと思う。そして彼は私と同じように、安全には狂気の沙汰に終止符を打つしかないことを知っていた。
私たちがしていた火遊び。彼は二度と私の部屋には来なかった。カルビンが帰ってきてしまったので、来られなくなったのだろう。ほとんど他人になってしまった。
それから1ヶ月間、私がどんな目に遭ったか語ることはできない。ある意味私はハーマンの変化に感謝した。自制心を取り戻す唯一のチャンスだと思ったからだ。しかしだからといって苦しみが軽くなるわけではない。ああ、あの悪夢のような月だった。時々猛烈な誘惑が襲い、ハーマンと結婚するように勧めた。しかし私は最悪のときでさえ、そんなことを真剣に考えたことはなかった。愛は強いものだった。
しかし、プライドや理性も同じくらい強かった。私は慌ただしい数ヶ月ではなく、長い人生を共にするために必要なすべての要素において、私よりはるかに劣る男と結婚することは私にはできないことだった。
私は、自分がこのような愛にとりつかれるとは夢にも思っていなかった。憑りつかれたというのが正しい表現だ。彼と同じ屋根の下にいるだけで、何ものにも代えがたい奇妙な甘美さを感じた。
彼の一撃は、他のどんな男の愛撫よりも甘美だった(父の目だから)。ああハーマン。私がどれだけあなたを愛してきたか、あなたは決して知ることはないだろう。
もちろん、このような精神的な惨めさ、情熱的な日々と眠れぬ夜、涙の夜もこのような精神的な惨めさを感じないわけにはいかない。健康にも悪い影響を及ぼした。私は痩せ細り青白くなった。誰もがそれに気づいたが、祖父の死を思い悩んでいるせいだと考えた。私はそのことに感謝した。
疑われるのは耐えられなかったからだ。時は流れ、3月も下旬に差し掛かった頃。月の半ばに帰ってきたアルが、再び学校を受け持ち、私は家に帰ることになった。ハーマンと別れること、もう会えないと思うと。
しかし、最後の旅立ちを前にして、私は安堵した。昔のような、疑うことを知らない気ままな幸福を取り戻したいと思った。しかし、平和と静寂、憧れと苦痛の停止を得ることができるかもしれない。私は
安らぎを得ることができるかもしれない。
しかし、ハーマンが最後まで私に対して冷淡な態度を取り続けるかもしれないと思うと、私は彼を残して去らなければならないかもしれないと思うと。カップの中の苦い一滴のようだった。
しかし、彼はその冷たさを打ち破ってくれた。ある晩(3月21日)、セントラルベデックでパーティーがあり、ハーマンは私を車で連れてきてくれた。彼はいつも通り無口で、私もそうだったが、突然彼が言った。
"いつまでここで教えるんだ?"
私は驚いた、というのも、彼が私がもうすぐここを去ることについて言及したのは初めてだったからだ。しかし、私はいつも通り、平然と答えた。口先だけでなく、彼の前でいつもシミュレーションしている無頓着さで答えた。
「あと1週間半ほどよ」。
彼は数分間、それ以上何も言わなかった。それから彼はゆっくりと言った。
自分の写真を持っているか?
「いいえ、今はないわ」と私は言った。彼はそれ以上何も言わず、私たちは目的地に到着した。しかし、愚かにも彼の質問は私に大げさな印象を与えた。
私は、その晩を明るくするのに十分な幸福感を味わった(彼が私の写真を求めてくれるの)。そしてその夜家に帰ると、星が散りばめられた紫色の空の下で、彼はまた昔のように私の頭を肩に乗せ、顔を近づけてきました。
その腕の中で、痛みも傷心も忘れてしまった。そのささやかな甘えは、すべての垣根を取り払い、私たちをかつてないほど近づけてくれたように思う。私たちはかつてないほど親密になったのだ。翌週の金曜日の夜、私たちはミリー・リードの家に招待された。私たちは大きな箱型そりに乗って、スプルース(松の木の一種)の下を歩いて帰った。
私たちは大きな箱そりに乗って、カルヴィンが運転する中、ハーマンは私に腕を回し私を引き寄せました。私は幸せのため息をつきながら、光り輝く湿原を走る間そこに寄り添っていた。
雪に覆われた森を抜けて、輝く湿原を走る間、私は小さな幸せのため息をついて、そこに寄り添った。彼は私をとても優しく抱きしめた。
彼の唇と私の唇は何度も重なり、"天国の炎と地獄の業火で" 忘れられないキスをした。
日曜日、アルとカルは留守だった。夕食後、レアード氏とヘレンは教会に行った。私は頭痛がして教会に行かなかった。ハーマンと私は午後はずっと部屋で二人きりだった。私がソファで丸くなっていると、ハーマンがやってきて、私の横にすわった。私の横に寄り添い、彼の腕が私を包み少年のような頭を私の肩に乗せた。
そんなこんなで最後の一週間が過ぎた。金曜日の夜、ベデックでの最後の夜がやってきた。ヘレンはハワードを待っていた。ヘレンは、応接間に火を灯して、月明かりの夕暮れに彼を待っていた。
彼女は私を呼び寄せると、何もせずに台所を離れようとした。ハーマンがテーブルで読書している姿は、私を魅了し苦しめた。
私は窓際のソファに腰を下ろした。私たちは8時半までおしゃべりしていたが、ハワードは姿を見せなかった。私たちはハワードは来ないだろうと判断した。
ハーマンが入ってきたとき、彼は来ないと判断した。ヘレンは彼の(ハーマン)登場をあまり歓迎せず立ち去るよう素っ気ないヒントを与えたが、しかし彼はそれを受け入れず、やがてヘレンはペットを連れて部屋を飛び出していった。
私はそこにいたが、ハーマンはあっという間に私のそばにやってきて、両腕を私の肩に、頭を私の肩の上に。私は声も出ず、しばらく動けなかった。そして衝動的な優しさに駆られ、私は身を屈めて彼の髪に唇を寄せた。
そして、彼は私を彼の横に引き寄せた。私たちは10時までそこにいた。私は神々しいほど幸せだった。ハーマンには、少なくとも私には自分以外のものを一時的に消し去る力があった。
自分以外のすべてを一時的に消し去る力があった。何も恐れず、何も気にせず、何も悲しまない。
「人生には何の魅力もない。
"彼の腕の外には幸せが見えない"
写真を撮ったら送るように言われたので送ると約束したら彼は言った。
「アルが終わったら、また学校を受けるんだろう?」
"そうではないと思う" と私は言った。
"なぜそうではないんだ?" 彼はそのような驚いた口調で要求した。
"私はこれ以上教えることができないと思う" と私は疲れ果てて言った。"私はおそらくこの後、おばあちゃんと一緒に家にいることになるんだろうな"
と。
彼はしばらく黙っていたが、呆れたように言った、「でも、今年の夏には来てくれるんだろう? この夏、遊びに来てくれるよね?
"手配できればそうしたいんだけどね" と私は言った。
そして、長い沈黙が続いた。一度だけ、私はからかうように言った。"眠くなったのか?" "いいえ" 彼は言った
"何も話さなくても" "ここにずっと座っていられる"だが10時になると、もう行かなくちゃと言った。
"写真 忘れない?" と彼は言った
"必ず送るよ " と私は約束した。
彼は私の上に身をかがめ、私たちは長く情熱的なキスを交わした。それから彼は元の場所に戻ったが、私はすぐに言った。
"ああ、もう行かなくちゃ"
"いつまたおしゃべりできるかな" と彼はささやきました。
"私は知らない" と私は窒息して言った。
彼は私の両手を握りしめて、私を抱きしめた。私は絶望と痛みで朦朧としていました。そしてどうにかこうにかドアまでたどり着いた。私たちはそこで立ち止まった。月光のきらめく輝きの中で本当のお別れをするために。私は胸が張り裂けそうだった
"最後の抱擁の苦しみを 経験したことのない者が
"最後の抱擁の苦しみを"
確かに誰? 彼は私を抱き寄せた――最後のキスで唇を合わせました
"おやすみ "と言って 私は彼を月明かりに残し、そして自分の部屋へ帰った。
朝、玄関先で彼に別れを告げ握手した。他の人と同じように彼はプラットホームに立ち私を見送った。すべてが終わった。私はただ、人生も終わってしまえばいいのにと切に願うばかりだった。
(キャベンディッシュに)帰ってきてから、私は惨めな一週間を過ごした。ハーマンが恋しい。ハーマンが恋しくてたまらない、どんなに努力しても昼も夜も彼のことが頭から離れない。彼は私にとってかつてないほど大切な存在だ。何時の間にか彼の顔を一目見たい、彼の声を聞きたい、キスをしたい、手を握り合いたい、そんな思いに駆られる時間がある。
しかし私は征服する。たとえ私の心が永遠に砕け散ったとしても、私はそれを生き抜く。――たとえ私の心が永遠に闘争の中で押しつぶされても生き抜く。
これを書き出すととても安心する。大きな痛みも、それがすべてを鮮明に蘇らせたからだ。
このような告白をした後で、他のより重要でない事柄を書くのは、とても反クライマックスのように思われます。(終わりの感動から離れてシラケる)しかし、この人生にはあらゆることが混在しているのだ。
最も悲劇的なことの後に続くのだ。この恐ろしい冬の間、私の魂があらゆる情熱で締めつけられたとき、ずっと私は自分の小さな仕事をすべて丹念にこなしてきた。
家庭でも出先でも笑顔でおしゃべりし、あらゆる慣習にきちんと敬意を払ってきた。だからこのように、私はこの情熱的な記憶から、他のより些細な事にも目を向けるのだ。語ることにする。
私は文学の分野でいくつかの成功を収めた。
新しい場所で この悲しい日々の中で、私の仕事は大きな慰めとなっている。私は自分の悲しみや当惑をそれに没頭している間は忘れてしまうのだ。私は非常に野心的だ――おそらく――おそらく野心的すぎるくらいだ。
ハーマンは以前、そう言って私の野心を嫌っているようだった。それが私たちの間の真の障壁だと感じていたのだろう。でも少なくとも今はそれが私の生きるすべてだ。それを追い求めたいと思う。
小説を読むと、そのほとんどが現実の生活にはほど遠いものであり、また現実の生活の淡い反映であることに、あらためて気づかされる。
小説は、実際の生活にはほど遠いものであり、最高のものでさえなんと淡い反射であることか。ある二つの小説でさえも特筆すべきものがあった。
"The Quick or the Dead" が印象的だった。この作品は力強い文章あるが、あまりに病的で均整がとれていない。しかも最後は苛立たしい形で終わる。ヒロインを連れてきて、少しは常識を叩き込んでやりたいと意識させるような、苛立たしい終わり方だ。
リットン卿の『夜と朝』には失望した。リットンは昔、私の好きな作家だった。昔、Nateが大好きだった頃、私もLyttonを熱狂的に崇拝していた。Nateと私は、彼の本や英雄について、いつまでも熱く語り合ったものだった。しかし、ここ数年私の忠誠心は悲しいことに揺らいでいる。
ハーマンは別として、私はベデックと私の学校を去るのが残念だった。私はどちらも好きだったし、学校ではとても成功していた。
祖母は1人では暮らせないので、私は教師をやめて家に残らなければならなかった。正直なところ、胸が張り裂けそうだ......でも、直面しなければならないのだ。爺さんの愚かな遺言で、婆さんが、ひいては私が家にいなければならないのだから。
その立場は非常に厄介で不愉快なものであり、時間が経つにつれてますますそうなっていくことだろう。
そしてまた、私はキャベンディッシュでは事実上、他人であると感じている。私はキャベンディッシュの利害とは全く無縁なのだ。しかし、もちろんこれは一時的なもので、数ヶ月もすれば、この点では昔のようになる。しかし他のことは決して同じではない。このことは、静かならぬ亡霊のように、ことあるごとに私に突きつけられている。
長い孤独な時間の中で、昔の手紙や、P.W.C.に通っていた頃の日記の一部を読み返して時間をつぶしている。その時の日記は、なんと軽快で、陽気で、ナンセンスだったことか! また私の手紙を淘汰する作業も行っている。
この作業は私が家に帰るたびにいつも行っていることだ。というのも、あるものは興味を失ったと結論づけ、それを破棄するからだ。しかし中には決して燃やせないものもある――少なくとも、今の私には、燃やせるとは思えない。
ようやく読み終えたが、とても疲れたので嬉しい。もう遅いし家も静まり返っている。私は疲れている、なぜならこれをすべて書き留めることで、私はもう一度それを生きているように思えたからだ。
私は疲れた。私はこの本(日記)を閉じて、二階の小さな部屋で寝ることにしよう。ああとても疲れた......苦しみと無駄な闘争に疲れた。
おそらく――あえて望むなら――未来は、癒しと治癒とネペンテス(ギリシア神話に出てくる香油の一種、自分の心をマヒさせる油)をもたらすだろう。
1898年7月10日(日曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
この3ヶ月はあっという間だったような気がするが、同時に、前回このページに書き込んでから長い時間が経過したような気もする。私は非常に多くの感情の段階を生きてきた。3ヶ月という短い期間で、そのすべてを受け入れることは不可能に思える。
日曜日の朝。7月の蒸し暑い朝で、鳥のさえずりとポプラのさざめき、レッドクローバー畑とバルサムモミの森の香りがする、クリーム色の空気で満たされている。家は静かで、夢のような雰囲気だ。
前回ここに書いたとき、私は惨めなほど不幸だった。まあ、今も不幸ではある。でも今はもっと穏やかな生活をしている。情熱の嵐やストレスは過ぎ去り、ある種の静けさが私の中にある。苦痛から解放されたことは、それとは対照的にほとんど幸福と思えるほど祝福に満ちている。
幸せのように思える。私は平静を得たが、苦闘なしに得たのではない。
どの糸(記憶をたぐる糸)を先に取り出そうか。エドの人生と私の人生とが織りなす糸を、私は最初に取ろうか。
そうだろうな、まあ神に感謝する、私は今自由です――全く、完全に自由だ。
この日記の最後の書き込みは、私がエドに苦い手紙を書いた直後にしたものだった。そして返事はなかった。木曜日に返事を期待したが何も来なかった。土曜日、火曜日になっても手紙は来なかった。しかし次の日手紙が届いた。手に取った瞬間その中に私の写真があり、それは自由を意味するものだとわかった。I
二階の部屋に急いだ。でも手紙を開くのが怖かった。もし彼がまだ無条件に自由を与えることを拒んでいたら、私は気が動転していたことだろう。気が散っていた。私はもうこれ以上耐えられなくなるまで、耐えて苦しんできたのだ。
私は窓際に座り、手紙を開けた。写真が落ちてきて、それと一緒に色あせたリンゴの花びらも一緒に。去年の夏6月のあの致命的な夜、私はリンゴの花のスプレー(押し花か)を身に着けていた。エドはそれを記念に取っていった。
彼の手紙の最初の3ページはとても辛辣だった。私の最後の手紙は彼を憤慨させた。彼は私に自由を与えてくれた。彼は私は自由だと言い、私は熱烈な安堵感に包まれ、手紙を落とした。その瞬間、他のすべての痛みが忘れ去られ私は幸せだった。
手紙の最後の方になるとエドは軟らかくなり、より控えめで心が痛むような調子で書いている。私の怒りはすっかり消え去り、私は彼に申し訳ない気持ちでいっぱいになった。そこで私は婚約を解消してくれたことに感謝し、これまでのことを許してほしいと頼んだ。そして私が書いた不親切な手紙のことを許してくれるように頼んだ。
そして彼に別れを告げた。私は彼から再び連絡が来るとは思っていなかった。しかし、5月7日にまた手紙が来た。
ある晩、私が帰宅した後、モリーがこちらに来て私たちはここで黄昏時に話をした。この間、モリーは去年の冬にベルモントを訪れたときのことを話してくれた。その中で、ソフィー・シンプソンから聞いたという話もあった。
ソフィーが、去年の夏エドに宛てた私の手紙を読んだと言ったのだ。私はひどく腹が立った。私はエドに、私の手紙を誰かに見られるところに置いてはいけないと何度も忠告してきたのに、結局はエドがそんなに不注意だったことに腹を立てた。
結局のところ しかも、よりによってソフィーが!? 彼は私に自由を与えると書いたとき私の手紙を燃やすと言ったわ。許してくれたら残したい手紙を除いてね私はその考えが好きではなかったが、私のできる限りの配慮をするべきだと思った。だから私は返事を書いたとき、許可してもいいと言ったが次のように付け加えた。
私の手紙がある人物に読まれたことがあるので、気をつけなければならないと付け加えた。このことが、エドが再び手紙を書くきっかけとなった。彼はその「人物」が誰なのか、どうしても知りたかった。
その「ある人物」が誰なのかを知ることを決意し、そのような卑劣なこと」をしたのは誰なのか、私が教えるべきだと主張した。彼はまた長い情熱的な手紙を書いた。
そして、彼は「いつも私を愛している」、私はいつも彼の「理想の女性」であるなどと書いた。ああ、エド、かわいそうに、あなたの「理想」がどんなありふれた土でできているのか(この私がどんなにありきたりな人間か)、あなたが知ってさえいれば。知っていたら......。
彼の手紙が来たとき、私はちょうど街に出ようとしていたので、帰ってくるまで返事を出さなかった。
それから短いメモを書いて、ソフィが彼の手紙を読んだと伝えた。エドが手紙を読んで、それからのソフィーの運命はわからないけど、エドが彼女を責めるなら羨ましくもなんともない。最後に私は彼の手紙を燃やした......灰になり、私は再び自分の女に戻った。
というわけでこれで終わりです。それは屈辱と苦痛の苦いカップであった。私はそれを飲み干したのです(苦汁飲めとかいうこと)。それは私の人生全体を、その
"澱" (ドブの沈殿物のように汚いもの)のようなものにしてしまった。
私の少女時代の美しいページを、絶望と羞恥心で染め上げた。そうです恥です。エドウィン・シンプソンと婚約していた事は恥ずべき事だったエドウィン・シンプソンに 愛情を注いだことより愛していたのに目をそむけたくなるような記憶だが、しかしそれは記憶であって現在の苦しみではない。
帰郷後1ヶ月ほどは孤独に耐えることができなかった。
私はあまりに長い間離れていたので、私はすべてのものの外にいるような気がしていた。しかし、その寂しさは消え去った。しかし、いつも密かな空虚感の痛みがあり、何も満たされない。
しかし、最悪の事態は過ぎ去った。私は再び自分の居場所に戻り、様々な義務やシンプルで熱狂的な楽しみを手に入れた。心を満たしその乱れた和音を再び調和させるようになった。再びハーモニーを奏でるようになった。
この夏、キャベンディッシュはかなり快適だった。何人かの男の子が楽しそうに私をドライブに連れて行ってくれた。しかし、私は彼らには皆ひどく退屈している。私のように悲劇的な感情に翻弄され惑わされるのは、言いようのない辛さだ。私は不滅の天才の泉に酔い、時代の名作に酔いしれたある古典学徒のような心境になるのだろう。
突然、幼いころの学校の初級クラスに押し戻され、また毎日毎日ABCの勉強をさせられるかもしれない。(新たな人生体験を積まねばと言う事か)
しかし、私には他人に依存せず奪われることのないいくつかの楽しみがある。私には本がある――魅惑の世界へのゆるぎない鍵が。私は古いお気に入りを再読し、新しいものも少し読んだ。後者の中には、バリーの
"A Window in Thrums"(ピーターパンの作者ジェームズ・バリーが書いた小説)小説) があった。
この本は、ある種の魅力と素朴さがあり、興味をそそる。バリーはありふれた場所に触れて、それが美と哀愁の花を咲かせる。
ローの "Chestnut Burr"には、ひどく退屈させられた。私はローをとっくに卒業した。そのためには、あまり堂々とした精神的な高さである必要はない。彼はあまりに説教くさいのだ。もし本が自らの道徳を指し示すことができないなら、どんなに善意の著者が削り取ろうともそれを心に響くほどには書き下ろせない。
この春、エラ・ウィーラー・ウィルコックスの「情熱の詩」を送ってきた。この詩は私のために書かれたようだ。私はその一語一句を大切に生きてきた。
そして、今年の小説「クオ・ヴァディス」を読んだ。この小説は非常に力強い。帝政ローマとネロ宮廷の華麗さと腐敗を完璧に描き、そこから初期キリスト教の純粋で恐ろしい美しさが立ち上ってくる。その原始的な単純さを保っていたなら、教義や冗語が氾濫する代わりに、今日でもコロッセオの殉教者たちが血で信仰を封印したときと同じように。強力な力となっただろう。
帰郷して以来、かなりの文章を書き、ゆっくりとしかし確実に、階段を上っている。(私の)最近の作品は、これまで書いたどの作品よりもずっといいと思っている。
私は一生懸命勉強し向上しようと努力している。私は詩を書くのが一番好きなのだが、スムーズに進む良い散文のプロット(題材)を手に入れるとそれを(短編小説に)書き上げるのが楽しくなる。
私は今、私の古い部屋の窓際で書いている。そこは私にとって正真正銘の小さな窓から見えるのは、不思議で美しい世界だ。
美しい。クローバーの香りを含んだ風が吹き抜け、ポプラの木から葉のざわめきが聞こえてくる。鳥たちは楽しげに低空を飛び交う。眼下には古びたリンゴ園が広がり、堤防沿いには桜並木があり、老いたタマラックが見張っている。その向こうには、緑の草原が星屑の舞う谷にそそり立っている。
キンポウゲ科の花々が咲き乱れ、その先には広い野原が広がり、紫色の縁取りのある森林の丘を背景に へと続いている。青い青い空があり、夕暮れには素晴らしい輝きに包まれ夜には満天の星空、夜明けには銀色の輝きに包まれる。
夜明けには銀の輝きに包まれる。
私はこのような人ごとのような題材に手を出し、現実の問題に照らして戦ってきたのだ。 現実の問題から遠ざかっていた。それについて私は何をどう言えばいいのか、ほとんどわからない。私はただ
私の人生における喪失感、つまりは常に存在しえないものへの飢えを、日が経つにつれて知っているし実感している。
帰宅後私はある賢明で慎重な、必要な決心をしました。 つまりハーマン・リアードを忘れなければならないのだから、つまり彼のことを考えるのをまったく拒否することによってそうしようと考えたのだ。 「夢見る者が目覚めたときに、夢から追い出されるように」、彼を私の心から消し去り彼に対する私の野生の愛を飢え死にさせる。 彼への乱暴な愛を、「視線や言葉やため息の食物」、あるいは記憶さえも拒否して餓死させる。 私はこの立派な決意をそのままにしたわけではなく、何度も何度も断片的に壊された。
しかしその失敗は私の努力や忍耐が足りなかったからではない。 私はあらゆる決意と良識をもって戦った。 眠れぬ夜も、疲れ果てた日も、孤独な夜も、私は戦い続けた。
そして孤独な夜と好ましくない朝を迎えるたびに失敗の意識に直面した(ダメだ、あんな男のことを思ってはいかん)。しかし私は徐々に勝利を収めつつあると信じている。
克服するまで戦い続けるつもりだ。
私は約束通り彼に写真を送った。彼はその受領を認める手紙をくれた。 受け取ったと書いてあった。もし私が彼のことを忘れられるようになってきたと思いこんでいたなら、彼の手紙が届いた瞬間に私はそのことを忘れていただろう。
彼の手紙が私に手渡された瞬間私を欺いたことであろうか(忘れたなどと言うことはない)。私は氷のように冷たくなり、頭から足までが震え、目の前には霧が立ち込めた。私はその手紙を唇に押し当てたまま、フラフラと2階に上がり、窓際に座って読んだ。
手紙と呼べるようなものではなかったと思う。あまり長くない。 長くないし全然賢くない。文法に抜けがあり文章も表現も粗い。 書や表現はかなり粗雑だった。世界中の人が見ていないようなこと(立派な表現)は何もない。 しかし、しかし、これほど歓迎され、これほど喜ばれ、これほど感動した手紙は、私の人生の中で初めてだった。
私はそれを暗記するまで読み直した。 一週間も枕元に置いて眠り、暗闇の中でしばしば目を覚まして、それを取り出しては唇を重ねた。 ハーマンがそこにいたなら、同じように熱く唇を重ねたことでしょう。
ペンシーは結婚していなくなった。彼女は先週の水曜日の晩に結婚した。この結婚は密室で行われた。ペンは1週間前から滞在していたが私にも言わなかった。私たちの旧交を考えるとこれは非常にみすぼらしいと思う。
(私は)ぞんざいな扱いを受けた。ペンはここ数年少し変な感じだ。彼女はウィル・ブルマンと結婚してニュー・グラスゴーに引っ越した。私の人生から消えてしまった。
3週間ほど前、私はパーク・コーナーに短期間滞在していた。クララもステラも家にいて、私たちは昔ながらのラケット(どんちゃん騒ぎ)で大笑いした。
ある晩クララと私は長い間話をした。彼女は私と同じような経験をしていて、お互いの苦しみが私たちをとても親密にしてくれた。ケイトは彼女の留守中に苦い酒を飲み、私のように酒かすまで飲み干した。
底にあるのはヨモギと灰だった。 ファニー・ワイズもいなくなった。彼女はCh'Townの書店で事務職に就いた。
.jpg)
ファニー・ワイズ
しかし、私はこのような別れを哲学的に受け止めることを学びつつある。 人間存在の必然的な悪の一部として哲学的に受け止めている。避けることのできないものである。
避けることはできないし悩むのは愚かで無駄なことだ。"古い恋は捨てて″というのは素晴らしい格言であり、それが実行に移せる場合はいいのだが、そうでない場合はどんな慈しみと苦渋をもってしてもその墓を、埋葬し、大切にしなければならない。
そうこうしているうちに、「時間」は、彼が何から私たちを引き離そうとも、彼とともに歩まなければならない。 私たちは一緒に行かなければならない。やがて終わりが来て、私たちは永遠に安らかな眠りにつくのである。
少なくとも昔の生活の疲れや苦痛を忘れるには十分な時間だ。 私たちを待ち受けている他の存在に再び目覚めなければならない。 その存在に私たちが失ったものを見つけることができるかもしれない。
1898年10月8日(土曜日)
また「落葉の月」! 一年一年、なんと早いことだろう。秋は美しく魅力的であるにもかかわらず、いつも何か悲しげだ。それは秋が人生の秋を象徴しているからではないだろうか。
秋は私たちにも訪れるはずの人生の秋を象徴しているからだろう。しかしもし私たちが信じるなら、そしてこのような信念は、正統派であれ非正統派であれ、何らかの形で私たちのほとんどに見受けられる。
冬の後には、別の人生の春がやってくると信じているのなら、それは私たちを悲しませるものではない。 今の私にとって、人生は平穏で何事もないようなものです。私はまた笑うことを学びました。
また笑えるようになった
"しかし私はどこに行っても
"地上から栄光が去ったと"
今日は私にとって「怠惰」な一日だった。仕事をする気にもなれず、気力も湧いてこない。 新しい物語を書き進めるだけの気力も湧いてこなかった。 この夏、私はかなりの量の文章を書き、新しい定期刊行物にも手をつけたし、古いものにもついていった。
この夏私はずいぶん進歩したと思う。物事をより明確に見ることができるようになった。 物事の本質が見えてきたような気がする。
もし私が経験したことすべてが、私に何らかの報酬をもたらさないのであればそれはつらいことであろう。 私は自分の経験したことが何らかの形で報われないとつらいと思いう。時々私はこのことが、あまりにもはっきりとものを見ることを私に教えたと思うのだ。
妄想や幻想をそのままにしておいた方が幸せかもしれない。しかしでも、盲目は決して幸福な状態とは言えないと思う。 新しい視界の瞬きや縮みを乗り越え、もしかしたら現実の激しい白色光に慣れれば、昔のように心地よい黄昏に浸れるかもしれない。
この夏の後半は忙しかったが楽しいこともあった。エドについては私は何も見ず何も聞かなかった。彼は春にベルモントに帰ってきた。私は彼がこの地の友人を訪ね、どこかで彼に会うのではないかと恐れていた。彼はできる限り留守にしていたようだ。 彼はできる限り遠ざかっていたのだろう、ついに彼が飛んできたとき、私は警告を受けるのに十分な時間遠くにいたのだ。 約束したビデフォードへの訪問が急に都合よくなったのだ。彼は私が戻ってくる前にいなくなっていた。
ビデフォードでの一週間は、イーディス・イングランドと一緒に過ごした。楽しい時間を過ごすことができた。 でも悲しい面もあった。もし自分がどれだけ変わったか、良くも悪くもはっきり知りたい人がいたら、しばらくしてからかつて住んだことのある場所を訪ねてみてほしい。そのとき彼女はあらゆる場面で、あらゆる親しい人たちと、あらゆる古い思い出の中に、かつての自分を見出すだろう。
.jpg)
.jpg)
イーディス・イングランドとイングランド邸
彼女は、現在とは対照的に、昔の理想、見解、希望、信念を見ることになる。他の方法では決して見ることができないような。少なくとも私はそうだった。
私は人生の外側にいるような気がした。肉体のない霊のような冷静な目で、昔の自分、つまりビデフォードの学校でリーチをしていたモード・モンゴメリーを冷静な目で見ているようだった。
不思議なことに彼女は(昔の霊となって)まだそこに住んでいるようだった。そして私は(昔持っていた)理想と幻想、人や物に対する評価、楽しみや苦しみの度合い。人や物の見方の違いを目の当たりにしたのだ。
私はある点ではどれだけ得をしたか、ある点ではどれだけ失ったか、取り返しのつかないほど失ったかがわかった。私は時々私にとても親切にしてくれた善良なビデフォードの人々に不思議な押しつけのような感覚を覚えることがありました。
私に親切にしてくれたビデフォードの人たちは、昔から知っているモード・モンゴメリを歓迎していると思っていたからだ。
私はモード・モンゴメリーではなく、モード・モンゴメリーの名を冠し、その肉体に宿るが、結局は偽者に過ぎない全く新しい生き物なのだ。いまの私は偽者なのです。幸せで明るい女の子だった前のモードとは全然違っていて、
理想や幻想をいくらでも持っていて、「一時的なもの」の安定性を心地よく信じていた。強い野心や憧れはあったが、その主な目的は、"自分らしく生きる"
ことだった。
理想を持ち、それを成功させるコツを知っていた。自分を信じ、人を信じ、良心の呵責にさいなまれ、心を尽くしていた。そして、人生の悩みを抱えたりはしなかった。
しかし、今日の少女はそのすべてとどれほど違っていることだろう。彼女は幻想を持たず理想もほとんど持っていない。
昔の立場から見れば、人生は平坦で、陳腐で、儲からないし、罠と落とし穴に満ちている。新しい立場から見れば、彼女には "過去"
があり、その影が彼女の行く手を阻んでいる。彼女の道を横切る。彼女は水面下を覗き込み奇妙なものを見てきた。
あの時のビデフォードの一年を、あの時と同じように生きることはもうできない。古い幻影を拾い集め、着古した衣服のようにそれを身にまとうことはできない。
もしできるなら彼女はそうしたいだろうか? これは私がよく自問自答することなのだ。「できることなら昔の自分に戻りたい」のか?。私は決して答えることができない。
そして、「ノー」とも「イエス」とも言えないのだ。知識の木の実は食べる人に苦い味を残すかもしれない。しかし、その味には、決して忘れることのできない、偽造することのできない何かがある。
Bidefordでの1週間の終わりに、私はBedequeに行きました。
どうしてそんなことをしたのか、不思議に思わないか? 私も不思議でならかった。でもヘレンに約束させられていたので、断ることもこれ以上先延ばしにすることもできなかった。それに、もう一つ理由があったのだが家のてっぺんで宣言することはしなかった。
ベデックを出てから数カ月、私は厳しい闘いに明け暮れていた。何度も打ちのめされたけれども、最後に貧しい勝利を得られなかったら本当に辛かっただろう。私は、ハーマン・レアードへの恋心を押し殺すことにある程度成功していた。
ハーマン・レアードへの熱情を押し殺し、無意識のうちに縛り付けていたのだ。それは本当に死んだのか? それが知りたかった。だからベデックに行ったのだ。もし震えや鼓動がなかったら...あの暴君のような情熱から解放されると思ったからだ。
夕方、ヘレンが船で私を出迎え私たちは家まで歩いた。ハーマンは道のそばの畑で干し草を積んでいて私に話しかけようとやって来た。
彼の手を握り、目を見た瞬間、私は自分が愛しているのだという気持ちの悪い確信に襲われた。
その瞬間、私は彼を心の底から愛しているのだと確信した。その瞬間死んだと思っていた情熱が、苦しげな鼓動とともに、3倍もの命を吹き込まれた。
私は夢の中にいるような気持ちで家に入った。その晩彼らは来客があり、私は昔と同じように自分の痛みを笑顔と快活さで隠すことを余儀なくされた。ベッドに入ったとき、涙が溢れてきて救われた。その時私は冷静さを取り戻し、この状況を正面から受け止めることができた。
その時、私はある程度、冷静に状況を見つめることができた。そして、ハーマンへの訪問は絶対に避けようと決心した。この決意が守られたとは信じられないかもしれないが、私は守ったのだ。
その代償は言葉では言い表せないほど大きいものだった。この家はほとんど訪問客でいっぱいだったのでその方が楽だった。
ヘレンと私は訪問先で留守にすることが多く、家にいる間はハーマンの邪魔をしないようにした。私は陽気で無頓着だった。でも毎晩泣きながら寝たよ。最後の晩、私たちはたそがれ時にみんなで庭に出た。ハーマンがやってきて牛を探しに行くと言った。
牛を探しにに行く途中、とてもきれいな小道があるから見に来ないかと言った。私は一歩前に進んだ。そして私は立ち止まった。何かが......何かわからないけど......私を押しとどめたのだ。このまま行って、数ヶ月の仕事を元に戻すのは狂気の沙汰だ。
私は言った。私は「雨が降りそうで怖い」と言って引き返した。それは私の人生で最も賢明なことであり、最も困難なことでもあった。もし私が行っていたら、どうなっていただろう。私は知る由もない。と、人生の終わりまで考え続けるだろう。
私はこの訪問が終わったことにとても感謝している。もしあと1日いたら、私は死んでいたかもしれないと思った。死んでいたか気が狂っていたかもしれない。ハーマンは、私が散歩に行かなかったので、怒ったのだと思う。
とにかく、彼は土曜の朝に姿を消し、私にさよならを言うこともなかった。そしてそれは終わる――そう。終わりなのだ。私はもうベデックには戻らないし、ハーマン・レアードにも二度と会わないと思うし、そう願っている。
彼への愛は二度と報われないと思う。私私の心を最も深く揺り動かすことのできる人物に出会うことはないだろう。そしてすべてにおいて、私はそうするのが一番だと思う。このような愛が幸福の前兆であることはほとんどないと思うからだ。「運命への挑戦」であり、運命は確実に、そして厳しくそれを罰するのだ。I
私は愛の夢を見たが、それは死んだか殺されたか、そして私はそれをとても深く埋めた。そして今、私がしなければならないことは、それをできる限り完全に忘れることだ。
自分の運命に対して無感覚なあきらめのようなものだ。私は家に帰り、働き、勉強し、そして今、私は安らかな気持ちでいる。積極的な苦痛は感じない。ときどき――。たとえばこうして書いているとき、昔の苦しみが刺さるような感じがする。
突然、懐かしいことに気づいて気分が悪くなる。それから私は目を閉じ死んでしまえと祈る。しかし、それは過ぎ去り、私は再び平静を取り戻す。私は不幸ではない。少なくとも肯定的な不幸ではない。私の人生にはある種の負の不幸がある。それは現在の苦痛ではなく、喜びの不在による不幸である。しかし私は本当に幸せな人というのは、この世にほとんどいないと思っている。
数えることができるほどで、私はその大多数より恵まれるとは思えない。その大多数の人たちよりも好かれるとは思えない。そして結局のところ私は率直に言って私の苦しみは私の正当な罰以上のものではなかったと認めている。
苦しみが軽減されるとは思えないが、むしろ悪化させると言うべきだろう。しかし私はこの不気味な方法で自分自身を裏返すことを止めなければならない。結局のところ言葉というものは、たとえどんなに素晴らしいものでも、言い過ぎたり言い足りなかったりするものだ。私には感謝すべきことがたくさんある。
去年の冬、あの狂ったような情熱で私の人生を完全に破壊しなかったことに。危うくそうなるところだった。ああ神に感謝、それはすべて終わった!!!
私はパークコーナーー経由で家に帰り、クララは1週間私と一緒に降りてきた(家に来た)。ピクニックやドライブなどかなり楽しい時間を過ごした。キャベンディッシュは今とても美しくなっていて、暗いトウヒの丘には花曇りが立ち込め、カエデや白樺は深紅と黄金に輝いている。キャベンディッシュは、私がこれまで訪れた場所の中で最も美しい場所だ。細長い集落で北岸に接し、その輪郭をたどっている。
その素晴らしい水は、色合いと光沢を常に変えながら銀色の灰色から青く揺らめく。月明かりに霞み、夕暮れには紫に染まる。その素晴らしい水の色と輝きは、どの場所からも見ることができる......。
1898年12月31日(土曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
あと5時間しかない旧年の最終日は、間違いなく「日記」を書くのに最適な時だ。
この時期になると、人は自分の内面的な意識を少し整理し、来年に向けて多かれ少なかれ良い決意をする。この時期人は自分の内面を見つめ直し、来年の抱負を語る。私は後日ひとつだけ決意表明をしようと思っている。今のところ私は過去を振り返っている。
98年の記録を振り返るのは、正直なところ、楽しいこととは言い難い。そのページを見てから、永久に背を向けることにする。
夕方である。外は寒く霜が降り星が光っている。今日降った小さな雪が古いセンダンのトウヒを白く粉砕し、新年の王者の足が踏みしめるために、大地を覆う王家の絨毯を敷き詰めたのだ。すべてがとても静かだ。
祖母はテーブルの片側で本を読み、私はその端に座っている。私の足元にはふっくらとしたシルバーグレイの猫が丸くなっている。私たちは古い台所にいる。この長い冬の夜は少し退屈になりがちなのでいつもここに座っている。98年の最初の数ヶ月は嵐に翻弄され、情熱に苛まれたが、この終わりの数ヶ月はまるで平穏で穏やかだ。
正直なところあまりに平穏で、私は少しばかり刺激的なことを望んでいる。しかしそれはそれは好ましいものではないかもししれないし、天は私が今年の早い時期に十分な種類の興奮を味わったことを知っている。この数ヶ月、私は一生分の興奮を味わった。
私は、刺激的でない条件のもとで、できるだけ着実に執筆を続けた。そのうちのいくつかは、新しい場所で受け入れられた。私はこの仕事が大好きだ。私の仕事。日が経つにつれてますますこの仕事に夢中になり、他の希望や興味が失われていくようだ。私の考えや行動、発言のほとんどすべては自分の仕事を向上させたいという願望に従属させられている。私はそのために人々や出来事を研究し、考え、推測し、読む。
ある意味では、私はかなりいい時間を過ごしている。もちろんいつものように悩みはある。キャベンディッシュは、今かなり活気に満ちている。10月には文芸協会が再開され良いプログラムが用意されている。私はその会合を楽しんでいる。私のような静かな生活では、文芸協会の会合のような些細な外出でさえも楽しみの一つなのだ。
歩いて行くのもいいものだ。暗いモミの木に縁取られた道を元気よく歩いていくと会場に着く。ホールに着くまで。そして30分ほど漫然としたおしゃべりが続く。
友人との交流や本の整理をした後、講演、討論、エッセイなど、その日のお楽しみに没頭する。それが終わると、その晩の言動について軽く話し合うことができる便利な付き添い人と一緒に、家まで歩いたりドライブしたりする。その晩の言動について軽く話し合い、様々なシンプソンの特異性を揶揄することができる。
この秋、キャベンディッシュではいくつかの死があった。そのうちの一人が「カーダインおばさん」である。「カーダインおばさん」は、私が物心ついたときから「キャロラインおばさん」だった。実際彼女が若い時があったか疑問だ。本当に、彼女はとぼけた赤ん坊の姿も、ピンクのほっぺたをした赤ん坊の姿も、全く想像できない人だった。
彼女はCさんの家に住み、彼の未婚の妹の家で家事手伝いをしていた。かわいそうにこの世の中で、彼女を本当に惜しんでいる人、寂しいと思う人はいないと思う。彼女は爽やかな人ではなく、いつも心配ばかりしている不幸な人の一人だった。
自分のことだけでなく、他人のことまで心配して、自分も他人も全く休めないような不幸な人だった。それでも、彼女はある種のランドマーク(町の観光物)であり、その点では寂しい存在であった。Wm.教会ではCさんの席が私たちの席の前にあり、キャロラインおばさんは毎年、窓際の角の席でくつろいでいた。
忘れられないのは、彼女のシャーリング(帽子の縁に細かい皺をつける加工)された黒いサテンのボンネット、それともいつも同じボンネットだったのでしょうか? 小さな私の目には恐ろしく、そして不思議なほどよくできていた。ナイトキャップのように、彼女の頭にぴったりとフィットして彼女のしわだらけの顔をぴったりと縁取っていた。(彼女は今まで見たどの人よりも皺が多かった)あのようなボンネットは
見たことがない。
また、彼女の細い肩にいつも正確に同じ角度で掛けられていた古い黒いレースのショールのようなものもほかにはなかった。その錆びた模様をなぞるのが、私の楽しみだった。その錆びた模様は、歌うために立ち上がるときに、私自身を楽しませてくれた。夏にはキャロライン叔母さんはいつも
綿手袋をはめた指に、大きなピンクの「イングリッシュ・ローズ」を挿し、礼拝の間中、それを鼻に当てていた。
キャロライン叔母さんは実に保守的だった。新しいものには魂がないと恐れた。讃美歌は反キリスト教であり、自転車は天国を守るために、闇の王子の道具だ。私は彼女に自転車を買うつもりだと言って、邪悪な喜びを感じていた。
実は私は買う余裕なんてないんだ。彼女の恐怖を見るのはとても楽しいことだった。これ以上ないくらい。もしも私がズボンを履いて出かけると言ったら、どれほど愕然とした顔をするだろうか。
可哀想に亡くなってしまったわ、彼女の個性と偏見にね哀悼の意を。それは彼女の古い座席の角が空になっているのを見ると、寂しい気持ちになる。
色あせたショールをかぶった老人の姿は、そこから永遠に消えてしまったのだ。お墓の中でかわいそうなキャロラインおばさんは人生に否定された安息を得て、憐れな人間の不幸や欠点を心配することもなくなったことだろう。
昨年の今頃の私の心境を思い出し現在と比較してみると、私はいかに多くのことをしなければならないかがわかる。私は昨年の今頃の自分の状態を思い出して現在と比較すると、どれほど感謝すべきことがあるかがわかる(落ち着いた今は文学修行を頑張る)。あの恐ろしい時間をもう一度生きることはできない。
あの忌まわしい時間をもう一度生きることはできない。しかし私はそれをやり遂げ、そしてそれは深く埋もれてしまったのだ。しかしその亡霊が私を責めるようにつきまとうほど深くもない。深くはないがその苦味はまだ私の杯を毒する(楽しいときにも影を差す)ほど強力であり、深くはないがその冷たい嫌悪の記憶が蛇のように這っている。幸せなことだ。
このところいくつかの新刊を愉しんでいる。そのうちの一冊がホール・ケインの話題の新作「ザ・クリスチャン」である。私はこの作品をかなり気に入っている。
正直言って主人公のジョン・ストームには我慢の限界に達した。主人公のジョン・ストームは、現実的な立場から判断すると、愚か者と狂信者の合成物である。しかし私はこう思う。この本もその登場人物も、現実的な立場から判断することはできない。ジョンやグローリーのような人は世の中にたくさんいるのだろう。
そして、彼らの感情の対立は、必ず悲劇的な問題に帰結するのである。ケインの古い本で、"The Manxman" を読んだことがある。この本は私が本当に好きなケインの本の中で唯一のものだ。私はあまり「感動して泣く」ということがないのだが、「The
Manxman」は泣けた。
クリスマスプレゼントにキップリングの『バラッド』をもらった。この本はとても力強く、生命力に満ち溢れている。スリリングで脈動があり、燃え上がるようなそんなバラードだ。自分の些細な興味や心配を忘れて、広い魂の世界へ飛び出し、自分の周りで鼓動している無数の生命をより明確に認識することができる。そして、それは常に良いことだ。
たとえ、その後自分の人生の狭い枠の中に戻ってしまったとしても。そのほうがいい。私たちは、二度とそのような狭い境遇には戻れないのだ。
11月8日、私は名残惜しそうに荷物をまとめ、かねてから約束していた叔母の家へ行くことにした。エミリー叔母さんを訪ねる約束をしていた。「残念なことに」と言ったのは、エミリー叔母さんは私のお気に入りではないし、マルペも私のお気に入りではないからだ。
私はパークコーナーに行き土曜日までそこに滞在した。それ以来私はアニーおばさんのところへ行く」というのは、覚えている限りでは、楽しい遠足のことを意味する言葉だった。そもそも、曲がりくねった13マイルの丘や森や川を走るのはとても楽しいドライブだった。
まず、キャベンディッシュとベイ・ビューを通る3マイルがある。美しい「ホープ川」にかかるベイビューブリッジまでの3マイルだ。さらに3マイル先にはスタンレーがある。この村は別の川のほとりにある美しい村だ。スタンレーには2、3軒の店があり、私たちはいつもそこで日用品を買っていた。子供の目には、スタンレーはかなり大きな町に見えたものだ。スタンレーは宇宙の中心、いや少なくとも太陽系の中心だったのだ。
その先クリフトンという小さな村に向かった。そして、この辺りには黄色がかった茶色の小さな家が 道路に面して建っている。その家は、私の父と母が結婚後住んでいた家であり、私が生まれて最初の一年間を過ごした家でもある。年月が経つにつれて、この小さな茶色い家は、その都度みすぼらしくなっていった。
しかし、私の目に映るその魅力は決して色あせることなく、角を曲がるといつも同じように熱心にその家を探している。
そして98年も終わりだ。本当にありがたいことだ。古い影からその(新しい年の)夜明けの陽光の中に出て行けるように、震えるような希望を持って、この一年のマントを、着古した衣服のように投げ捨てることができるように。
昨年のこの夜、私はガーディナーのダンスに参加し新年を一緒に踊った。ハーマンと一緒に新年を迎えた。時計が12時を告げたとき私たちは一緒に踊っていた。私はその時良い兆しだと思った。
しかし、そうではなかった。ああ98年、私はあなたの中でどれだけ苦しんだことだろう。どれだけ善悪を教え込んでくれたことか、厳しくて残酷で容赦のない先生だ。
しかし結局のところ、98年、あなたの厳しい規律は良い実を結んだ。苦いけれども、私はあなたに感謝する。ありがとう。
1899年
1899年4月4日(火曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
これは4月で、春であるべきだがそうではない。4月には春を期待するものだ。泥とぬかるみと裸の野原と暖かい日差しを期待するものだ。冷たい風、良いそり、雪が降るのは季節外れのような気がする。
しかし、春は遅くとも必ずやってくるし、それは二重に喜ばしいことだ。というのも、この冬はとても厳しかったからだ。お正月からずっとひどい寒さで震えが止まらないので、肉体が疲弊してしまう。この3ヶ月は忙しく、不快ではなかったが、イベント的なものは全くなかった。
このエントリー(日記の記録)に含まれるかもしれない興味深いスパイスは、驚くべき、あるいは珍しい事柄の報告から生じることはないだろ。しかしこの冬の静かな平凡な生活の詳細を書き出してみることにする。
この冬の平凡な生活を、ただ自分の楽しみのために書いてみようと思う。私はこの文章を楽しんでいる。自分の狭い軌道(生活)の中でも、人生や物事に対する自分の印象を書き留め、後でそれを読み返して新しいものと比較するのが楽しい。
私がベデックから帰ってきてからちょうど一年、ほとんど日にちが経っている。不幸で、幻滅して、絶望的な少女だった。今にして思えばこの世のどんなものでももう二度とあのつらい思いをすることはないだろう。なんてことだ。苦しんだことか。どうやって生きてきたんだろう? 今は良い方向に変わっている。
苦痛は、たとえ最も激しいものであっても、時間の終わりまでその影響が続くとしても、それ自身を消耗させる。その影響は時間の果てまで、もしかしたら永遠に続くかもしれない。私たち感覚のある生き物がそうであるならば。だから私は、どうにかこうにか深淵から這い上がってきたのであり、深淵にまた戻る気にはなれない。
この冬は、ある意味とても楽しい時を過ごしている。"ある意味" と言ったのは、というのも、この冬は陽気なのは表面だけで、その下には私の新しい内なる意識が渦巻いていたからだ。新しい内なる意識は巣穴の中で蛇のようにうずくまりながら、そしてときおり私の心の奥底に突き刺さるのだ。しかし私はまだしばらくは自己分析に入るわけにはいかない。
この冬は文芸協会が盛んであった。私の心を喜ばせてくれた数冊の本のおかげである。私はそれが運命の、あるいは摂理の賢明な命令であると信じている。私は欲しい本をすべて手に入れることができないのは、運命の、あるいは摂理の賢明な法則であると信じている。そうでなければ私は決して多くのことを成し遂げられないだろう。私は単に
"本の酔っぱらい" だ。本には酒がその信奉者に与えるのと同じように、本には抗しがたい誘惑がある。
私はその誘惑には耐えることができない。たとえば99年に初めて読んだ新しい物語は、アンソニー・ホープの「フロソ」だった。
ある惨めな寒い夜、ホール(公会堂かなにか)からその本を持ち帰り、2時までベッドに座って寒さに震えながら、凍えながら、しかしそんなことはお構いなしに、2時までベッドで起きていて眠る前に本を読み終えた。それは輝かしいものだった。
人生と "GO" (さあ出発)に満ち溢れた輝かしい物語だった。現実主義も哲学もない、純粋で単純なロマンスだった。私は現実的で哲学的な小説も好きだが、楽しく純粋な小説は好きだ。楽しく純粋な喜びを与えてくれるのがロマンスだ。私はいつもおとぎ話を楽しんでいた。
でも、最近読んだ本が1冊あるんだよ、天罰が下りました。このような本を読むことはない。こんな本を永遠に読まされるなんて、これ以上悪い「未来の罰」はないと思う。
それは古い物語で、「修道院の子供たち」という昔話で、今まで読んだ本の中で最も陰湿でスラムな本で、この本は最も涙もろいヒロインが登場し、どの章でも気絶して何十滴も涙を流すというものだった。しかし彼女が受けた試練や迫害はというと、「軍団」と呼ばれ、この退廃した時代の美しい乙女は、「新しい」女性でさえもその試練に耐えることができなかったのである。
この冬、私はコンサートや社交界に何度か足を運んだ。そのほとんどは朗読をしなければならなかったが基本的には楽しんだ。しかし、「パイの社交界」だけは勘弁してほしい。あれは荒廃の忌まわしいものだ。プログラムは見せかけで、その夜の本当の仕事はパイを売ることであり、ピット(パイ売りのコーナー)では恐ろしいほどの興奮に包まれる。
オークショニア(オークションの司会者)は肺活量が豊富で、ジョークを飛ばすのがうまいオークショニアが選ばれ、パイが競り落とされる。最高値をつけた人がお金を払いパイを手に入れる。
パイを手に入れた人は、権力者に連れられて2階に行き、そのパイを作った人を見つけて、一緒に食べるのです。
パイを買わない人、買えない人は、できる限りの騒動を起こし、何度も手と手を取り合って昔の決着をつけるというものである。バベルは、あなたが考えることも聞くことができないほど大きな帽子であり、その光景は、今まで見たこともないような、ことわざの「熊の庭」のようなものだ。
しかし、ついにパイはすべて売れ、あなたのエスコートは片手でパイにしがみつきながらやってきた。片手でパイを持ち、もう片方の手でパイを持ってきた内気な女学生にしがみついている。彼はそして、女主人たちが熱いコーヒーを出している高いところへあなたを送り出す。
あなたは、空いている場所を確保し、ナイフを握りしめ、フロスティング(霜の降りたような色合い)のシートで覆われたそのパイを攻撃する。それは勇敢に抵抗するがついに打ち破られ、しかし残念なことに、それは白い墓標に過ぎなかった(皮の中身はたいしたものではない)。しかし、この時あなたはとてもお腹が空いていて、何でも食べることができる。
パイをたっぷりと食べ、熱燗を一気飲みする。熱いコーヒーで一息つきながら。部屋中が笑いと会話とパクリで騒がしい。そしてパクパクと食べる。食べ終わったら、パイの残骸を残しながら、勝者には戦利品があるという原則のもとにパイの残りを残して、誰が最初にパイの社交を発明したのか、そしてそのために何をされたのかを考えながらラップに包む。
この冬は、新しい教会建築のための資金調達のために、「裁縫サークル」を組織した。面倒くさいことこの上ない。しかしこれは裏の顔です。仕事とゴシップの楽しい午後にはもう一つの側面がある。そして夜は、少年たちがやってきて、ゴシップと同じようなゲームをするのが楽しみだった。もちろん、群衆の中には「変人」もいて、関係者全員にできるだけ迷惑をかけようとする。
私たちは牧師を失いつつある。彼はトライオンとハンプトンへの呼び出しを受け入れ、今日から彼の地へ「放浪」している。"逃亡中"だ。彼はかなり良い伝道師だったが、牧師ではない。
そのため、このような曖昧な表現になってしまった。キャブ・ロバートソン夫人が亡くなった後、キャブ・ミュージシャンがどんな話をするのか私にはわからない。彼女の言動は、現在の挨拶における天気の座を完全に奪ってしまった。
"ロバートソン夫人の話を 聞いたことは? ロバートソン夫人の近況を聞いたか」「R夫人は何をするか」。というのがお決まりの質問。彼女は実に奇抜で、その奇抜さに驚かされる。ストッキングをはかずにブーツを履いて教会に行ったり、ロバートソンさんの馬具を引き裂いて、それを信徒の男の子たちのせいにしたり、非難したりと驚きの連続だった。この女性はある点では正気ではないと思うし、もし彼女が正気ならその行為に弁解の余地はない。いつもそう思っている。
1899年5月1日
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
春には魔法がある。半分死んだような希望や信仰を蘇らせ麻痺した魂を興奮させる力がある。新しい命の霊薬で、麻痺した魂を興奮させる。春には年齢がない。誰もが若々しく楽しげに見える。介護はしばらくの間お預け。
不老不死の本能に胸がときめく。この頃はとても美しく、まろやかで、風があり甘い。まだ葉はないけれど、茶色の小さな芽が膨らみ、日当たりの良い場所には緑の気配がある。日々は長く、黄昏時はまろやかな恵みで満ちている。
そして雪はすべて消え去った。青い空とかすかな紫色の霧が、そして先週の金曜日の夜、私は小さなピンクと白のメイフラワーを手に入れた。春の始まりだ。この花を見るために春を迎えるために、冬を生き抜く価値がある。
4月は忙しい月で仕事しかする時間がなく、時間があっても道路がないので、家にいることが多い。外出もままならない。外出もままならないので暇な夜は読書にふけった。
今月最初に読んだのは「ロンドン塔」1 で、これは砂糖でコーティングされた(きれいごとが書いてある)歴史書である。昔、私が10歳の子供だった頃モンゴメリー爺さんの家で読んだことがある。殉教者の火あぶりの章が印象に残っていて何週間も頭から離れなかった。この春までこの本を見ることはなかったが、再読するのが怖くなった。
というのも、最初に読んだとき、私はこの本を素晴らしいと思ったし、私たちの子供じみた意見はほとんど残っていないからだ。私は子供の頃に好きだった本を、大人になってから再読し、苦い失望を味わった。それは愚かな空想に過ぎないのだろうが、私にとってその幻滅は昔好きだった人に会うのと同じくらい辛いものだ。
昔愛した幼なじみに会って、記憶の中に描いていたものと違っていたときと同じぐらいつらいというようなものだ。しかし、「塔」はその試練によく耐えた(迫力は薄れていないと)。私には、「恐ろしい章」は、私の血を恐怖で凍らせた。
新聞や雑誌に掲載されたあらゆる浮世離れした物語の中で、その中で私の心に強烈な印象を残したものがある。3月の『アトランティック』誌に掲載された。体外離脱した霊が死後初めて経験することを扱ったもので、3月のアトランティック号に掲載された短いものである。私たちの中にある未来に対する好奇心に訴えかけるものであった。
その好奇心は、私たちが死ぬまで、いや、おそらく死ぬことさえなければ、決して満たされることはないだろう。しかし、もしそうでなければ好奇心はなくなる。
私は再び2階の親愛なる書斎に移り住み、まるで追放から戻ってきたかのように感じている。私はあの一階の部屋が好きではない。十分に暖かくなるとすぐに私はここに行進し、スクラップと改装を開始した。そして私のすべてのラレースとペナテスを移動させ私はここにいる。王国の女王です。哀れなのは自分の部屋と呼べる小さな部屋さえも持てない人間だ。
この「文学」は、4月21日に新バプティスト、ジャクソン氏の論文で幕を閉じた。
牧師はスイッチが入り「宗教vs道徳」。彼は古い説教ではないと言った。「そうでなければ、考えるべきだが、私は考えない!」。考えるべきだが、考えない! これは危険な習慣である。
その紙は乾いていて、かなり霞んでいた。ジャクソン牧師は、この説教のことをすっかり忘れていたのだと私は思う。この件に関しては、私見ではあるが、ジャクソン師は完全に霧散していた。でも彼はとても素敵な人だ。しかし、彼はとても親切な人であり、「宗教と道徳」があまり魅力のあるテーマでなかったのは彼のせいではない。
こうして書いているうちに夕方になってしまった。太陽は木々の陰に隠れ、長い影がゆったりと広がっている。長い影が道や畑に落ちている。向こうの茶色の丘は薔薇と青の淡い空の下で、琥珀色の輝きに包まれている。南の丘のモミの木は青銅のようで、その長い影が丘の草地を遮っている。親愛なる古き世界よ、あなたはとても美しく、私はあなたを愛している。
1899年5月28日
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
...5月はとても忙しかった。リアンダー叔父さんは大部分ここにいて7月までいる予定だ。彼は神経系がひどく壊れているようで、「病気休暇」中である。
おじさんが来たとき、新しい本をたくさん持ってきてくれたので、私は文学の「旅」に出かけた。一週間、昼も夜も本と戯れ、食事の合間にも本を読んだ。最初に読んだのは、マリー・コレリの「リリスの魂」だった。マリー・コレリ著。文学的な見地から見ると、コレリはたいしたことはない。しかし彼女は面白い話を書くことができる。
ウェイマンの「狼の家」はウェイマンが資本だった。そしてクロケットの「黒いダグラス」。批評家の立場から見るとクロケットはこの例で失敗を犯してしまったようだ。
プロットは統一性に欠け、非常にセンセーショナルだが刺激的で魅惑的な、血も凍るような物語として、この作品を保証する。一気呵成に読み終えるに値する、刺激的で魅力的で血も凍るような物語として、私はこの作品を推薦できる。
"ブラック・ダグラス" だ。子供の頃好きな本を好きと言うことに抵抗がなかった。その告白が、味覚や判断の上で「バレた」ものであろうとなかろうと気にしなかった。単純においしい」と言ったことだろう......。
1899年7月24日
私の居間、3:30 P.M.
キャベンディッシュ、P.E.I.
今日から草刈りが始まった。つまり夏の最良の半分が終わったということだ。そして窓の前の畑は、銀色に輝く一面の草原となり、暑い午後の太陽と錆びたような風を受けて輝いている。ポプラの木がそよぐ風は、熟した草の香りを運んでくる。
私は今日の午後、怠惰で、予定していた写真撮影を実行することができない。私は今朝は学校の小川にある、古いモミの木と、それを笑う水と一緒にVictoria Islandの写真を撮った。
私たち女子学生や男子が遊んだあの懐かしい日々に、きらきらと波打ち音を立てていたように。あの頃、私たち女子学生や男子が遊んでいたように。今では私以外、誰もそこに行くことはない。
(私も)あまり行かない。ただ一度だけ迷い込んで、小川と風のデュエットに耳を傾け、太陽の光を眺める。小川と風の二重奏に耳を傾け、暗い枝の間から忍び込む朝日や、ゴッサムシを眺める。
この夏、私たちはここで新しい教会を支援するためのお茶会を開いた。これは本当に大文字で書くべきものだ。
というのも、膨大な量の仕事と心配事があったからだ。しかしもうすべて終わり、前回の報告書までに全員が生き延びた。私たちソーイングサークルのメンバーは、その日の暑さと負担に耐えながら、このイベントを立ち上げた。Mrs.アルバート・マクニール夫人と私は、その前段としてメイフィールドで聞き込みをしなければなりませんでした。
メイフィールドを訪ねた。長い道のりではないので、正気を保っていられたのはそのおかげです。私は生きている限り、二度とこのような活動をすることはないだろう。
「もう二度と、お茶のために道を尋ねるようなことはしない!」。どの家に入っても私は縮こまった。少なくとも1インチ、時には2インチ、3インチと縮んでいき、最後には肉眼では見えなくなったに違いないと思っている。
6月に古い教会を取り壊した。私はとても嫌な思いをした。取り壊しが始まった日私は泣いた。内側も外側も決して立派な教会ではなかった。とても大きな教会で、私たちの席は左側の上から2番目であった。窓際の席で長い西の丘の斜面を見渡すことができ、青い池を見下ろすことができ、砂丘の縁の曲線と青い湾の広がりまで見渡すことができた。ウィリアム・Cの席は私たちの席のすぐ前にあった。モリーとティリーはいつもそこに座っていた。
聖歌隊は、昔はギャラリーに座っていたが、近年は私たちのすぐ前にあるクロスシートに座っている。これは説教のためのものだった。祈祷会では、高水位マークは、中央の列席者、ストーブの周り、そしてギャラリーの下の席であった。
ギャラリーは、近年はコミューンの礼拝で大教会が満員になったとき以外は、ほとんど使われることはなかった。ミッションが大きな教会に溢れるほどあるときを除いては、ギャラリーそのものが使われることはほとんどなかった。昔はいつも使われていた。
私はいつもそこに座りたがっていた。これも禁断の果実の一例である。他の女の子と一緒にそこに行くことが許されたのは、年に一度の聖餐式の日曜日だけだった。特に幸運にも一番前の席に座れたときは、最高のご褒美だと思っていた。その日はいつも新しい帽子や花で満開になった会衆を見下ろすことができた。
新しい帽子やドレスの花が咲き乱れていたのだ。「聖餐式の日曜日」は、その点では都市に住む人々にとってのイースターのようなもので、服飾職人たちは何週間も残業して新しいドレスを作っていた。だからそのため、前方のギャラリー席はとても便利で、新しい衣装のすべてを見ることができた。
私たちは、この礼拝の厳粛さと、それが何を記念しているのかということよりも、その衣装のほうにばかり思いを巡らせていたような気がする。
当時の礼拝は非常に長いものだった。聖餐式を挟んだ2回の礼拝という古い習慣を守っていたからだ。私たち貧しい子供たちはひどく疲れてしまい、その間に聖餐式を行う少年や会衆が歌っている間に立ち上がって帰っていく少年や無責任な人々を、どんなに羨ましく思ったことか。
その夜、私たちは「知るべき運命にある」と思った。私たちはあえて動揺しなかったが、カーストには罰則があることを痛感した。そしてパンとワインが運ばれている間、なんという静けさに包まれたことだろう。
パンとワインが配られる間、長老たちはつま先で歩きながら恭しく列から列へ。私は以前パンには何か特別なものがあると信じていた。そのパンは、普通の家庭で作られたパンではないはずだ。それが(そのパンを作っていたのが)、「ジミー長老」の豊満な妻が作ったものだと知ったときは、本当にショックだった。私はなぜ彼女たちがいつも白いハンカチで顔を隠していたのか気になったが。もちろん、大人になればすべて理解できるだろうと思っていた。そしてそれが終わって、青空の下、外に出たとき、どんなに嬉しかったことか。もう一度、神の陽光のワインを飲むことができるのだ。
しかし、古い教会は、その記憶や連想とともに、もうなくなってしまった。彼らは近代的な教会を建てるだろうが、それは単に木と漆喰の櫛のような国であり、まろやかになることはないだろう。
その美しいとは言えない古い教会を美しくしていた記憶によって、まろやかで神聖なものになることはないだろう。教会も他のものと同じように熟成させなければならない(古びなければならな)。
私は、この悲劇的な章の「仕上げ」の前に、まだ書き残すことがある。私の人生の最も悲劇的な章の "仕上げ" として。それは永遠に終わりをめくる。
ハーマン・リアードが死んだ」。
5月以来、私はヘレンから連絡を取っていなかった。7月1日、郵便が来たとき、その日はお茶の準備で忙しく、私は島の新聞を見ることができなかった。
7月1日郵便が来た。帰宅してお茶を飲んでいると、おばあちゃんが「あなたが下宿していたところに、ハーマン・レアードがいたわね」と言った。
私は不思議に思って頷くと、「そうよ、彼はどうしたの?
"死んだわ"
"死ん!!" 私は馬鹿にして彼女を見つめた "どうして知ってるの?"
"パイオニアに書いてあるわ " と彼女は言った。
私は新聞を取りに行った。地元のコラムに致命的な項目があった。簡潔に書かれていた。彼はインフルエンザの合併症で7週間の闘病生活の後、前日に亡くなった。葬儀は日曜日の午後に行われる。それだけであった。
ハーマン・リアードと別れたとき私の人生のその章は永遠に閉じられたと思った。だからこの死は私にとって何の変化もない。ところが..,彼が死んだと悟った時――私の前から薄暗く恐ろしい未知の世界へ永遠に消えてしまったのだ。
そしてもう二度と、ここでも、この先でも私たち二人が出会うことはないのだということがわかったとき、ああなんということだろう! 私はあまり涙を流さなかった。昔、ハーマンのことでたくさん流したから、今はもうない。夜明けまで眠れぬ枕に悶えた夜もあった。
彼は私の愛に値しないからと、心の中で熱く泣いた夜もあった。そうして彼が死んだ今、私に涙は必要ない。どんな苦悩もかつて私が耐えたものに等しい。死んでもなお 私のものだと思えば楽だ。生前はあり得なかったことだ。他の女性が彼の心臓に 横たわったり、彼の心臓に触れることもなく 彼の唇にキスすることもなく。
しかし、その夜、家中が静まり返ったとき、私は窓のそばにひざまずき、薄暗い、香りのよい外を眺めていた。
星が輝く薄暗い夏の夜を眺めながらその時、ハーマン・リードは棺の中で冷たく、静かに横たわっていたのだ。そして、もし私が彼のそばにいて、彼に呼びかけることができたなら、その時、彼は棺の中で冷たく、静かに棺に横たわっているのだ。その声も届かない。
彼の青白く冷たい唇に微笑みはなく、私の心を揺さぶった濃いブルーの瞳に優しい光はない(詩的な感想が続く)。
その閃光が私の心を刺すような生命にかき立てることもないだろう。そこに膝をつきながら私はこう思ったのだ。あの情熱と苦悩に満ちたベデクの冬を、幸福と悲哀に満ちたあの時間を。幸せも悲しみも。ハーマン・レアードとの出会いを、ハーマン・リアードとの出会いを、最初から最後まで、あの狂おしいほど甘美な時間も、あの悲しい時間もすべて思い返した。
苦い時間、帰宅する前の最後の夜私たちの本当の別れを思い浮かべた。死よりも辛い別れだった。ハーマンの墓のそばで棺の音が聞こえてもあの時の苦しみは半減した。
あの夜、私たちは月明かりの下に立ち、彼の腕が私を包み込み、彼の唇が私の唇に重なり、それが最後だと知った。そして、窓枠に頭を下げ、「これが最後」と願った。ハーマンの腕の中で彼と同じように死に際に冷たく横たわっていることを願った。
ハーマンの腕に抱かれ、痛みも淋しさも、夢のない眠りの中に永遠に消え去り、最後に永遠の抱擁を交わしているように。
ハーマンは死んだ。彼は死んだのか、それとも彼の外殻や殻が死んだだけなのか。彼はまだどこかで生きているのだろうか、生きているとしたら、もしそうなら彼は覚えているのか忘れているのか分からないところをさまよっているのだろうか。
彼のために罪を犯しそうになり(不貞を犯しそうになり)、とても苦しんだことを。私はそれを信じるなら、私は気が狂ってしまうだろう。しかし私はそうではない。それでも彼を冷たい人間ではない霊として考えるのは、ほとんど恐ろしいことだ。人智の及ばぬ魂だと思うのも恐ろしい。
キスする唇も、握りしめる強い手もなくそうだ。いいえ、いいえ、私たち二人が再び出会うことは、どのような人生においても決してないと信じたいのだ。出会いがあったとしても、それは苦痛と恥辱に満ちたものでしかない。私の恥でもあり彼の恥でもあるのだ(情熱に突き動かされることなど恥だ)。
その質問には答えられない。ハーマンは私を愛した...あるいは愛したふりをした。情熱的で官能的で、高尚でも永続的でもない、しかし決して私が彼を愛したようには愛せないだろう。まあ少なくともこの世はこれで終わりだ(人生の意義を失うくらいだ)。
希望か恐れか、どちらかわからないが、これから先のすべての人生において。
| ハーマンの死による新聞の追悼記事 一部に手書きによる修正がある |
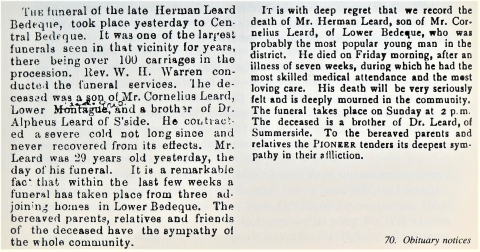 |
| その近辺では、何年も前から葬儀が行われています。100台以上の馬車の行列ができました。W・H・ウォーレン師が葬儀を執り行った。亡くなったのはコーネリアス・レアード氏の息子で、S.モンタギューのアルフィウス・レアード博士の弟である。 S'sideのAlpheus Leard博士の兄弟である。彼は少し前にひどい風邪を引き、その影響から回復することはなかった。Mr.Leard氏は昨日29歳であった。葬儀の日である。 驚くべきことはこの数週間のうちに葬儀がローワーベデックの3軒の隣接する家で行われたことである。ご遺族のご両親、ご親戚、ご友人には、全コミュニティーからお見舞いを申し上げます。 このたびのご逝去は、誠に残念でなりません。コーネリアス・レアード氏のご子息で、ローワー・ベデックに住むハーマン・レアード氏が亡くなられました。この地区で最も人気のある若者でした。彼は7週間の闘病生活の後、金曜の朝に亡くなりました。 その間、熟練した医師が付き添い、細心の注意を払って治療を受けた。彼の死は非常に深刻に受け止められ地域社会で深く悼まれることでしょう。葬儀は日曜日の午後2時に行われます。故人は、サマーサイドのレアード博士の弟です。 サマーサイドの 遺族であるご両親とご親族にパイオニアは、深い哀悼の意を表します。 |
1899年10月8日、日曜日の朝
キャベンディッシュ、P.E.アイランド
私たちはちょうど定期的な秋雨に見舞われている。今はもう終わり、今日は晴れてさわやかで美しい。まるで失われた夏を思い起こすような、さわやかで美しい日だ。しかし、この雨は2日間続き、なんと陰鬱な世界であったことか――びしょ濡れの草原、水浸しでぐちゃぐちゃになった軒先、荒れ果てた谷は靄に覆われ、「海の長い平地」を吹き抜ける生々しい風が吹いていた。
「雨で薄暗い海の底」を吹き抜ける生々しい風。一昨日の夜は、屋根に降り注ぐ雨の音と轟音で眠れなかった。
一昨日の夜は、屋根に降る雨の音と、軒下や外の木々の風の悲鳴で眠れなかった。まるで夜と嵐の魔力が中天でせめぎ合っているようであった。
少し前のある日、メアリー・マッキンタイアおばさんとジェームズの訪問があった。それはとても驚きだった。私はジェームズが家にいるとは知らなかったのでとても驚いた。私は二人に会えてとても嬉しかった。彼らは長居はできなかったが、その間も私たちは(旧交を温めるのに)舌鼓を打った。
私はマクニール家よりモンゴメリー家の従姉妹たちの方が好きである。
リアンダーおじさんやジョン叔父さんの子供を除いては。でもマッキンタイアとサザーランドは兄弟同然に思えるほど親切で陽気で仲がいい。私はいつも心からくつろいでいる。親族や親戚の近くには、何十人もの(知り合いの)人がいるが、その人たちとは見ず知らずの人たちよりも話が合わない。
私はそれを説明できないが、そうであることを痛感し、それを克服することはできない。私は彼らと一緒にいるとき、彼らと一緒にいるときとはまったく別の生き物なのだ。
それは「類は友を呼ぶ」という不文律なのだろう。もし二つの魂がお互いを知らなければ、生まれつきの偶然も、付き合いも、二人を結びつける役には立たない。たとえ半世紀にわたって一つの屋根に覆われていたとしても永遠に他人のままなのだ。
8月に2週間ほどパーク・コーナーに滞在したとき、ステラとフレッドが家にいたので楽しい時間を過ごした。ヘンリー・マクルーアが車で送ってくれた。彼はこの夏ずっと私を車で連れてきた。
今も昔も、友情以外には何も手に入らないことを彼ははっきりと理解しているのだ。彼はラスティコの粗野な農夫で、ダンディなギーギーが取り柄のラスティコの粗野な青年農民だが、私は好きでも嫌いでもない。彼は無価値だが便利な存在だ。
私はパークコーナーにカメラを持って行き、いくつもの{美しい}景色を手に入れた。そこにはジョン・キャンベルおじさんの家の裏には、素晴らしいカエデとブナの林がある。その中をぶらぶら歩くのは飽きることがない。曲がりくねった小道は楓で縁取られ、光はたくさんのエメラルド色の網目を通して柔らかく降りそそぐ。
ダイヤモンドの心のように完璧な光を放つ。娘たちと私は子供の頃、その木々の間を縫って長い道を駆け抜けたものだ。高い木々が、私たちの楽しげな笑い声に無数のエコーを返してくれていた。
9月にエドから手紙が来た。私はそれを手にしたとき、恐怖と反発の寒気がした。それを読んだとき、私は、なぜ彼がそれを書いたのか判断に苦しむ。エドの文体は常に明晰というわけではない。しかしどうやら彼は、私たちの出来事について何か噂を聞いたようで、それが何であるかは言っていない。
その噂が私か、私が誰かに話したことに端を発していると考えているようだ。私はその暗黙の告発が(私がエドの体質が気に入らないと言っている噂を聞いた)腹立たしいと言わざるを得ない。エドは私が彼のことを乱暴に話すことに甘んじていると、あるいはそうしたいと望んでいるのだろうか?
手紙の他の部分は苦痛だった。彼は私を忘れるようにという私の命令に従おうとしたが、うまくいかなかったと言った。「これまでと同じように私を愛している」、などと書いてあった。
私はその手紙に返事をしなければならなかった。私は彼に文字どおりの真実を話した。私の婚約破棄について、それを知っている数少ない人たちに簡単に発表した以外は、彼の言う事は文字どおり真実であることを告げた。
だから、噂が流れても、それは推測の産物でしかない。噂は推測とゴシップの産物でしかない。
最近読んだ新刊は、マーク・トウェインの「More Tramps Abroad」(その他の海外の不貞の輩)だけである。楽しい本だった。旅に出て古い世界の土地や不思議をすべて見てみたいものだ。そんなことができるのだろうか? まずイングランドとスコットランド、それからイタリアとギリシャ。エジプトや聖地もいいけど月も入れたらどう? ということだ。
どちらもあり得る話だ。私の旅の大部分は紙の上で行われると思うし(本を読んで空想する)、その方がはるかに手間も費用もかからないと思う。
先週のある冷たい雨の降る陰鬱な日、私は何もすることがなかったので、座ってウィルの古い手紙を読み返した。それを読むと彼が死んでいるなんてありえないように思えた。少なくともこの平原にはウィルがいないのだから。
私が知っているすべての男性を振り返ってみると......彼らの中にウィルより優れた仲間はいなかったと思う。いやハーマンでさえも。ウィルを愛したことはないが...そして今でもそう思っている、私が知る限り最も素敵な少年だ。私たちの友情は完璧だった。あの頃、P.A.(プリンスアルバート)での日々は今となってはとても遠いことのように思える――実際、遠いことなのだが。しかしウィルの手紙は私をもう一度あの頃へと連れ戻した。
かわいそうなマスタード氏をひどくからかったこと、冬のさわやかな夜に家まで歩いたこと、夏のたそがれ時に散歩したこと、読んだ本について話し合ったこと、そして私たちの知人関係における千差万別の小さな出来事。私は
私は、彼が死んだと最初に知ったときよりも、彼の友情を失ったことをもっと残念に思っている。なぜなら、その本当の価値をよりはっきりと理解することができたからだ。しかし私は知っている。もし彼が生きていて、私たちが再び会うことができたとしても、それはもう不可能なことだとも思う。
ありえないことです。それは、愛をフィナーレとする男と女の友情かもしれない。しかし昔のような仲間意識は持てないだろう。
昨日恋人たちの小径を歩いた。私にとって世界で最も愛しい場所であり、私にとって最も良い影響を与える場所だ。私の気分がどんなに暗くても、どんなに心が重くても、どんなに悩んでも、あの美しい場所で1時間過ごせば、その美しい孤独の中で1時間過ごせば、自分自身と世界との関係を正すことができる。
困惑や悲しみは溶けて森の香りが私の悩める思考に降り注ぎ、無限の安らぎを与えてくれるのだ。無限の平和の恩恵のように。
白樺の下の小道を下り、裸になった学校の校庭を横切るのはいつも同じ道だ。多くの落ち着かない足で、むき出しになり硬くなった古い学校の校庭を横切る。そこには10月の日差しの中、遠く離れた岸辺で波が砕けるような音を立てて、トウヒの木々の間を風が通り抜ける。柵がある。
そして、曲がりくねった道を進むと、穏やかな静寂の中に入り込んでいく。時折木々の隙間から遥かな紫の丘や、輝く青い海を垣間見ることができる。
古くからある泉は、深く澄んでいて、氷のように冷たく、私たちの行く手にある。小川は静かに鳴り響き、モミの木は昔と同じようにその上でささやく。シダは土手から垂れ下がり、野生のつる植物が切り株や根の上で暴れまわっている。小川の下のカエデは金と深紅に輝き、枝の間から上には青い秋の空が見える。
学校の森を過ぎると、秋の野原が二つ。金色に輝く白樺と、霜の降りたワラビで縁取られた2つの秋の野原がある。その先にあるのはカエデやシラカバ、ヤマザクラのある森の縁に沿って、親愛なる小径が続いている。
カエデ、白樺、ヤマザクラ、トウヒが頭上で出会い、隠れた小川の低いせせらぎが耳に入ってくる。一歩一歩が啓示であり祝福なのだ。モミの木の下の空気は紫色で、太陽の光はワインのように爽快だ。最後は小川にかかる橋で、橋の向こうには銀色の野原が広がり、赤いリボンの大通りに出て、丘の頂上を越えて家に帰る。
1900年
日曜日の夕方
1900年1月14日
この日付を書くのはなんと不思議なことだろう。本当にホームシックになりそうだ。1800年代を懐かしく思いう。まるであの頃に戻ったような気がする。
今夜は書く気になれない。退屈で馬鹿みたいだ。このところずっと忙しくて、それだけなんだ。最近の私の人生は、確かに何事もなかったかのようだ。
私はこの前書いてから、10月のある日街に飛び出した以外はどこにも行ってない。というわけで少しは気が晴れた。結局のところ私はそこそこ満足しているのだ。誰の人生にも憂鬱な日や落胆する日があるのだろう。人生のあらゆることが味気なく思えてくる。最も晴れた日には雲がある。しかし太陽はいつもそこにあることを忘れてはならない。
(項目:―あなたが土砂降りの雨の中で外出している場合、それはあなたに多くの利益をもたらすか、またはあなたが乾いていられるようにしなければならないことを覚えておくのは、あまり良いことだろうか?)
アルファベット、ペン、印刷機の発明者たちに祝福がありますように。人生は本がなければ、恐ろしいものになっていただろう。私はこれまで読み方を習ったこともない。でもある日突然、"S" が "S" であることを知り、魅惑の世界へ一歩を踏み出したことはあったはずだ。"A" が "A" であることを知り、魅惑の世界へ第一歩を踏み出した時期があったはずだ。
しかし、(あなたに)そのような記憶がないのであれば、私は呼吸や食事と同じように、読む能力を持って生まれてきたのかもしれないということになる。幸運なことに、私は何度も何度も本を読むことができる。そうでなければ、この旺盛な読書欲を満たすだけの本を手に入れることはできないだろう。
この秋、私はスコットの詩をすべて読み返した。私の幼いころの思い出の一つである。昔の『六王室読本』には、『湖の女』の全編が載っていた。私はいつもその詩をどんなに愛していたことだろう。
その気迫に満ちた描写、ロマンチックな雰囲気、ドラマチックなシチュエーションに魅了された。この詩は、私の熱心な若い心と空想にとって、なんという糧だったことだろう。私は、古い校舎でこの詩をじっくりと読んだものだ。
分数と格闘しているはずの校舎で、あるいは先生がそうしろと言ったときに、この本を熟読したものだ。でも、この本は私の心の支えだった。分数の勉強をするよりもこの本の方がずっと役に立った。心や精神、魂の栄養になった。
少なくとも、スコットの魔法の本を読んでいる間は、空腹や渇きを意識することはなかった。
11月、私はアンソニー・ホープの『ヘンツァウのルパート』を手に入れた。それはある日の午後2時に届いた。私は座ってそれを始め、日が暮れるまで決して動かなかった。そして読み終えた。私は精神的に酔った。どんな酔っぱらいでもそうであるように、私は脳を完全に酔わされた。それから一週間は、何も読むことができなかった。
他のものは読めなかった。読む価値のないものばかりだった。(モンゴメリは熱血冒険物語が好きだったと見える)
あの刺激的な一杯(読後感)の後。実はまだ克服していないのだ。確かに。あのような本を読み続けることはあまり健康的とはいえないだろうねえ、台無しにしてしまうだろう。でも、たまにはちょっと一服。
トランスバール戦争が始まったとき、私は「アフリカの農場の物語」を再読した。これは私のお気に入りの一つである。思索的で、分析的で、どちらかといえば悲観的だ。偶像破壊的で、大胆で、非常に型破りだ。しかし力強く、独創的で、大胆不敵な作品で絶妙なアイデアを含んでいる。トニックのようなもので、苦いけれども爽快だ。また多くの人がこの本を危険な本と呼ぶ。おそらくそうなのだろう。しかし、その鋭い言葉の多くには、快楽よりも真実がある。
私は12月に『ヴァニティ・フェア』を再読した。ずいぶん前に読んだのだが......そのころは少女時代の魅惑的な時代だった。当時はあまり好きではなかった。おそらく、私が抱いていた幻想のいくつかに、あまりにも強くぶつかったからだろう。私は若すぎたのだ。サッカレーを理解するには、当時の私よりもっと成熟した心が必要だ。この冬読んだとき、どうして今までその魅力に気づかなかったのだろう、と思った。ああ、あの愉快なベッキー。
11月に不愉快な経験をした。ある日曜日の夕方ミラー氏がホールで説教をした。私は脇の席に座って、人々が入ってくるのを眺めていた。するとドアが開き、エドウィン・シンプソンが入場してきたのだ! 私は完全に驚かされた。彼がこの島にいることさえ知らなかったからだ。彼は通路を歩いてきて、私の後ろの席に座った。
礼拝が終わると私は、彼に会うのを恐れて、すぐに外に飛び出した。しかしホールは混雑しており、ドアまで行くことができなかった。そこで私たちはポーチの光のまぶしさの中で、顔と顔を合わせたのだ。人は恐ろしい瞬間に遭遇しても、傍観者が夢にも思わないほど冷静になれる。
野次馬達が私が興奮しているとは夢にも思わないだろう。私は冷たく頭を下げ、こう言った。「こんばんは」。エドは帽子を持ち上げて、私と同じように感情のこもらない声で「こんばんは」と言った。そして、彼は去っていきそれは終わった。しかしその影響は何日も私に残った。
10月に英国とトランスバール共和国の間で戦争が起こり、それ以来激しさを増している カナダは国中が熱狂的な興奮状態にある。カナダの少年連隊が南アフリカに志願したからだ。
カナダは岸から岸まで(大西洋岸から太平洋岸まで)興奮状態にある。この島から行った連隊の中に、私の古いPWC(プリンス・オブ・ウェールズカレッジ)ののPWCの古い友人で同級生であるヘドレー・マッキノンがいた。刺激的で戦地から何千キロも離れた、この静かな小さな島でさえも、そのすべてに心を揺さぶられるのだ。誰もが、このニュースに強い関心を寄せている。
1900年5月1日
キャベンディッシュ、P.E.島
1月17日の朝、私はこの電報を受け取って目を覚ましました。
「プリンスアルバート、N.W.T.、1月16日」
Hugh. J. Montgomery(父)が今日亡くなった。肺炎だった。安らかな幸せと苦痛のない死
私の気持ちを言い表す言葉はない。この数週間はただ死を(自分のか?)望んでいた。この知らせは、晴天の空から降ってきた雷のようなものだった。ほんの少し前まで、私は健康で元気な時の彼からの手紙を受け取っており。その次に、あの残酷な電報だった。
ああ、私にとってはとても意味健康で元気な時の彼からの手紙のあるものだった。父親を亡くしても、母親や兄弟姉妹がいる人もいる。
私には祖母しかいない そして父と私はずっと一緒にいた。父はとてもいい人で親切で優しくて ずっと昔、父が西へ行く前、私がまだ小さかった頃、私たちはよく一緒にいてどんなに愛し合ったことでしょう。彼が遠くへ行っても、何年経っても私たちは決して離れ離れになることはなかった。
私たちはいつも近くにいて、親愛なる存在であり続けた。父上、本当にお亡くなりになったのですか? 小さなモーディを一人にしてしまったのですか? あなたらしくない。
今年は長い冬が続いた。私は懸命に生きようとした。勇敢に生きようとしたが難しいな。私はそれを考えると疲れるのだ。この時間帯になると、いつも父のことを思い出すのだ。太陽が沈んで丘の上に薄明かりの影が忍び寄っている。私は一人で父のことを考える。昔を思い出しながらね
そう、この冬は悲しいほど暗い冬だっが、忙しい冬でもあった。仕事があるというのは、なんと幸せなことだろう。
本当に。"神は災い転じて福となす" "神は人を呪わば穴二つ"だ
父の死後数週間は仕事が手につかず、私には働く気にもなれず、野心さえも失われていた。何の役に立とうというのか。成功しようが失敗しようが誰も気にしないのだから。父はいつも私の小さな才能を誇りに思ってくれていたのに、今となっては知る由もなく気にも留めてくれない。
しかし、しばらくして私は再び仕事に取りかかった。その努力の結果力が湧いてきて、生まれながらにして持っていたペンへの愛情が戻ってきたのだ。ああ。働くことができる限り私たちは人生を美しくすることができるのだ。そして人生は美しいものだ。
その真実に日々気づき、その美しさをよりはっきりと見ることができるようになった。もし私たちがそれを見る目と心を持ちさえすれば、世界には私たち皆のために多くのものがある。それを見る目と愛する心、そしてそれを自分のものにする手さえあれば。男にも女にも、芸術にも文学にも、あらゆるところにたくさんのものがある。
どんなに狭くて窮屈な人生でも、楽しみ、喜び、感謝することがたくさんある。感謝することができる。
さて私はこれから一人で世界に立ち向かわなければならない。
このような闘いのために、私の装備を見てみよう。私は若く、学歴も浅く、表面的なものしかない。学問所での一冬とダルハウジー大学での一冬で得た乏しく表面的な教育しか受けていない。
父が遺書で200ドル残してくれたし、この2年間でさらに100ドル貯めた。私は教師としての訓練を受けたわけではない。私は今のところできない。私はどの方面にも何の影響力も持っていない。それだけですか? それは乏しいリストですね。そうそう他にもありますよ、落書きのコツが。
(その価値は)羽の重さなのか、それともやがて私に有利な天秤を重くする黄金の才能なのか。去年はペンで96ドル88セント稼いだんだ。それは(成功のための)贅沢な約束(結果)ではない。しかし、私たちは、見てみよう。私はもう一つの資産を持っている。それはとても価値のあるもので、自分の力を信じることだ。それがある限り私は揺るぎない心で未来に立ち向かうことができる。(しかし、モンゴメリが成功したのも、高尚な学問と言うよりも少女の素朴な不安と希望の話に頼んだからである)
先日、私はラシーヌの『アタリー』を原文で読み直した。それは二重の意味を持っていた。フランス語のブラッシュアップ(理解を深くすること)と、ダルハウジーでの過ぎ去りし日々を思い出すためだ。
ロッティ・シャットフォードと私は、リヒティ教授の部屋でフロントデスクに座り、教授がラシーヌが墓の中でひっくり返るようなドイツ訛りのフランス語を読むのを聞いていた、ダルハウジーでの過ぎ去った日々を思い出すのだ。かわいそうな教授......彼は教授の中でも、なんという珍品だったのだろう。しかし、彼は完璧な紳士で、今では決して見ることのできない立派な「オールドスクール」タイプだった。
最近、「ソロモン王の鉱山」も再読した。私はこの作品が大好きだ。私は冒険が大好きで、子供の頃よりずっと好きなのだ。荒唐無稽でありえない」「文芸に乏しい」と言われようが気にしない。私はもう
そのような批評の規範によって、私の好き嫌いが妨げられることはもうない。
私が本に求める本質的なものは、それが私に興味を抱かせることである。そうであれば他のどんな欠点も許す。
3月にアンソニー・ホープの『王様の鏡』を読んだ。この作品は、彼の他の作品とは全く異なるものである。この本は、ある国王の自伝と称して、彼の幼年時代から結婚にいたるまでを描いている。幼少期から結婚に至るまでの自伝とされているが、非常に興味深い。
私たちの幼い頃の思い入れは、なんと強く残っていることだろう。私はこれまで、王は幸せな存在で、規則に縛られることなく、自分の喜びのためだけに存在し、要するにすべてを華麗に自分の思い通りにすることができる。と信じていた。もちろん、大人になってからそうではないことを理解した。
しかし、「王の鏡」を読むまでは、そのような古い考えに本当の意味で打ち勝つことはできなかった。そのとき私は、信じていたこととはまったく違うことだが、王は他の人々と何ら変わるところがないことを悟った。
王は、悲惨な目にあう危険性がはるかに高く、重要な点での自由度は、現実の最も貧弱な農民よりも低いという点を除けば他の人々と何ら変わりはないのだということだ。だからもう二度と女王になる夢を見ることはないだろう。
つい最近まで、私はフィクションを好んで読んでいた。歴史や伝記には惹かれなかった。しかし最近になって、この点に関する私の好みが大きく変わってきた。フィクションはもはや私を満足させない。現実の男女が何をし、何を考え、何に耐えてきたかを読みたいのだ。
最近マッカーシーの『四人のジョルジュ』やパーク・マンの「ウルフとモンカルム」を読んだが、どれも魅力的だった。後者に関連して私は「ラスト・オブ・モヒカン」を再読した。ネイトから借りて読んだものだ。私たちは二人ともこの物語に魅了され、その登場人物や出来事についてよく語り合ったものだ。
この間の夜、私は会館の図書館からドラモンドの「人間の上昇」を取り出して家に帰り、真夜中過ぎまで読んだ。この本は、進化論について、驚くほど明瞭で説得力のある記述をしている。さらに、ドラモンドは、科学といわゆる
"進化論" とを調和させるための、優れた、しかし完全には成功しているとは言えないような試みをしている。
科学といわゆる啓示を調和させる試みは、うまくいっているが完全には成功していないと思う。彼の類推は、その限りでは良いように思えるが、しかしもしそれを論理的に完成させようとするならば、ドラモンドは、時に科学とはまったく異なる結論に達することを余儀なくされるであろう。彼のこのような試みの弱点は、概してそこにある。
今、私はナンセン(北極探検家)の「最北端」を読んでいる。ロマンスのように読める。しかもあまりに最近の作品なので、まるで自分がその作品に関わったかのように感じられる。私にとってはそれがメアリーと私がP.W.C.にいた頃、私がビデフォードで教えていた頃であると思い出すと、現実味を帯びてくる。
私がダルハウジー図書館を徘徊していた頃、ナンセンは極海を探検し、他の誰よりも極海へ近づいていたのだ。
多くの人が到達しようとしながらも、決して到達することのできない神秘的なボーン(骨、核心地域)に、かつてないほど多くの人が到達したのだ。誰も到達できないと言うのは軽率だろう。私は、いつの日かそうなると思う。今、不老不死のチャンスはほとんどないが、これはその一つだ。
北極点に到達した人には、地上での記憶が保証される。それは考えてみると奇妙なことだ。誰も得をしない。しかしその点では人間の好奇心を満足させるだろうし、
人間の好奇心は、ほとんどすべての価値あることを成し遂げてきたのだから、その気まぐれを甘受するのは当然である。
1900年5月20日、日曜日の夕方
キャベンディッシュ(P.E.島)
都会での土砂降りの雨は好ましくないが、田舎では―どこにも行きたくないときには―雨になる。どこにも行きたくないときにはその魅力がある。今日も雨は降り続いた。
かすかに緑を残す丘や、つぼみが開きはじめた林の上に今日も滔々と降り注いでいる。谷間では、日当たりのいい場所で、青いスミレが色あせた草の間から顔を出して紫の頭巾の下から世界を眺めている。
でも、今は晴れている。明日には、暖かく明るい太陽が顔を出し、草原は一日にしてエメラルド色に染まることだろう。
今晩は、やりたくないことをやらなければならない。エドウィン・シンプソンに手紙を書くことだ。2週間前、私は彼から思いがけない手紙を受け取った。驚きました。彼の手紙はいつもそうだが、私を驚かせた。彼はこう書いていた
私が冬に病気だと聞いていた―父の死後数週間はそうだった。私が冬にインフルエンザと神経痛で体調を崩したことを聞き、それを心配していたこと、そして私に手紙を書いてそのことを伝えてくれないかと頼んだ。
私がどうしているか、何をしているかを手紙で伝えてくれないかと。彼は、断るのは不親切だし礼儀知らずだと思われるような言い方で、その依頼をした。
私は彼にどんな親切を施せるか、きっと恩がある。だから私は彼の手紙に今回だけ返事をしよう。もし彼が次もまた手紙をよこしたら私は返事をしない。私は過ちを犯し重い罰を受けた。そのために重い罰金を払ったが、私はそれを払いもう済ませた。
何度も何度もこの問題を持ち出されるのは、まるで憎い死体を定期的に掘り起こすようなものだ。私の死んだ過去(嫌な記憶)は、その死者を埋葬しなければならない。
たとえ、私が不当な扱いをした男が、大司祭として執り行うことを望む者がいたとしても。私はそれを過去のものとしたのだ......。
1900年6月7日(木曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
.... "Isabel Carnaby" のおかげで昨日は楽しい1時間ほどを過ごすことができた。この本は巧妙だが、あまりにも「おしゃべり」だ。この本に登場する人々は常に「賢い」ことを言い、「賢い」ことを演じることで頭が一杯のようだ。
この本に登場する人々は、「賢い」ことを言ったり、叙事詩を作ったりすることに終始していて、重要なことをする時間がないようだ。また数ページにわたって純粋な輝きを放った後、人は少し眩しく感じ、次のページに進みたくなる。緑色でくすんだものを見て休みたくなる。
しかし。私はこの本をとても気に入ったので鯉の餌食になるのはありがたいことである。
「ジャニス・メレディス(Janice Meredith)」は、これもベストセラーである。確かに私はアメリカ独立戦争はもう飽き飽きだし、ジャニスはもっと長い間物語が展開されていた。しかし、この本は私の小さな本棚の列に加わることを歓迎する。私はときどき仕事(執筆の仕事)から目を離しては、彼ら(本たち)を眺めてはほくそ笑んでいる。みんな私のペットなのだ。
私は以前に読んだことがあり、それがよく身につくとわかっている本でない限り、「一見さんお断り」(評価の高い本)を購入する。買うことができるほど信頼できる作家の本でなければ買わない。そこには好きな詩人や、十代のころに読んだオルコットやジプシーの物語、そして今でも好きな小説がある。機会があればあちこちで手に取った小説もある。
ほとんど擦り切れるまで読み続けた小説がある。読み返したり、貸したり、借りたりして、ほとんど擦り切れるまでになったものだ......。
1900年8月5日(日曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
地獄への道は善意で敷き詰められていると言われるように、私はこのところ少なからぬ貢献をしてきたのではないかと思う。
一ヶ月前からこの日記を書き上げる「つもり」だったのだが、時間があっても気分が乗らず、気分が乗っても時間がない。その気になったら時間がない。しかし不思議なことに、この素敵な日曜日の夜に、気分と時間が一緒にやってきた。
私は自分の娯楽のために少し落書きするために、この窓の開いた「私の古い場所」に座った。
というのも私が文章を書くのは、私の細い財布にいくらかのドルを突っ込むためであり(投稿小説の執筆のため)、多少の利益はあっても、そこにはあまり楽しみがないのだ。昔、自分の書いたものが市場価値を持つようになる前、純粋に好きで書いていたのだから......。
6月、メアリー・キャンベルが結婚した。私は火曜日の午後にダーリントンへ車で行き、5時に到着すると、花嫁に選ばれた女性がチャイムを鳴らしていた。そして他の娘たち(ドナルド・Eにはたくさんの娘がいる)が、一度にたくさんのことをして飛び回っていた。
ドナルド・E.の娘たちの大群が、一度に何十ものことをやって飛び回っていたのだ。私たちはとても楽しかった。そして夕暮れ時メアリーと私は空き部屋に逃げ込み長い間話をした。少女時代の最後の会話だ
そして私たちは少し泣いたのです。
水曜日はいい天気で、忙しい一日だった。夕食後花婿候補のアーチー・ビートンが来た。私は彼を見たことがなかっ。彼は大きくて、静かで、堅そうなハイランダーです。メアリーよりずっと年上のようだ。メアリーは彼のどこを見たのだろう。彼女が彼を深く愛していたとは思えない。
クロンダイク産の金塊が、メアリーの目に映ったのだろうか。ドナルド・E(彼女の父親).は、そのことを強く意識していたに違いない。しかし(花婿が金持ちであることが)メアリーにそこまで影響を与えるとは思えない。
彼が到着した後、私はメアリーの着替えを手伝い、それから来客の応対と結婚祝いの包装を解くのを手伝いに行った。結婚祝いの包装を解く手伝いをした。80人ほどが集まった。夕暮れ時にノーマンがバーティとローラを連れて到着した。8時メアリーは結婚した。式は果樹園の木の下で執り行われた。
結婚式を挙げた人たち、招待客の鮮やかなドレス、そして西の空に沈む夕日の輝き。西の空には夕焼けが広がっていて、とても美しい光景だった。メアリーは私が今まで見た中で、最も落ち着きがあり率直な花嫁だった。
私は桜の木の下に立って、その場にふさわしい厳粛でロマンチックな気分になろうとしたが、どうしたわけかキャンベルの犬がすぐ近くで発作を起こしていたので、なかなかうまくいかなかった。キャンベルの犬が私のすぐ後ろで発作を起こしていて、とても奇妙な、得体の知れない音を立てていたからだ。
それが終わると、式は終わったが発作は起こらず、私と少女たちは明かりをつけに飛んでいった。夕食の後、牧師は気を遣って家に帰り、残りの私たちは、「瞑想」をすることにした。
ダンスに没頭した。庭に立派な大きなダンスパビリオンがあり楓の枝で屋根が覆われていた。理想的な舞踏会場になった。
夜露がなく、空気は常に冷たく澄んでいた。私たちは3人のバイオリン弾きを連れていた。ダンディーなダンサーがたくさんいた。私たちはとても楽しい時間を過ごした。私たちは一晩中踊り続け、最後の踊り手を終えたときちょうど太陽が昇っていた。それから朝食をとり、無慈悲な日の光の中で、私たちはかなり疲労した様子だった。
しかし、朝食後私は生存者全員の写真を撮り、それから花嫁のペアを駅まで送った。多くの少年たちが米を何ポンドも持ってやってきて、パディ・クラークンと私は、メアリーの日傘を持って材木の山の陰からこっそり抜け出した。その中に米を入れた。メアリーは疑いもせずそれを持って出て行った。メアリーがそれを開けた時にそばにいたら、私は梅干しをあげただろう。
私はその日、とても疲れて眠くなりながら帰宅した......。
1900年10月7日(日曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
...今日の午後、私は「ウンディーネ」を再読していた。その絶妙で小さな牧歌的な作品だ。私はこの作品を何年も前、10代の初めに読んだ。ネイトが持っていたのだが、文学者の叔父からもらった小さな本だった。
ある日、彼が学校から持ってきてくれたので、私は自分の机の後ろで、そのようなことをするにはとても便利な、あの楽しい広々とした古い「背もたれ」の中で、それをすべて読んだ。その頃、私は間違いなくイギリスの歴史か地理を勉強しているはずだった。
でも、そうしていたら歴史のことはすぐに忘れてしまっただろうし、ウンディーネのことは決して忘れてはいない。
ウンディーネを。この本を読み終えたとき、私は厳粛な誓いを立てた。この本を手に入れようと。
先日チャイナタウンでカーター書店に行った。そこは本や新しい雑誌の香りが、甘い香のように私の鼻孔を満たしていた。私はそのとき、白と金で装丁されたウンディーネの最愛の版を見つけたのだ。
その魅力は、何年も前に白い小さな机の上に置かれた茶色い机の後ろにいたときと、まったく同じように強力なものであることを私はうれしく思った。
その魅力は、何年も前に、白い校舎の茶色い机の後ろで、私をバイパス・メドウに誘い込み、空想の世界を開かせたときと、まったく同じであることを、私はうれしく思った。
それは、結局のところ古典の真価が問われるところである。子供の頃から白髪になるまで、すべての年齢層を満足させなければならない。それこそが古典の真骨頂である。
先週、私は展覧会に出席するため、そして私の白髪に刺激を与えるため、チャイナタウンに行った。
先週、私は長町に行き、展覧会に出席して、私の白髪を少しかき乱しました。いつも同じ場所にいると、コケるんだよ。と思っていた。
しかし、そこで!? 自分のスタイルに嫌気がさしてきたので、今夜はもう止めます。今夜はこの辺で。
1900年10月18日(木曜日)
キャベンディッシュ(PE島)
10年前、15歳の学生の頃、私は「10年書簡」を書くことに熱中していた。10年後に開封されて読まれる手紙という意味だ。どこで思いついたのかよくわからない。パンジーの本で読んだことがあるような気がする。
とにかく、とても素敵でロマンチックに思えたので自分なりに採用したのだ。そして10年は正に一生(もの長い期間に思えた)、25歳は実に由緒正しい年齢のように思われた。
今、この手紙を読むのは、かつて期待したような喜びはない。それどころかまるで幽霊の手紙を読んでいるような、墓の向こうの手紙を読んでいるような、そんな不気味な感じがするのだ。喜びよりも苦痛の方がはるかに大きい。
今晩8時に、10年前にプリンス・アルバートの古い「サウスビュー」で書かれたこの書簡の一つを開かなければならなかった。10年前プリンスアルバートのサウスビューに住んでいたエディス・スケルトンが書いたものだ。私はそれを書いた夜のことをはっきりと覚えている。
私たちはいつものように陽気に過ごしていた。イーディスはとても陽気な女の子だった。私たちはとても軽い気持ちでその手紙を書いた。私たちの友情が何年も続くとは思ってもみなかった。しかしそのようなことはなくただ去っていった。イーディスとは6年も音信不通だ
彼女は私の手紙を開いてくれただろうか?
私は彼女の手紙を開いて読んだ。陽気な手紙で昔の冗談がいっぱいだった。そのうちのいくつかはすっかり忘れていて、その意味するところが全くわからない。しかしイーディスの才能は手紙を書く方面には向いていなかったのだ。そして、それを読むために10年間保管しておく価値はないだろう。
1900年11月10日(土曜日)
キャベンディッシュ、P.E.I.
今日、「グッド・ハウスキーピング」11月号が届いたが、私の詩がいくつか掲載されていた。私の詩「一足のスリッパ」が掲載されている。私はこの機会に言及する価値があると思う。
というのも、この詩は1ページまるまる使われ、イラストも描かれていたからだ。私の詩がこのように名誉を受けたのは初めてのことだ。しかしその姿は威厳に満ちていて、うっかりしているとその中に何かあるのではないかと錯覚してしまう。
本当に何かあるのではと思わせるほど威厳があった。この挿絵を描かせる気になった編集者に祝福を。私の自尊心を大いに高めてくれた。
かなりね。
1900年12月22日(土曜日)
プリンスエドワード、キャベンディッシュ
世紀末を祝うホワイト・クリスマスを迎えることができそうだ。冬がやってきた。私は冬が嫌いだ。夕方一人で外をうろつくことができないからだ。薄暗い冬の夕暮れ時に一人で外を徘徊することができないからだ。
暗い部屋にもぐりこんで、ちょっと心労をねぎらうしかない。もし夏だったら木々や星々の下に逃げ込んで、私の魂はその美しさで心が満たされ、痛みなど感じなくなる。確かに、
私は今夜体質を改善するために不機嫌な顔をして出かけた。誰にも会わずに広場を歩き回った。寒くて澄んでいて白くて、白くて、白くて、どこもかしこも白くて、魂がなく生気がない。
西側にはオレンジ色の帯が走り、低地のはるか下には海が広がっていた。海は黒く、不機嫌だった。私は広場の周りを歩き、そして決心がつき、広場に入った。外はあまりにもひどく静かで寂しく、ひどい沈黙を破るために叫びたくなった。
家の中にいてもあまりいいことはない。おばあちゃんは座って縫い物をしたり、新聞を読んだりしている。私は座って本を読んだり文章を書いたりして、自分の心を食べ尽くす。この単調さはひどいものだ。私はそのようなことに反抗したことはないが。
この冬、私はそうする(反抗する)。確かに私は自分の反抗を自分の胸にしまっておき、誰もそれを疑わないが、しかしそれはすべての人のために煮えたぎって発酵しているのだ(回り中の人に文句がある)。
私は明るく陽気な仲間、笑いきらめくような会話が大好きだ。私には何も得られない。祖母はいつも控えめで、よそよそしい女性だった。誰よりも気遣いのないよそよそしい女だった(冷たい女か)。
他の人がそれを好んだり望んだりすることに奇妙な憤りを感じていた。私の内面はほとんどの場合、完全に一人で生きてきた。最も付き合わなければならなかった人たちは、どんな時も、どんな危機の時も私から最も遠いところにいた。
私にとって本当に助けになり、インスピレーションを与えてくれる友人はめったに私の近くにいない。大きな魂の孤独を感じることがある。そして精神的にも、私はいつも一人で立っていなければならなかった。それが強さにつながっているのだろう。しかしそれは難しい。
さて、そろそろ唸るのをやめよう。でも本当に呪文(他人が言う悪口)には不満があるのだ。私は些細な、つまらない、絶え間ない悩みの垣根で四方を塞がれたような気がする。神経を逆なでするようなものだ。
今夜、古い手紙を読み返しながら、ハーマンの手紙を読んでみた。でもできなかった開いて、最初のページを読んだらたたんでしまってしまった。耐え難い痛みだった。なんという、あの男は私にどんな影響を与えたのだろう。彼のマークは私の魂に永遠に焼きついている。彼の死から2年経った今、ありふれた言葉しか書かれていない彼の粗雑で人間味のない手紙を読む気にはなれない。
まるで残忍な手が私の心の琴線に触れて、それを好きなように引きずっているような気がしてならない。と思うのだ。しかし今は彼のことを考えることはあまりなく、あの荒々しい情熱は彼とともに死んで葬られた。今夜のように、彼の手紙や彼について書かれたこの日記のページを読もうとするときだけ昔の情熱がよみがえるのだ。
この日記のページを読もうとするときだけ、昔の苦しみが目を覚まし、頭を持ち上げて、かつての力を忘れようとするのだ。
結局のところ、あらゆる落胆と心労にもかかわらず私はある意味でうまくいっているのだ。ある意味ではうまくいっている。つまり筆で生活できる収入を得始めているのだ。外見上はうまくいっている。内面的なことはすべて騒いでいるのだ(心は落ち着かない)。
そうだ私はうまくいっているし、これからうまくいくつもりだ、どんな反発や落胆や失敗があろうとも、挫折や落胆、失敗があろうとも 私はこれまで、この「嫌な気分の三重奏」を征服してきた。(大作家になる挑戦を)続けるつもりだ。「人(かつての偉人たち)がしたことを、人がすることができることを」。
では行ってくる。この不平不満は私に良い結果をもたらした。私はこの日記で革命的な傾向(大暴れしたいと言う傾向か)をすべて解消している。
この日記に書いている。もしこの「行った」ことがなかったら、私はいつか千々に飛ぶかもしれない。
[この項終わり]